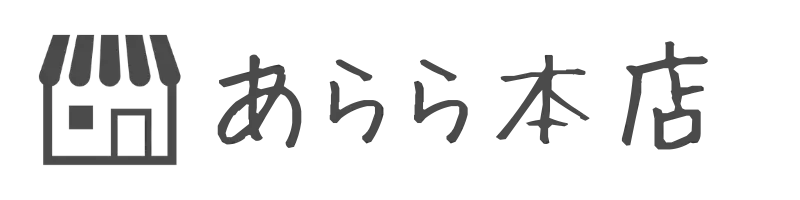樋口一葉『十三夜』現代語訳・全文
上
いつもなら威勢のよい高級な人力車で帰り、「それ、門の前に音がした、娘じゃないのか」と両親に出迎えられるものだが、今夜は適当に拾った人力車で帰ってきて、しかも家の前まで車を付けることもせず、しょんぼりと格子戸の外に立っていた。家の中では父親が相変わらずの高声をあげていて、
「言ってみれば私も幸福な人間の一人、いずれもおとなしい子どもを持って、手がかからないので人には褒められる。これ以上の望みもないし、本当にありがたいことだ」
と言うのが聞こえる。
「あの相手はきっと母親だろう。ああ、何も知らずにあんな風に喜んでおられる。どんな顔をして夫と離縁したいと言えばいいのだろうか。叱られるに違いない。息子の太郎までも家に置いて出てきた決意をしたのは、色々考え尽くした結果ではあるけれど、今さら両親を驚かせて、これまでの喜びを水の泡にしてしまうことは辛い。いっそ話さずに戻ろうか。戻ればこれまで通り太郎の母で、両親には高級官吏の婿がいることを鼻高く思わせてあげられる。私さえ我慢すれば、両親にもよい暮らしを続けさせてあげられるのに、思うままを通して離縁してしまったら、太郎も両親も悲しむだろう。それに弟の行く末もある。戻ろうか戻ろうか。あの鬼のような夫の元に戻ろうか。あの鬼の、鬼の夫のもとへ。ああ考えるのも嫌だ嫌だ」
と身をふるわせた途端、よろけて思わず格子にがたりと音をさせてしまえば、
「誰だ」
と大きく父親の声、近所の子どものいたずらと勘違いしているらしい。
外で「おほほ」と笑って、
「お父様、私でございます」
といかにも可愛いらしい声、
「やあ、誰だ、誰であった」と障子を引き開けて、
「ほう、関か。なんだそんな所に立っていて。どうしてまたこんな遅くに出かけてきた。車もないし女中も連れていないのか。やれやれ、まあ早く中へ入れ。どうも不意に驚かされたからうろたえてしまう。格子は閉めなくてよい、私が閉める。ともかくも奥に行きなさい。ずっとお月様のさす方へ。さあ座布団に座れ。どうも畳が汚いので、大屋に言ってはおいたのだが、どうも職人の都合があるらしい。遠慮はいらない。着物が汚れるからそれを敷いておくれ。やれやれ、どうしてこんな遅くに出てきた、みんな元気にしてるのか」
といつもと同じように持てなされるので、心苦しく思いながらも感情を押さえて、
「はい、みんな元気にしております。申し訳なくご無沙汰をしておりましたが、お父様もお母様も元気でいらっしゃいますか」
と問えば、
「いやもう、私はくしゃみ一つしないくらいだ。お袋はたまに頭痛などするが婦人特有のもので、数日も経つとけろりとしているから問題はないさ。」
と元気よくからからと笑っている。
「亥之助が見えませんが、今晩はどこかへ行ったのですか。あの子も変わらず勉強でしょうか」
と聞けば、母親は笑顔でいそいそとして茶をすすめながら、
「亥之は今さっき夜間学校に出て行きましたよ。あの子もお陰様でこの間は昇給させて頂いたし、課長が可愛がって下さるので安心です。これと言うのもやはり原田さんが口をきいてくれたからだと、うちでは毎日のように言っていますよ。亥之はあの通り口数の少ない性格だから、もし原田さんに会ったとしても簡単な挨拶しかできないと思う。どうかお前が間に立って、私どもの心が通じるよう、亥之助の行く末をも頼んでおいておくれ。ほんに季節の変わり目で天気がすぐれないけど、太郎さんは元気ですか。なぜに今夜は連れてきていない、お父さんも恋しがっていたのに」
と言われて、また物憂げな気持ちになり、
「連れてこようと思ったのですが、あの子はもう寝たのでそのまま置いてきました。本当にいたずらばかりで、外に出ると足跡を追って、家にいれば私の傍ばかりにきて、ほんとうに手がかかってなりません。どうしてあんな風なのでしょう」
と言いながら太郎のことを思い出すと、涙が胸の中にみなぎるようで、「思い切って置いては来たけれど、今頃眼をさまして、母さん母さんと泣いているに違いない。女中は迷惑がって、鬼に喰わすなどと言いおどかしているだろう。ああ可哀想なことを」と、声を立ててでも泣きたいものだが、両親の機嫌が良いのでおさえて、こんこんと空咳で涙をごまかした。
「今夜は十三夜、昔風で古めかしい風習だけれど、団子をこしらえてお月様におそなえしていたのよ。これはお前の好物だから、亥之助に持って行かせてあげようと思ったけれど、亥之助も何かきまりを悪がって、そのような物はおよしなされと言うし、十五夜の後だから片見月(*十五夜と十三夜のどちらかだけ月見をすること。縁起が悪い)になっても悪いし、食べさせたいと思いながらも上げることが出来なかった。今夜来てくれるとは嬉しい偶然、ほんに心が届いたのであろう。そちらで甘い物はたくさん食べるだろうけれど、親がこしらえたのはまた別物、奥様の雰囲気は取って、今夜は昔のお関になり、見栄を構わず豆でも栗でも、好きな物を食べておくれ。
いつでも父様と噂をしているのだけど、お前は立派なところに嫁いだから、位の高い人や、身分のある奥様方とのお付き合いもして、原田の妻と名乗っているからには、気苦労の多いこともあるだろう。女中の使い方、来客への心配り、人の上に立つものはそれだけに苦労が多く、実家がこのような身分ならなおさらのこと、人に侮られないよう心懸けてもおかなければならない。そんなことを色々に思ってみると、父さんも私も孫の顔を見に行きたいのは山々なのだけど、あまり頻繁に出入りをして迷惑になってもいけないし、御門の前を通ることはあっても、こんな貧しい身なりで入っていけるはずもなく、二階のすだれを見上げながら、お関は何をしているだろうと思いやるばかりで通り過ぎてしまう。実家ももう少し身分が良ければ、お前の肩身も広いだろうし、同じ苦労でも少しはましに思うだろうに。お月見の団子をあげようにも、粗末だから恥ずかしいではないか。ほんにお前の心遣いが思われる」
と嬉しい中にも思い通りの交際が出来ないことを、自分たちの身分が低いことと一緒に情けなげに言われて、お関は、
「本当に私は親不孝だと思います。たしかに絹の着物を着て、自家用の人力車に乗っている時などは、立派らしくも見えるかもしれませんが、父さんや母さんにこうしてあげようと思うこともできず、言わば自分一人だけの贅沢、いっそ内職仕事をしてでも、二人のおそばで暮らした方がよっぽど快いと思います」
と言い出して、
「馬鹿、馬鹿、そんなことを仮にも言ってはいけない。嫁に行った身が実家の親に仕送りをするなどおかしいこと。うちにいるときは斉藤の娘、嫁入りすれば原田の奥方ではないか。勇さんの気に入るようにして、家の内をとりしきって行けばそれで良いのだ。苦労も多いだろうが、身分のある人の夫人になれるだけ運のあるお前なら、堪えられないことはないだろう。女などという者はどうも愚痴っぽくて、お袋などがつまらないことを言い出すから困り切る。いやどうも、今日も朝からお前に団子を食べさせることができないと言って、かなり立腹であった。だいぶ熱心にこしらえたと見えるから、たくさん食べて安心させてやってくれ、余程うまいことだろう」と父親がおどけてみせるので、また夫と離縁したいということを言いそびれて、ごちそうの栗や枝豆を頂いた。
嫁に行って七年の間、お関が夜になって実家を訪れて来たことはなく、土産もなしに一人で来るなど全く例のなかったこと、気のせいか衣類もいつもほどきらびやかではない。久々に会った嬉しさに、たいして気付かなかったけれど、婿からの伝言も何のあいさつもなく、無理に笑顔を作りながらどこか元気のないところは、何か理由がなければならない。父親は机の上の置き時計を眺めて、
「こりゃ、もうすぐ十時になるが、関は泊まって行ってよいのかの。帰るならばもう帰らねばならないぞ」
とそれとなく関の気持ちを探ってみた。そんな親の顔を娘は今さらのように見上げて、
「お父様。私はお願いがあって来たのでございます。どうぞ聞いて下さい」
と意を決して畳に手を突いたとき、はじめて涙をひとしずく流し、胸に積もった憂いの数々を言い始めた。
父は不安な顔色をして、
「改まってどうした」
と膝を進めれば、
「私は今夜限り、原田の家へ帰らないつもりで出て参りました。勇の許しで来たのではなく、太郎を寝かしつけて、もうあの子の顔を見ない決心で出て参りました。お父様、お母様、察して下さい。私は今日までたったの一度も、原田家での生活について二人のお耳に入れたことはなく、また勇と私の仲を人に言ったことはありませんけれど、何度も何度も考え直して、二年も三年も泣き尽くして、今日という今日、なんとしても離縁を貰って頂こうと固く覚悟を決めました。どうぞお願いです。離縁状を受け取って下さい。私はこれから内職なり何なりして、亥之助の片腕にもなれるようにしますので、一生一人で置いて下さいませ」
とわっと声を立てるのを、袖の下で我慢する姿は、羽織に描かれた墨絵の模様も涙で紫色に変わりはしないかと、しみじみ心を打たれる。
「それはどういう理由で」
と父も母も詰め寄って問いかけると、
「今までは黙っていたのですが、私の家の夫婦のやりとりを半日見て下さると、たいていお分かりになるでしょう。話すのは用事のあるときだけで、それも荒々しく申しつけられるばかり。朝起きて機嫌を聞くと、私の言葉は無視して、脇を向き庭の草花をわざとらしく褒めるばかり。これに腹も立ちますが、夫のすることならと我慢しています。言葉争いをしたこともない私ですが、朝食の時から小言は絶えず、召使いの前でさんざんと私の身の不器用無作法を指摘して、それはまだ辛抱もしますが、二言目には教育のない身、教育のない身と私を蔑むのです。もとより私は上流の教育を受けて育った者ではないに違いなく、御同僚の奥様方のように、お花やお茶、歌や画などを習ったこともないので、お話しのお相手は出来ませんが、出来なければ出来ないで、習わせて下されば済むべきはず。私の実家の身分が悪いことを表に言いふらして、女中たちが軽蔑するよう仕向けなくてもよいでしょう。お嫁に行ってから半年くらいの間は、関や関やと非常に大切にして下さったけれど、太郎が産まれてからというものは、まるで人が変わってしまって、思い出しても恐ろしいほどです。私は暗闇の谷に突き落とされたように、暖かい日の光を見たことがありません。
はじめのうちは冗談で、わざと素っ気ない態度をしているのかと思っていたのですが、本当のところは私にお飽きなされたようで、色々の嫌がらせをして私を追い出そうといじめるのでございます。お父様もお母様も私の性格はご存じでしょう。もし夫が芸者遊びに耽ろうとも、妾を囲って置いておこうとも、そんなことに嫉妬する私でもなく、実際女中たちからはそんな噂も聞こえてくるのですが、あれほど仕事の出来るお方ですし、男のひとならそれくらいはよくあることだろうと、他の女性のところへ通うときには、むしろ夫が着ていくものにも気を付けて、気に逆らわないように心懸けているのですが、ただもう私のすることは何でも気に入らないようで、日常の細かなこと全てから、『家の中が楽しくないのは妻の振る舞いが悪いからだ』とまでおっしゃります。それも、どういうところが悪い、ここが面白くないと言って下さるのならいいですが、ただただ『つまらぬくだらぬ、解らぬ奴。とても話の相手にはならぬ』だの、『言ってみれば太郎の乳母として置いてやっているのだ』だのと、私を嘲っておっしゃるばかり。ほんに夫というものではなく、あの方は鬼でございます。ご自分の口から出て行けとはおっしゃりませんけれど、私がこのような意気地なしで、また太郎を思うと気が引けるので、夫の言いつけに背くこともせず、はいはいとお小言を聞いておりますと、『張り合いも意気地もないはっきりとしない奴、だから気に入らないのだ』とおっしゃります。もし、そうかといって少しでも私の言い分を立てて、負けん気にお返事をしましたら、それをきっかけにして出て行けと言われるのは目に見えています。私はお母様、家を出るのはなんとも思わないのです。名前だけ立派な原田勇に離縁されたからといって、少しも惜しいとは思いません。けれど、何も知らないあの太郎が、片親になるかと思いますと、意地も自分の意見も出さず、詫びて機嫌を取って気を遣っていく方が良いかと、今日まで何も言わずに辛抱していました。お父様、お母様、私は不運でございます」
と娘がくやしさ悲しさを口に出して、思いも寄らないことを語るので、両親は顔を見合わせて、いやはやそのように辛い仲だったのかとあっけに取られて、しばらく言葉も出なかった。
母親は子に甘いものなので、聞いたどのことを取っても自分のことのように口惜しく、
「父様は何と思ったか知りませんが、もともとこちらから貰ってやって下さいとお願いして嫁にやった子ではなし、身分が悪いだの、学校がどうしたのとよくもよくも、勝手なことが言えたものです。向こうは忘れたかもしれませんが、こちらはたしかに日にちまで覚えている。お関が十七のお正月、まだ門松の置いてある七日の朝のことでした。もと住んでいた猿楽町の家の前で、お隣の小さい娘と羽根つきをして遊んでいると、あの子の突いた白い羽が、通りかかった原田さんの車の中に落ちて、それをお関が貰いに行ったら、その時見そめたとか言って、仲立ちする人を次々とよこして強引に求婚してきたのです。お身分が釣り合いませんし、こちらは全くの子どもで、何も稽古事は習わせていないし、嫁入り支度も貧しい状態ですから何も出来ないと言って、何度断ったか分かりませんけれど、何も舅姑の口うるさいのがいるわけでもないし、わしが欲しくてわしが貰うのだから、身分も何も言うことはない、稽古は引き取ってからでも十分にさせられるから、その心配もいらない、とにかく嫁にくれさえすれば大事しますからと、それはそれはあわただしく催促して、こちらから強請ったわけではないけれど、嫁入り支度まで向こうが調えてくれた。言うなればお前は恋愛で嫁に行った者、私や父様が遠慮してむやみに家の出入りをしないというのも、勇さんの身分を恐れてではない、妾として貰われたわけでもないし、正当に何度も頼みこんで貰っていった嫁の親だから、大威張りに出入りしても差し支えないだろうけれど、勇さんが立派にやっているのに、こちらがこの通り貧しい生活をしていれば、娘を利用して婿の助けを受けるつもりかと、他人がつまらぬ噂をすることを思えば口惜しいので、痩せ我慢ではないけれど、付き合いだけは相手の身分に合わせて、いつもは会いたい娘の顔も見ずにいるのです。
それなのに何の馬鹿馬鹿しい、親のない子でも拾っていったように偉そうな。学問や稽古事が出来るの出来ないのと、よくそんな口が利けたものです。お関が黙っていては際限もなく募って、それはそれは癖になってしまいます。そもそも女中どもの手前ですから、奥様の威光がなくなって、しまいにはお前の言うことを聞く者もなくなり、太郎をしつけるにも、母親を馬鹿にするようになってしまったらどうします。言うだけのことはきちんと言って、それがきっかけで小言を言われたら、なんの私にも家がありますと言って、出てくるとよいではないか。本当に馬鹿馬鹿しいといっては、それほどのことを今日という今日まで黙っているということがありますか。あんまりお前がおとなしすぎるから、わがままを言いつのられたのでしょう。聞いただけでも腹が立つ。もうもう引き下がっていなくともよかろう。身分が何であろうが、父もいて母もいる。年は若いが亥之助という弟もいるので、そのようなつらい境遇にじっとしていなくてもよいでしょう。なあ父様、一度勇さんに会って、十分とっちめてやったらよいでしょう」
と母は興奮して乱暴なことまで言い出す。
父親はさっきから腕組みをして目を閉じているのだが、
「ああお袋、無茶なことを言ってはならん。わしも初めて聞いてどうしたものかと考えに困る。お関のことなので、並大抵のことではこのような話を持ち出すはずもなく、本当に辛くなって出てきたと見えるが、それで今夜は婿どのは留守か、何か大変な事件でもあったのか。いよいよ離縁すると言われて来たのか」
と落ち着いて問うと、
「夫は一昨日から家に帰っていません。五日六日と家を空けるのはいつものこと、別段珍しいとは思いませんけれど、出る際に着る服のそろえ方が悪いといって、いくら詫びても聞き入れてもらえず、それを脱いで叩きつけて、ご自分で洋服に着替えなさって、『ああ、わしくらい不幸せな人間はいないだろう、お前のような妻を持ったのは』と言い捨てて出て行かれました。なんということでございましょう。一年三百六十五日ものを言うこともなく、たまに言うことはこのような情けのない言葉をかけられて、それでも原田の妻と言われたいか、太郎の母だとうわべは平然としているのか、自分でもなぜ辛抱しているのか分かりません。もう私は夫も子どももありません。嫁入りしていない前に戻ると思えばそれまで。あの幼い太郎の寝顔を眺めながら、置いてくるほどの気持ちになったほどなので、もうどうしても勇のそばにいることは出来ません。親はなくとも子は育つと言いますし、私のような不運な母の手で育つより、誰でも勇さんの気に入った人に育てて貰ったら、少しは父親も可愛がって、後々あの子のためにもなりましょう。私は今夜限りどうしても帰ることは致しません」
と言うが、絶とうと思っても絶てない可愛い子どもがいるために、口ではきっぱりとした言い方をしているのに対して、言葉はふるえている。
父は嘆息して、
「それほどのことなら無理もない、居づらくもあろう。困った仲になったものよ」
としばらくお関の顔を眺めていたが、大丸髷(*人妻の髪型)に金の輪の装飾を巻いて、黒い豪華な絹羽織を惜しげもなく着こなしているところを見ると、我が娘ながらもいつのまにか奥様らしさが自然と出ている。「この髪を結び髪(*長髪をぐるぐると巻いただけの簡略な髪型)に結いかえさせて、粗末な羽織にたすき掛けで炊事や洗濯をさせるなど、どうしてそんなことが親として堪えられようか。太郎という子もあるし、一瞬の感情に任せて一生を棒に振れば、他人には笑われ者となり、その身は斉藤主計の娘に戻ったならば、泣いても笑っても、再び原田太郎の母に戻ることは出来ない。夫に未練は残さないかもしれないが、我が子に対しての愛は絶ちにくく、離れていても子どものことを思うはずだ。あのまま苦労してでも離縁しなければ良かったと思う心も出てくるだろう。お関はこのように美しく生まれたためにかえって不幸だ。身分不相応の人と縁を持って、多くの苦労をしている」と哀れに思う気持ちが増したけれども、
「いやお関、こう言うと父が無慈悲でくみ取ってくれないと思うかも知れないが、決してお前を叱るのではない。身分が釣り合わなければ思うことも自然と違って、こちらは本当に尽くす気でも、取りようによっては面白くなく見えることもあるだろう。勇さんもあの通り、物の道理を心得た賢い人だし、ずいぶん教養のある人でもある。無茶苦茶にいじめ立てるわけでもないだろう。まあ世間で褒められる働き手などと言うのは、極めて恐ろしいわがまま者のことが多い。外では普通の顔をして切り回していているが、勤め先の不平などまで家に持ち帰って当たり散らされる、その的になっては随分辛いこともあるだろう。だけれどそれほどの夫を持つ者のつとめ、安月給の下級官吏が生活を支えてくれるのとは格が違う。だから文句を言われることも、難しいこともあるだろう。それを機嫌の好いようにととのえて行くのが妻の役目だ。表面には見えないけれど、世間の奥様という人たち、みんなが楽しく幸せな夫婦仲ばかりではない。辛いのは私だけだと思うと恨みも出る、これが世のつとめだ。とりわけこれほど身分の違いもあれば、人一倍の苦しみもある、お袋などがえらそうなことは言うけれど、亥之が昨今の月給にありついたのも、つまりは原田さんの口利きではないか。七光りどころか十光もして、間接的な恩を受けていないとは言えないだろうし、辛くても一つは親のため、弟のため。太郎という子もあるからして、今日までの辛抱が出来たのならば、これから先も出来ないことはない。離縁をして家を出たならば、太郎は原田のもの、そちは斉藤の娘になる。一度縁が切れては、二度と顔を見に行くことはできないだろう。どうせ不運に泣くのであれば、原田の妻という立場で大泣きに泣け。なあ関、そうではないか。納得したなら全て胸の中に納めて、知らぬ顔で今夜は帰って、今まで通りつつしんで世を送っておくれ。お前が口に出さなくても親も察する、弟も察する、涙は各自に分けて泣こうじゃないか」
と言い聞かせて父自身も目を拭えば、お関はわっと泣いて、
「それでは離縁をと言うたのもわがままでございました。なるほど、太郎と別れて顔も見られないようになれば、生きていても甲斐がないというもの。ただ目の前の苦しみを逃れたとてどうなるものでもありません。ほんとうに私さえ死んだ気になれば、三方四方、もめ事も起きず、ともあれ、あの子も両親の手で育てられるというのに、つまらぬことを考えつきまして、お父様にまで嫌なことをお聞かせしてしまいました。今夜限り関という身はなくなって、魂一つがあの子の身を守ると思えば、夫が私に辛く当たるくらい、百年でも辛抱できそうなことです。お言葉もよく納得がいきました。もうこんなことはお聞かせ致しませんので、どうか心配なさらないで下さい」
と言って、拭うあとからあとから涙を流し、母親は声を立てて、
「何というこの娘は不仕合わせ」
と大雨が降ったように泣き、曇がかかっていない月もちょうど淋しげで、弟の亥之がうしろの土手から折ってきて、瓶に挿しているすすきの穂が風になびいて手招くように見える様子さえも、どことなくもの悲しい夜だ。
実家は上野で、原田の家がある駿河台の高級住宅地へと続く路の途中にある。周りには木々が茂り、樹木の下は暗くて心細いけれど、さいわい今夜は月が明るく、大通りまで出れば昼も同様。いつも利用する人力車屋もない家なので、通りかかった車を窓から呼んで、
「納得がいったのならともかく帰りなさい。主人の留守に断りなしの外出、これを咎められるとお前も立場が悪かろう。少し時刻は遅くなったが、人力車ならひとっ走りで着く。話はまたゆっくり聞こう。まず今夜は帰った方がよい」
と言い、手を取って引き出すようにするのも、事をおだやかに済ませようとする親の慈悲を感じる。お関はこれ以上どうすることも出来ない身の上だと覚悟して、
「お父様、お母様、今夜のことはこれ限り。帰ってしまうので、私は変わらず原田の妻です。これ以上夫を非難するのは申し訳ないので、もう何も言いません。関は立派な夫を持ったから、弟のためにも良い片腕だ、ああ安心できると喜んでいて下されば、私は何も思うことはありません。絶対に家出や自殺など間違った考えを起こすようなことはしませんので、それもご安心下さい。私の身体は今夜以降勇のものだと思って、あの人の思うままにどうなりとでもしてもらいましょう。それではもう私は戻ります。亥之さんが帰ったらよろしく言っておいて下さい。お父様もお母様もご機嫌よう、この次来るときには笑って参ります」
と元気なさげに立ち上がれば、母親はお金など入っていなさそうな財布を持って出て、駿河台までいくらで行けるかと、門前で待っている車夫に声をかけるのを制して、
「あ、お母様、それは私が払います。ありがとうございます」
とおとなしく挨拶をして、格子戸をくぐれば顔を袖で隠し、涙を見せまいとしながら乗り込む姿が不憫である。家にいる父が咳払いをするが、これも涙ぐんだ声をしている。
下
清く澄んだ月に風の音もして、虫の音も途切れ途切れに聞こえて、もの悲しい上野に入ってから、まだ家までは少し距離があると思っていると、どうしたのか、車夫は急に車を止めて、
「誠に申し訳ありませんが、私はここまでで失礼致します。代金はいりませんのでお降り下さい」
とだしぬけに言われた。思いもかけないことだったので、お関は胸をどきりとさせて、
「あれ、お前、そんなことを言っては困るではないか。少し急いでもいるし、約束の代金よりも余分に上げるから行っておくれ。こんな淋しいところでは代わりの車もないではないか。それはお前、人困らせというもの、愚図らずに行っておくれ」
と少しふるえて頼むように言えば、
「余分にお代が欲しいと言うのではありません。私からのお願いです、どうか降りて下さい。もう車を引くのが嫌になったのでございます」
と言うので、
「それではお前具合でも悪いのか。まあどうしたというのだ。ここまで乗せてきて嫌になったでは済まないだろう」
と声に力を入れて車夫を叱れば、
「許して下さい、もうどうしても嫌になったのですから」
と言い提灯を持って、押していた車から手を離し、身体を横によけてしまったので、
「お前はわがままな車屋さんだね。それならば駿河台までとは言いません、代わりの車があるところまで行ってくれれば良い。代金は払うのでどこか都合の良いところまで、せめて大通りまでは行っておくれ」
と優しい声で機嫌をとるように言えば、
「なるほど若いお方ですし、こんな淋しいところへ降ろされては、たいそうお困りになるでしょう。これは私が悪うございました。ではお乗せいたしましょう、お供いたしましょう。さぞ驚かれたでしょう」
と言って悪者らしくもなく、また車を引いていこうとすると、お関もようやく胸をなで、安心げに車夫の顔を見れば、年は二十五、六で肌は日に焼けて黒く、背は小さくてほっそりとしている。
「あ、月に横向けた顔が、誰か見知りの人のような気がする、誰かに似ている」と人の名前も喉まで出そうになりながら、
「もしやお前さんは」
と思わず声をかけると、
「え」
と驚いて振り向く男、
「あれ、お前さんはあのお方ではないか、私をまさかお忘れではないでしょう」
と車からすべるように降りてつくづくと見つめると、
「あなたは斉藤のお関さん。面目ない、こんな姿で。うしろに目が付いていないので何も気がつかずにいました。それでも声で気づくべきはずのものを、私もよっぽど鈍感になりました」
と下を向いて身を恥じれば、お関は頭の先から爪先まで眺めて、
「いえいえ私も同じようなもの。通りですれ違ったくらいでは、よもや貴方と気づかないでしょう。たった今の今までも、知らない他人の車夫さんと思っていたのですから。ご存じないのは当たり前、恐れ多いことではありましょうが、知らなかったことを許して下さい。まあいつからこんな仕事をしているのですか、そのか弱い身体に差し障りませんか。あなたの伯母さんが田舎に帰らなければいけなくなって、小川町のお店をたたんだという噂は、よそながら聞いてもいましたが、私も結婚した身ですので、色々とさしさわることがありまして、お会いするのは言うまでもなく、手紙を書いて送ることも出来ませんでした。今はどこに住んでいるのですか、おかみさんもお元気ですか、子どもも産まれたのでしょうか。今も私は折につけて小川町の百貨店へ行くたびに、もとのお店がそっくりそのまま、同じたばこ屋の能登屋という店になっているので、いつ通っても覗いてみて、ああ高坂の録さんが子どものころ、学校の行き帰りに寄っては、巻き煙草のくずを貰って、大人びたふうにキセルで吸っていたけれど、今はどこで何をしているのだろう。気の優しい方だったから、こんなむずかしい世の中を、どうやって渡っているのだろうか。そんなことも気がかりだったので、実家に帰るたび、録さんのご様子を知っているかと聞いてはみるのですが、猿楽町を引っ越したのは今で五年の前で、まるっきりお便りを聞くことがなく、どんなに慕わしく思っていたことでしょう」
と人妻という自分の身分も忘れて熱心に話せば、男は恥ずかしさの冷汗を手ぬぐいで拭って、
「お恥ずかしい身に落ちまして、今は家というものもございません。寝どころは浅草町の村田という安宿で、そこの二階にごろごろしています。気が向いた時は、今夜のように遅くまで車を引くこともありますし、いやだと思えば朝から晩まで一日中ごろごろとして煙のように暮らしています。あなたは相変わらずの美しさですね。ご結婚なさったと聞いたときから、それでも一度はお会いすることができるか、一生のうちにまたお言葉を交わすことができるかと、夢のように願っておりました。今日までは生きていても用のない命、どうでもよい物として扱ってきましたが、命があったからこそお目にかかれた。ああよく私を高坂の録之助と覚えていて下さりました。ありがたい限りです」
と下を向くと、お関は涙を流して、
「つらい思いをしているのは、広い世間に自分だけだと思ってはいけません。それで、おかみさんは」
とお関が問えば、
「筋向こうの杉田屋の娘をご存じでしょう。色が白いとか姿がどうだとか言って、世間の人はやたらに褒めた女でございます。私がひどく放蕩をして家に帰らなくなったのを、嫁を貰うべき時に貰わなかったからだと、親類の中のわからずやが勘違いをして、あの娘ならばと母親が見定めて、是非もらえ、やれ貰えと無茶苦茶に薦めたてられました。もうどうにでもなれと思って、杉田屋の娘を貰ったのは、ちょうど貴女がご懐妊だと聞いた頃のことです。一年目には私のところにも子どもも生まれて、赤子のおもちゃなどが家の中に並ぶようになったのですが、それくらいのことで私の放蕩癖はおさまりません。周りの人は、顔の良い女房を持たせたら放蕩がやむか、子が生まれたら気が改まるかと思っていたのでしょうけれど、たとえこの上ない美女が私のために尽くしてくれようとも、決して放蕩はやめないと決めておいたものを、どうして乳くさい子どもの顔を見たくらいで、真面目になることができましょう。遊んで遊んで遊び抜いて、呑んで呑んで呑み尽くして、家も仕事もそっちのけにして、全くの無一文になったのは三年前です。お袋は田舎へ嫁に行った姉のところに引き取って貰っていて、女房は子どもと一緒に里へ帰したまま音信不通。女の子で跡取り息子にはなれないので、惜しいともなんとも思いませんでしたが、その子も昨年の暮れに、伝染病にかかって死んだと聞きました。女は早熟なものですので、死ぬ間際にはきっと父様とか何とか言ったのでございましょう。今年いれば五つになる娘でした。こんなつまらない身の上、お話しにもなりません」
男は淋しげな顔に笑みを浮かべて、
「貴嬢ということも知りませんでしたので、とんだわがままの失礼をしました。さ、乗って下さい、お供をします。さぞ不意で驚きなさったでしょう。車夫と行っても名ばかりで、何が楽しみにかじ棒をにぎって、何が望みに牛馬と同じような真似をするのか。金をもらえるのが嬉しいか、酒が呑めたら愉快なのか、考えれば何もかも全て嫌で、お客様を乗せようが、空車のときだろうが、嫌となると容赦なく嫌になります。あきれ果てるわがまま男で、我ながら愛想が尽きるではありませんか。さ、乗って下さい、お供をします」
とすすめられて、
「なにを、そういう気持ちを知らなかったので乗っていましたけれど、知ってからは乗れませぬ。それでもこんな淋しいところを一人で行くのは心細いので、せめて大通りへ出るまでは道連れになって下され。一緒に話ながら歩きましょう」
とお関は着物の前を少し持ち上げて歩きやすくする。あたりには塗り下駄の音が淋しく響いて聞こえる。
「昔の友達の中でも、この人は特に忘れられないゆかりのある人。小川町の高坂という小綺麗な煙草屋の一人息子で、今はこのように色も黒い男になっているけれど、落ちぶれていない頃は服も小粋でお世辞も上手。愛嬌もあるし、若いのにしっかりしていて、父親がいた時より却って店が賑やかだと評判されていた人の、驚くほどの変わりよう。ちょうど私が嫁入りしようとする頃に聞いたけれど、やけに遊んで底抜けの放蕩、高坂の息子はまるで人間が変わってしまったようだ、悪魔にでも取り憑かれたか、それとも悪霊の祟りか、よもやただ事ではないと。聞き及んではいたけれど、今宵見てみればいかにもみじめな身のありさまで、安宿泊まりをするようにまでなっているとは思いも寄らなかった。私はこの人に想われて、十二の年から十七まで毎日顔を合わせるたびに、ゆくゆくはあの店のあそこに座って、煙草屋で商いをするのだろうと思ってもいたけれど、思いがけず原田と縁があり、両親の薦めもあったので反対などできなかった。嫁に行くなら煙草屋の縁さんのところへと思っても、それはほんの子どもごころで、縁さんから口に出して言われたこともないし、こちらからはなおのこと。これはとりとめのない夢のような恋だから、思い切ってしまえ、思い切ってしまえ、諦めてしまおうと心を決めて、今の原田へ嫁ぐことになったけれど、嫁入り直前までも涙がこぼれて忘れられなかった人。私が恋したのと同じほどに、この人も私のことを恋してくれて、それが原因で身を滅ぼしたのかもしれないのに、私はこのような丸髷で悠々と世を送っているような姿、どのくらい憎らしく思われるだろう。決してそのような楽しい身ではないけれど」
とお関は振り返って録之助を見ると、何を思うのか呆然とした顔つきで、思いがけず出会ったお関を前にしても、あまり嬉しそうな様子も見えなかった。
大通りに出れば車もあった。お関は財布から紙幣をいくらか取り出して、高級紙につつしみ深く包み、
「録さん、これは本当に失礼ですが、鼻紙でもなんでも買って下され。久しぶりに会えて、話したいことがたくさんある気はしますが、口に出てこないのは察して下さい。では私はこれでお別れいたします。本当に身体を大事にしてお元気で、伯母さんも早く安心させてあげて下さい。陰ながら私も祈ります。どうぞ以前の録さんに戻って、立派にお店を開いているところを見せて下され。さようなら」
と挨拶すれば、録之助は紙づつみを受け取って、
「本来は遠慮するべきはずでしょうが、貴嬢の手から下さったものであれば、ありがたく頂戴して思い出にします。別れるのが名残惜しいと言っても、これも夢のうちならば仕方がないこと。さ、行って下さい。私も帰ります。これ以上夜が更けては路が暗くなってきますよ」
と言って空車を引いて後ろを向いた。録之助は東へ、お関は南へ、大通りの柳が月の陰になびいて、力なさげな塗り下駄の音が響く。村田の二階も原田の奥も、お互い悲しい世を生きて、とりとめのない考えに耽ることが多い。
終
樋口一葉『十三夜』の原文
『十三夜』の原文が気になる方は、
- 青空文庫
- Kindle
などから無料で読むことが出来ます。
ネット上で簡単に読むなら青空文庫が、電子書籍として縦書きで読むならKindleがおすすめです。
リンクを貼っておきますので参考にしてみて下さい。
・青空文庫
・Kindle
また、当サイトでは『十三夜』の作品解説や感想も書いています。よければそちらもご覧下さい。
-

-
『高瀬舟』200字のあらすじ&作者の伝えたいことをサッと解説!
続きを見る
現代語訳について
樋口一葉『十三夜』の現代語訳にあたっては、手元にあった集英社文庫版『十三夜』を参考に進めました。
したがって、カギ括弧の位置は集英社文庫版『十三夜』に拠るところが大きいです。
また、当サイトによる現代語訳は直訳ではなく意訳です。
大意は通ると思いますが、明らかな文法上の誤りなどを見つけられたらご一報下さい。ここに追記の上、修正いたします。
この記事で紹介した本