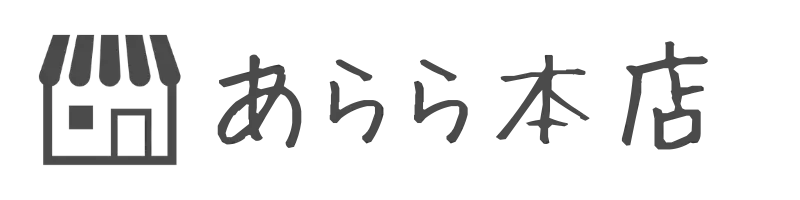『セロトニン』の感想
ミシェルウェルベックは、僕が一番好きな作家だ。
『セロトニン』は彼の8作目の小説。
「史上最高に暗い話」なんて囃されているけれど、そんなことはない。彼の作品はたいてい同じぐらい暗い。
ここではそんな『セロトニン』についての感想を書いた。
・ウエルベックと「セックス」
ウエルベックの作品の根底に、いつも流れているのは「セックス」だ。
主人公たちはたいていセックスが人生で最大の幸福だと考えている。
彼らは金持ちなのだけれど、残念なことに冴えない男たちばかり。
彼らは考える。現代の資本主義社会では金持ちになるだけでは幸福になれない、金持ちであり、かつ女にモテないと意味がないのだと。
一昔前なら、金があるだけで女には困らなかった(貴族社会なんかを思い出してみるといい)。でも現代は違う。異性と付き合うだけの魅力がなければ僕らに幸福は訪れないのだ。
つまり人間にとって、闘争領域は拡大している。彼の処女作のタイトル『闘争領域の拡大』は、端的にそれを表している。
さて、今回の『セロトニン』では、抗鬱剤によって性不能になった男が主人公だ。
つまりセックスができない。その時点で、この作品がどういう結末を迎えるのか、ウエルベックを読んできた読者なら容易に気が付いてしまうだろう。
ただ『セロトニン』の主人公は、これまでの作品の主人公とは違って、過去に「愛」と呼べるような関係を女性たちと結んだこともあった。幸福への扉は、そこまで開かれていたのだ。
だけど多くの人々と同じように、簡単な過ちを犯したり、または犯されたりして、全ての恋愛は終わっていった。それは冒頭ですぐに述べられる。
彼に残ったのはMacBookに収まる写真くらいで、彼の所有物自体も、その薄くスタイリッシュなノートパソコンと、メルセデスベンツ4WD G350TDしか無い。
唯一の希望であるセックスも抗鬱剤によって不可能。もっと言えば、彼は性欲すら感じられなくなっている。
ただし作中にはよく食事のシーンが描かれていて(ウエルベックの作品は食事のシーンが少なくないが、今作は特に多かったように思う)、それは性欲を無くした人間の、セックスの代わりとなる欲望を思わせた。
最後まで主人公の食欲が消えなかったことは、この物語の幸福な部分だと思う。
・主人公の職業と愛の消失
主人公は農業食糧省に勤めている。彼はフランスの農業事情に精通している人物として描かれているわけだ。
作中で注目されるのは、遺伝子組み換えのジャガイモ。
遺伝子組み換えをした作物を用いて収穫のペースを速めなければ、近年の世界的な人口増加に対して、食糧の供給量を間に合わせることができない。
一方、大学時代からの友人エムリックは、地球や動物たちに優しい昔ながらの畜産業を営んでいて、それがために厳しい生活を強いられている。非効率的な農業は金にならないのだ。
つまり、時代は遺伝子組み換えのジャガイモを求めていて、人間はその流れに抗うことができない。
この遺伝子組み換えのジャガイモは「愛の消失」の比喩として機能する。
ジャガイモ同士が自然に交配して、新しいジャガイモが芽を出す、というのが自然のあるべき姿だ。遺伝子組み換えは、その自然に科学を介入させる人工的な営為となる。
本来あるべき姿が、時代の流れによってなくなってしまう。人間同士の愛も同じ、というわけだ。
人間の愛を破壊するものとして描かれるのは、キャプトリクス。「胃腸の粘膜で形成されたセロトニンの細胞外への分泌を助長するというシステム」をもつ抗うつ剤だ。
作品では次のような言葉で表されている。
それは白く、楕円形で、指先で割ることのできる小粒の錠剤だ。
ミシェル・ウエルベック『セロトニン』
この人工物が人間にもたらすのは幸福なのか、それとも不幸なのか。その判断は我々読者に委ねられることになる。
・主人公と女たち
『セロトニン』では、主人公が人生の清算として、過去に関係のあった友人・恋人の元を訪れていく。
その人数が少ない、ということを主人公は度々主張するけれど、僕にはそうは思えなかった。
友人がひとり、恋人が数人。平均的な人数ではないだろうか。(それとも僕の交友関係が淋しいのか?)
物語の最初に登場する女性はユズという名前で、その名の通り日本人。物語の現在進行形で、主人公と関係を持っている。
ウエルベックがここまでしっかりと日本人を登場させたのは始めてのことで、日本人の読者にとっては嬉しいことだと思う。日本人という人種が世界にどう思われているかを知れるという点においても。
そうして次の女性、次の女性と訪れていくのだけど、ここは物語を守るためにも深く言及すべきではないと思う。
ひとつだけ言うとすれば、訪問先のそれぞれの描写ががたまらなく切なくて、まるでタルコフスキーの映画を観ているようだった。
・過去作『素粒子』との関連
今作も遺伝子組み換えの話、抗うつ剤がもたらす人体への作用などが、ミシェル・ウエルベックらしく語られた。
過去作の『素粒子』という小説でも、似たような構図で愛が語られる。(といってもこちらは神話の色彩が濃い。)
ウエルベックの理系的な部分、またエロティックな部分に惹かれた人は、ぜひ読んで欲しいと思う。間違いなく面白いから。
以上。
この記事で紹介した本