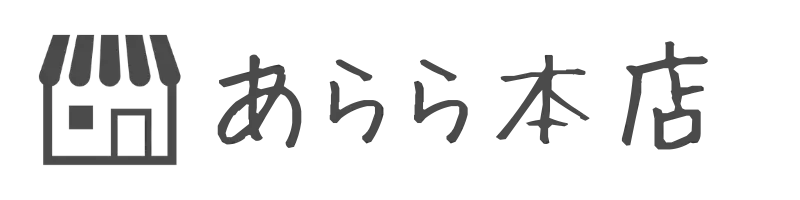『城の崎にて』とは?
『城の崎にて』は志賀直哉の短編小説で、1917年に発表されました。
三つの死を通して、生と死の非対立性を写実的な筆致で描いています。
ここでは、そんな『城の崎にて』のあらすじや、実際に起きた志賀直哉の電車事故との比較、作中で触れられる『范の犯罪』の解説までをまとめました。
『城の崎にて』のあらすじ
山手線の電車に蹴飛ばされて怪我をして、その養生にわたしは一人で城崎温泉へ出かけました。
脊椎カリエス(結核)になる可能性を考えましたが、3年間何もなければまず大丈夫とのことで、念のための養生です。
静かな秋を城崎で過ごすなかで、蜂の死、鼠の死、いもりの死を見ます。
それらは全て静かな死、あるいは偶然の死でした。
私は自分も電車に轢かれて死んでいたかもしれないことを思い、生と死はすぐ近くにあり、両極にあるものではないと考えます。
我慢できれば5週間ほどいても良いと思っていた城崎ですが、3週間で帰ることにします。
それから3年が経ちますが、脊椎カリエスになるだけは助かりました。
『城の崎にて』ー概要
| 物語の中心人物 | わたし |
| 物語の 仕掛け人 |
蜂、鼠、いもり |
| 主な舞台 | 城崎 |
| 時代背景 | 近代 |
| 作者 | 志賀直哉 |
『城の崎にて』ー解説(考察)
志賀直哉と電車事故|『城の崎にて』の発端
『城の崎にて』は、志賀直哉の身に起こった電車事故の経験が元に作られた作品です。
作中では簡潔に、次の一文で記されています。
山の手線の電車に蹴飛ばされて怪我をした、その後養生に、一人で但馬の城崎温泉へ出掛けた。
志賀直哉『城の崎にて』新潮社,1968,p28
軽い怪我かな?と思ってしまいますが、実際は重症で、二、三日は身体を動かせないほどでした。
大正2年(1913年)の8月15日の志賀直哉の日記に、事故当日の出来事が書かれています。
八月十五日 金
病院。かへつて「出来事」の了ひを書き直して出来上つてひるね、伊吾(注:里見弴)来る。起きてそれを讀む。将棋をする、晩、散歩に出る、芝浦の埋立地へ行く 水泳を見、素人相撲を見物して、帰り山の手線の電車に後ろから衝突され、頭をきり背を打った。伊吾が、どうかかうか東京病院へ連れていつてくれた。十時だった。
伊吾も一緒に泊つてくれたのださうだ。母とろく子が来たさうだ。『志賀直哉全集 第十巻「日記」』岩波書店,p694-695
ちなみに「出来事」というのは、志賀直哉がこの時に書いていた短編小説で、「子どもが電車に轢かれかけて助かった」という内容でした。
つまり、子どもが電車に轢かれかけて助かった話を書き終わった日に、彼自身は電車に轢かれてしまったわけです。
志賀直哉はこの時のことを、次のように述べています。
「出来事」これは自身で目撃した事実を殆どそのまま書いた。
(中略)
余談になるが、此小説を書き上げ、その晩里見弴と芝浦へ涼みに行き、素人相撲を見て帰途、鉄道線路の側を歩いてゐて、どうした事か私は省線電車に後からはね飛ばされ、甚い怪我をした。東京病院に暫く入院し、危い所を助かつた。電車で助かる事を書き上げた日に自分も電車で怪我をし、しかも幸に一生を得た。此偶然を面白く感じた。此怪我の後の気持を書いたのが「城の崎にて」である。『志賀直哉全集 第八巻「創作余談」』岩波書店,p5
この事故が起きてから3日後の8月17日には「もう気だけはハッキリして」いる様子が、日記からは分かります。
そうして事故から約2週間後の8月27日には退院が決まりました。
八月二十七日
雨が烈しく降った。それでも退院した。気分が悪かった。自家にかへつた時、少しも楽しくない気分がした。何故かわからぬ。
山内が来てくれた。
晩一緒に出て、虎の門まで歩いた。非常に疲労した。
戸外を歩く事、入院中は如何にも楽しさうに思えたが自身歩けると何んでもなかつた。『志賀直哉全集 第十巻「日記」』岩波書店,p699
志賀直哉が城崎温泉に行ったのは、この事故から約50日後である10月18日土曜日のことです。
帰ったのは11月7日の金曜日で、約3週間ほど滞在していました。
十月十八日 土
起きぬけに出発 七時半の汽車にのる、
沿道水害、城崎も水害かなりに烈しく町の中央を流れてゐる、川の橋大方流されてゐた。ゆとう屋といふ家を断はられて三木屋に行く、割りに気持よき所なり、湯の塩気強きは少し困る、然し、タムシにもいゝと効能書きにあつた。夜は按摩をとらせて早くねる、散々ウナサレタ。『志賀直哉全集 第十巻「日記」』岩波書店,p699
これらの日程をまとめると下記のようになります。
- 1913年8月15日:電車事故に遭う。当日入院。
- 1913年8月27日:退院。
- 1913年10月18日:城崎へ出発
- 1913年11月7日:城崎から尾道へ帰る
小説『城の崎にて』この期間のことを書いたものであり、構造的には、この時から3年後の「わたし」が回想するという形式です。
実際、この小説が発表されたのは1917年5月で、事故から丸3年が経過したタイミングになっています。
志賀直哉と『城の崎にて』の体験
作中の「わたし」に起こる出来事も、志賀直哉が実際に体験したことが盛り込まれています。
- フェータルな傷と脊椎カリエスへの心配
- 蜂、鼠、イモリの死
この2点です。
作中でも主要な部分ですが、彼の日記に同じことが書かれてあります。
フェータルな傷と脊椎カリエス
日記では、志賀直哉が友人に自分の怪我の状態を聞いています。
八月十九日 火
母、おせい叔母、山内、喜三郎等来てくれる、
自分は「此怪我はfatalな出来事なのではあるまいね」と訊いたさうだ。「そんな事はない」と聞いて、それから益々快活になつてゐたといふ事だ。『志賀直哉全集 第十巻「日記」』岩波書店,p696
fatalとは「致命的」の意味で、電車に轢かれた怪我が命に関わりはしないか、ということを聞いています。
具体的にここで言うフェータルな傷とは、脊椎カリエスになる可能性のある傷かどうか、という意味でしょう。
作中の「わたし」が心配している脊椎カリエスとは、傷口などから結核性の細菌が入り脊椎で化膿してしまう病気で、1913年の当時は難病でした。
「フェータルなものか、どうか?医者は何といっていた?」こう側にいた友に訊いた。「フェータルな傷じゃないそうだ」こう云われた。こう云われると自分は然し急に元気づいた。亢奮から自分は非常に快活になった。
志賀直哉『城の崎にて』新潮社,1968,p32
細菌は目に見えないので、医者が否定したとしても、もしかすると脊椎カリエスになるかもしれない。
脊椎カリエスになれば手足が動かなくなってしまう可能性があります。
『城の崎にて』の草稿である『いのち』には、より具体的に脊椎カリエスへの心配が書かれています。
若し内臓にそれが及ぼし得る危険を聞くとそれ以上に恐ろしい事が幾つかあつた。医者は診察の度に手足に触ってシビレるやうな気はしないかと訊ねた。これは後で聴いたが、若し自分のからだに結核菌があると、それが脊髄につく。すると脊ツイ、カリエースといふのになつて、手足が全く利かなつて了ふのださうだ。
『志賀直哉全集 第二巻「いのち」』岩波書店,p534
現代で言えば、ガンが同じ気持ちにさせるでしょう。
がん細胞のある箇所を手術で切除したが、もしかするとガン細胞はリンパ節を通って違う箇所へ転移しているかもしれない。
それは3年以内に再発するかどうかで見極めることができる、というものです。
その3年間は、嫌でも死を意識する期間でもあります。
『城の崎にて』は、そうした主人公の気持ちが背景になっているので、「生と死」という主題が作品の中心になっています。
蜂、鼠、いもりの死|「わたし」の禅的な死生観
作中では三つの死が描かれます。
- 蜂の死=死後
- 鼠の死=死の直前
- いもりの死=死の瞬間
この三つです。
まずは死後を描写した、「静かな感じ」の蜂の死です。
忙しそうに動き回る蜂たちの傍で仰向けになって裏返って死んでいる蜂の個体を見て、主人公はその死に「静かな感じ」を覚えます。
次はしの直前を描写した、「生へ執着する」鼠の死です。
子どもが「首の所に七寸ばかりの魚串が刺し貫して」ある鼠を川へ投げ入れ、それに向かって石を投げますが、それでも鼠は「何処かへ逃げ込む事が出来れば助かると思っているように」川を一生懸命泳ぎます。
最後は死の瞬間を描写した、「偶然の」いもりの死です。
「わたし」は驚かすつもりでいもりに向かって石を投げますが、いもりに偶然当たって死んでしまいます。
この三つの死も志賀直哉が実際に見たことで、「創作余談」や「日記」に書かれています。
十月三十日 木
蜂の死と鼠の竹クシをさゝれて川へなげ込まれた話を書きかけてやめた。
これは長編『志賀直哉全集 第十巻「日記」』岩波書店,p696
「城の崎にて」これも事実ありのままの小説である。鼠の死、蜂の死、ゐもりの死、皆その時数日間に実際目撃した事だつた。そしてそれらから受けた感じは素直に且つ正直に書けたつもりである。所謂心境小説といふものでも余裕から生れた心境でもなかつた。
『志賀直哉全集 第八巻「創作余談」』岩波書店,p11
これらの死は、主人公の感情を強く揺さぶるのでもなく、ドラマチックな影響を与えるのでもありません。
ただ淡々と死が書かれ、その死を恐れず「静かな気持ち」で、むしろ「死への親しみ」を感じている「わたし」が描かれる点に、『城の崎にて』の特徴があります。
あの鼠はどうしたろう。海へ流されて、今頃はその水ぶくれのした体を塵芥と一緒に海岸へでも打ちあげられている事だろう。そして死ななかった自分は今こうして歩いている。そう思った。自分はそれに対し、感謝しなければ済まぬような気もした。然し実際喜びの感じは湧き上がっては来なかった。生きている事と死んで了っている事と、それは両極ではなかった。それ程に差はないような気がした。
志賀直哉『城の崎にて』新潮社,1968,p36
生と死を対極的に見ているのではなく、禅的な方法で生と死を同じものとして捉えている死生観が見て取れます。
葉がヒラヒラしている意味とは?
終盤で、主人公が小川に沿って山を登っていくと、ヒラヒラとし葉が何かによって動いているのが見えます。
不思議な光景ですが、それに対する具体的な説明はなく、「原因は知れた」「何かでこういう場合を自分はもっと知っていたと思った」と主人公だけが納得している、非常に分かりにくい文章で終わっています。
この原因は、ヒラヒラとしている桑の葉の軸だけが弱っていたからです。
ほかの葉が揺れる風が吹くととその葉は揺れず、その葉が揺れる風が吹くとほかの葉は揺れない、というわけですね。
この「ヒラヒラとした葉」については、草稿の『いのち』に詳しい描写があります。
自分は不圖(注:ふと)前の大きい桑の木の枝で何かピラピラ、ピラピラ動いてゐるものを見た。其時風は吹いてゐなかつた。近よるとそれは一葉の桑の葉だつた。他の物には感じられない微かな風を其向きと、ジクの弱さ加減とで其葉だけ感じてゐたのだ。それは時計のセコンドのやうな細かさでいつまでも動いてゐた。而して他の物も感じるやうな風の吹く時には反つてそれは止まつた。これは書く程もない事だつたかも知れない。
『志賀直哉全集 第二巻「いのち」』岩波書店,p538
つまりは、同じ風が吹いても、対象によって力の受け方が違うことを言いたいわけです。
『城の崎にて』に当てはめれば、ある偶然の出来事があっても、結果的にいもりは死んで、わたしは助かった、ということですね。
それにしても言葉足らずすぎて、意味がつかみにくい文章です。
草稿の『いのち』を読むと、かなり削られて本稿になったことが分かりますが、この場面はいささか削りすぎた節があるでしょう。
ちなみにですが、事故の直前に書かれた『出来事』という短編も、ある出来事(子どもが電車に轢かれかける)に対して、車内にいた人々の多様な反応を描いた作品です。
『城の崎にて』を書いた頃の志賀直哉は、同じ出来事が人によって違う表れ方をする、ということを強く意識していたことが分かります。
『城の崎にて』ー感想
『范の犯罪』とは何か?
『城の崎にて』には、『范の犯罪』という小説に言及する場面があります。
これは志賀直哉の短編小説で、『城の崎にて』よりも3年ほど前(1913年10月1日)に発表されました。
大道芸人の男(范という中国人)が、演芸中に妻を殺してしまう(夫婦でナイフの芸をしていた)というもので、その殺人が事故なのか故意なのかについて、男と裁判官の問答が描かれる作品です。
男は、他人の子を身ごもっていた妻を「殺してやりたい」と常々思っていましたが、演芸中にその考えはありませんでした。
しかし常々思っていた事ならば、たとえ事故でもどうなの?という主題が追われます。
『城の崎にて』では、この小説を「范の犯罪」ではなく、「殺されたる范の妻」として書けばよかったと言っています。
それは范の気持を主にして書いたが、然し今は范の妻の気持を主にし、仕舞に殺されて墓の下にいる、その静かさを自分は書きたいと思った。
志賀直哉『城の崎にて』新潮社,1968,p30
これは、「電車に蹴飛ばされる」という生死を分けた出来事を経て、作者の心持ちが「動→静」、へと移行したことを表しています。
事実、『城の崎にて』には全体的に静かな印象を与える描写が多く、それが特徴となって本作を名作たらしめています。
この『范の犯罪』について書かれる部分は、少し過激な内容から、高校の教科書からは削除されているようです。
高校の授業で『城の崎にて』を読んだことがある人でも、「范の犯罪」については記憶にないかもしれません。
個人的な印象ですが、初期の志賀直哉は非常に素直な青年で、作品にもそれが表れているように思います。
『城の崎にて』が好きだった人は、『小僧の神様』や『和解』も気にいると思うので、読んでもらえると嬉しいです。
以上、『城の崎にて』のあらすじ&解説でした。