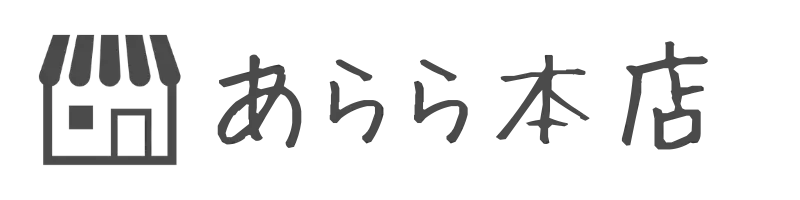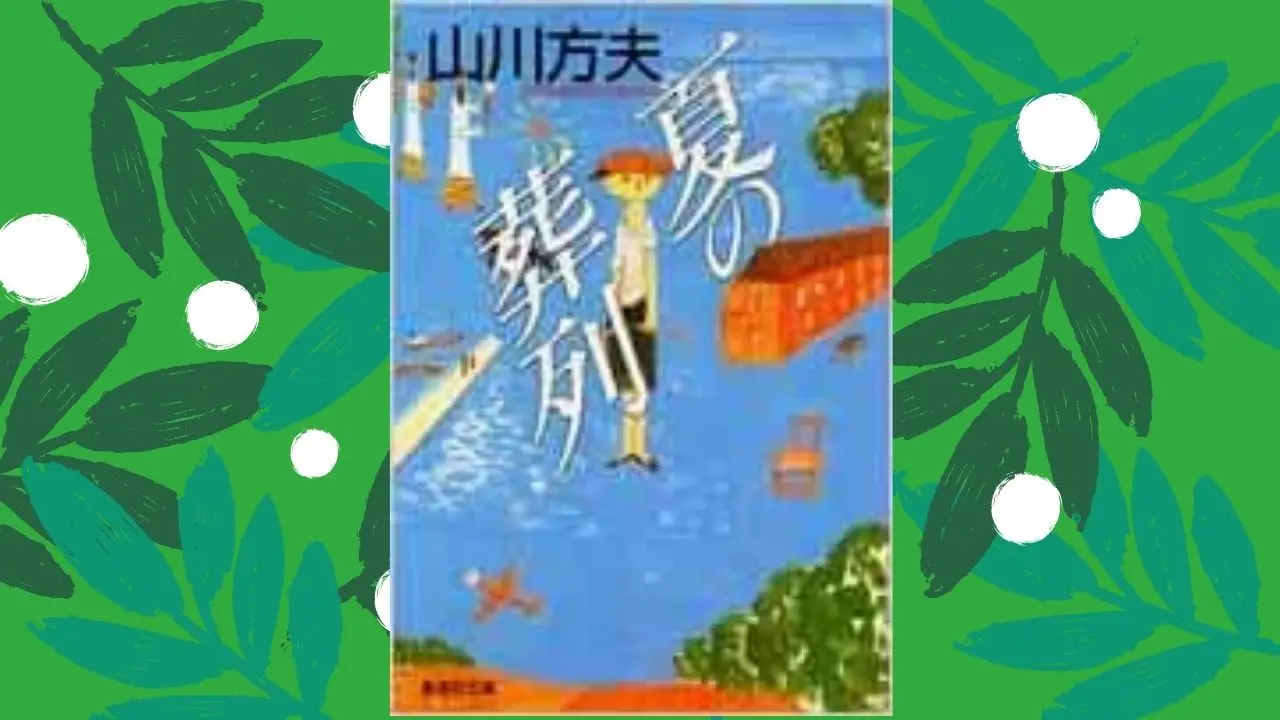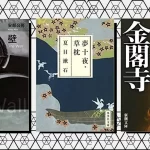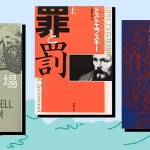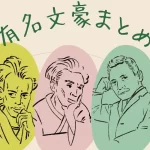『夏の葬列』とは?
『夏の葬列』は山川方夫の小説です。
戦争文学として有名で、教科書に載っていることもあります。
ここではそんんあ『夏の葬列』のあらすじ・感想・解説をまとめました。
『夏の葬列』のあらすじ
彼は海岸の小さな町の駅に降りて、久しぶりにこの地を訪れました。
なだらかな丘にさしかかったとき、ある一列の葬列が見え、思わず数十年前のことを思い出します。
戦時中、疎開児童としてこの地へやってきた彼は弱っちく、ヒロ子さんという2年上級の5年生に、いつも守ってもらっていました。
そんな彼女と、ジャガイモの葉が生い茂る青々とした畑を駆けていたとき、葬列を見つけた二人は駆け寄ろうとしました。
そのとき、上空に米軍の戦闘機が現れます。
ヒロ子さんは彼の元へやって来ますが、彼女が着ていたのは真っ白の服でした。
白い服は銃弾の絶好の標的になる。
怖くなった彼は、「向こうへ行け!」とヒロ子さんを突き飛ばします。
彼女は重傷を負い、白い服の下半身は真っ赤に染まっていました。
その翌日に戦争は終わり、彼はヒロ子さんがどうなったのか見届けないまま、東京に戻ったのです。
大人になった今この地に来て、あの日と同じ葬列が目の前を通ろうとしている。これは偶然なのだろうか?
彼は担がれている棺の写真をよく見ると、写っているのは老いたヒロ子さんでした。
良かった!俺はあのとき人を殺したわけではなかったのだ!
彼は上機嫌になり、近くにいた少年に、亡くなった人のことを色々と聞きます。
すると亡くなったのはヒロ子さんではなく、彼女の母親であることが分かります。
「あの小母さん、なにしろ戦争でね、一人きりの女の子がこの畑で機銃で撃たれて死んじゃってね、それからずっと気が違っちゃってたんだもんさ。」
ヒロ子さんの母親は、川に飛び込んで自殺したということでした。
彼はこの二つの死が、もはや自分の中で永遠に続くだろうということが分かり、もはや逃げ場所などないのだという意識が、彼の足どりをひどく確実なものにしました。
『夏の葬列』ー概要
| 物語の中心人物 | 彼 |
| 物語の 仕掛け人 |
ヒロ子さん |
| 主な舞台 | 東京近郊の海岸のある小さな町 |
| 時代背景 | 1945年8月14日→十数年後 |
| 作者 | 山川方夫 |
『夏の葬列』ー解説(考察)
物語の構成と「二つの死」
『夏の葬列』は、20代の男性が、ある海岸の小さな町に来て、過去を思い出す物語です。
という構成でストーリーが進みます。
主人公は、「あの日」の出来事(助けに来てくれたヒロ子さんを突き飛ばしたこと)を後悔しており、大人になってもずっと頭から離れていませんでした。
その答えを知りたいという思いもあったのでしょう。
彼は久しぶりに児童疎開先だった小さな町に訪れたのです。
明らかになる「二つの死」
彼が町のジャガイモ畑で見たのは、当時と同じ白い装束を着た葬列でした。
しかもその棺にある写真が、ヒロ子さんとそっくりなのです。
――おれは、人殺しではなかったのだ。
彼は、胸に湧きあがるものを、けんめいに冷静におさえつけながら思った。山川方夫『夏の葬列』
しかし、そう思ったのも束の間。それはヒロ子さんの母親の棺でした。
彼女は、娘のヒロ子さんが「あの日」の銃撃で死んでから気が違ってしまい、自殺したというのです。
ここで、主人公の彼は「二つの死」を同時に知らされることになります。
すなわち、
- 彼が突き飛ばしたヒロ子さんの死
- ヒロ子さんの死が原因で自殺した小母さんの死
の二つです。
彼がこの町に来るまでは、ヒロ子さんがあの後どうなったのかも知りませんでした。
しかしこの町で「あの日」と同じ葬列を見たことで、ヒロ子さんを自分が死なせてしまったことを知り、そのせいで小母さんも死なせてしまったことを知ったのです。
彼は、いまはその二つになった沈黙、二つの死が、もはや自分のなかで永遠につづくだろうこと、永遠につづくほかはないことがわかっていた。
山川方夫『夏の葬列』
過去と現在の「夏の葬列」をきっかけに、主人公は「二つの死」とともに生きることになるという構成が、『夏の葬列』の面白いポイントになっています。
作中の「白」が表すもの
『夏の葬列』では、色彩描写が効果的に使われています。
- まんじゅうの白
- ヒロ子さんの服の白
- 白い着物を着た葬列
- ジャガイモ畑の青々とした葉
などですね。
過去の回想に入った途端、物語の色彩がグッと豊かになります。
濃緑の葉を重ねた一面のひろい芋畑の向こうに、一列になった小さな人かげが動いていた。線路わきの道に立って、彼は、真っ白なワンピースを着た同じ疎開児童のヒロ子さんと、ならんでそれを見ていた。
山川方夫『夏の葬列』
また、回想が終わって現在に戻る場面も、色彩によって時間軸の変化を表現しています。
芋の葉を、白く裏返して風が渡って行く。葬列は彼の方に向かってきた。中央に、写真の置かれている粗末な柩がある。
山川方夫『夏の葬列』
白色は、日本文学的には「死」の描写として使われることが多い色です。
『夏の葬列』でも、死んだヒロ子さんの来ていた白いワンピースや、白い装束の葬列など、「死」と関連させた色彩描写になっています。
ジャガイモの花は何色か?
作中には書かれていませんが、ジャガイモの花も白色です。
舞台が主にジャガイモ畑で繰り広げられることから、このことは無縁ではないでしょう。
「あの日」は戦争終了の前日ということが書かれてあるので、8月14日ということが分かります。
彼は彼女のその後を聞かずにこの町を去った。あの翌日、戦争は終わったのだ。
山川方夫『夏の葬列』
じゃがいもの花は5月ごろから7月ごろに咲くため、作中の時期にはおそらく咲いていません。
しかし、芋畑は「濃緑の葉」や「真っ青な波を重ねた海」と表現されているので、青々と生い茂っていることは確かです。
そこにヒロ子さんの白いワンピースがあれば、その光景はまるでジャガイモの花を連想させます。
そしてじゃがいも畑が艦載機によって銃撃されると、葉が空に舞い上がります。
そのとき強烈な衝撃と轟音が地べたをたたきつけて、芋の葉が空に舞い上がった。あたりに砂埃のような幕が立って、彼は彼の手で仰向けに突き飛ばされたヒロ子さんが、まるでゴムマリのようにはずんで空中に浮くのを見た。
山川方夫『夏の葬列』
芋の葉の裏は白いので、舞い上がったじゃがいもの葉は、白くちかちかと見えるでしょう。
その様子はヒロ子さんだけでなく、ほかの多くの犠牲者たちが戦争で散っていったことを表現しているようにも思えます。
芋畑でじゃがいもの花のような白いワンピースを着たヒロ子さんが銃撃されることで、ほかのじゃがいもの花を連想させ、いくつもの命が絶たれたことを描いているのではないでしょうか。
「彼の足どりをひどく確実なもの」にしたのはなぜか?
『夏の葬列』は次の一文で終わります。
もはや逃げ場所はないのだという意識が、彼の足どりをひどく確実なものにしていた。
山川方夫『夏の葬列』
ということなら分かりやすいですが、主人公はむしろ足どりが確実になっています。
これは先にも説明した、
という問いから解放され、罪とともに生きていく決心をしたからだと考えられます。
「あの日」のトラウマ
主人公の彼は、「あの日(ヒロ子さんを突き飛ばしたこと)」をトラウマとして抱えていました。
トラウマから逃れようとして、何度も最良のパターンを考えたことでしょう。
彼の理想は、
- ヒロ子さんは銃で撃たれたけど、無事に生きている
ということ。
そう考えた彼は、彼女は生きているという理想を「逃げ場所」として、トラウマから逃れていました。
そのことは、ヒロ子さんが死んでいなかったと勘違いしたときの有頂天ぶりからも取れるでしょう。
――おれは、人殺しではなかったのだ。
彼は、胸に湧きあがるものを、けんめいに冷静におさえつけながら思った。たとえなんで死んだにせよ、とにかくこの十数年間を生きつづけたのなら、もはや彼女の死はおれの責任とはいえない。すくなくとも、おれに直接の責任がないのはたしかなのだ。山川方夫『夏の葬列』
彼が思い描いていた理想が叶い、人の死という場には似つかわしくない喜びが、ここでは表現されています。
しかし、次の場面で彼は現実を知ります。
ヒロ子さんを殺したのはやはり自分で、さらには彼女の母親の死にも責任があったのです。
事実を知った彼は、
という逃げ場所がなくなり、その罪をしっかりと背負って生きていく決意をします。
そのために、彼の足どりは「ひどく確実なもの」となったと考えられます。
こうしたことから『夏の葬列』は、過去のトラウマと向き合い、受け入れ、共に生きてゆく決心をした男の物語とも読むことができるでしょう。
『夏の葬列』ー感想
責任の所在
『夏の葬列』では、「責任」という言葉が多く使われています。
もはや彼女の死はおれの責任とはいえない。すくなくとも、おれに直接の責任がないのはたしかなのだ。
山川方夫『夏の葬列』
責任といえば、元を辿れば戦争を開始した「日本国」に責任があるはずです。
たとえば、葬列がくれるという「まんじゅう」を欲しがったのは主人公です。
- まんじゅうをもらうため、芋畑に入っていく
- 畑を走っていたら艦載機が来る
- 主人公に突き飛ばされたヒロ子さんが撃たれて死ぬ
この因果関係は大事で、二人がただ歩いていたところを艦載機が襲ったのであれば、別のテーマ色が強くなってしまいます(戦争の残酷さや理不尽さなど)。
さらに、主人公は弱っちく、2学年上のヒロ子さんにいつも守ってもらっていました。
彼が強い男の子だったのであれば、ヒロ子さんは主人公を気にすることなく逃げていたかもしれません。
つまり、ヒロ子さんの死は、以下3つの主人公の行動によって確定されていくのです。
- 主人公が弱っちかったから
- 主人公がまんじゅうを欲しがったから
- 主人公が彼女を突き飛ばしたから
このように、主人公を責められるポイントが、少なくとも3つほど小説内で提示されています。
根本的には国の責任ですが、戦争という特殊な状況下でも、「個々人の責任」にこだわる作者の姿勢がみられるように感じます。
自分ならヒロ子さんを突き飛ばしていたか?
その状況にならないと分かりませんが、僕が主人公と同じ立場なら、彼女を突き飛ばしてしまう可能性は十分にあります。
- 白いワンピースは銃撃の標的になる
- ヒロ子さんは白いワンピースを着ている
- ヒロ子さんが僕の元へ来る
- 僕も一緒に標的になってしまう
シンプルすぎる論理で、ヒロ子さんと一緒にいれば、命の危険度が増すことは明白です。
死ぬか生きるか。
死の恐怖が迫る極限状態では、ほとんどの人が生きる方を選ぶのではないでしょうか。
もちろん、相手が心から愛している人だったら話は別です。
しかし、相手は疎開先で知り合った2学年上の女の子。
淡い恋心はあったかもしれませんが、小学三年生の彼に、命を投げ打つまでの覚悟はないでしょう。
個人的には、仕方のない行為だと思います。
以上、『夏の葬列』のあらすじ・解説・感想でした。