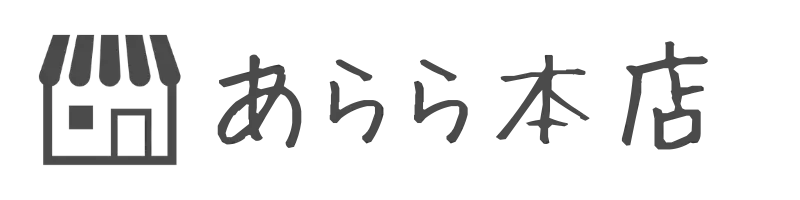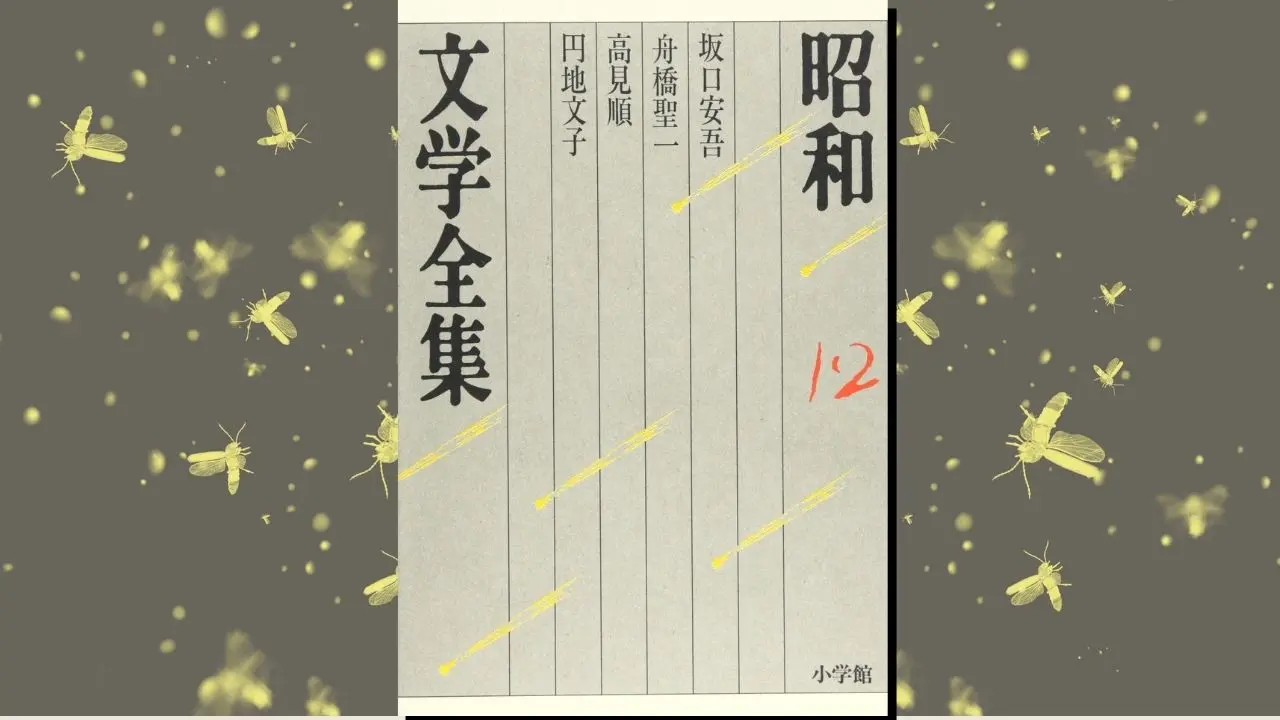『故旧忘れ得べき』とは?
『故旧忘れ得べき』は、高見順の芥川賞候補作で、転向文学の代表的な作品として知られています。
左翼活動に傾倒した学生時代と現在の生活の比較を通して、主人公とその友人達の自我の乖離が描かれる物語です。
ここではそんな『故旧忘れ得べき』のあらすじ・解説・感想をまとめています。
『故旧忘れ得べき』のあらすじ
主人公の小関は、母と妻と三人で貧しい暮らしをしている。
もとは高等学校を出たエリートだったが、左翼活動の波に呑まれて良い職に就けず、コネで入った雑誌社で安月給をもらっているのだ。
頭に禿が出来て、知り合いの医者である旧友の橘に診てもらおうと病院に行ったとき、偶然に同窓の篠原辰也に出会う。
篠原は神戸の金持ちの息子で良い身なりをしているので、小関は自分の薄給を情けなく思う。
しかし、小関は篠原との出会いから旧友達との交友が再び活発になってゆく。
保険外交員の松下長造、新聞記者の友成達雄や、彼らに関係する女性達。
そして終盤には転向した沢村稔という友人の自殺が描かれる。
旧友たちは彼の追憶会を行い、「故旧忘れ得べき(蛍の光)」を唄って物語は幕を閉じる。
・『故旧忘れ得べき』の概要
| 主人公 | 小関健児 |
| 物語の 仕掛け人 |
篠原辰也 |
| 主な舞台 | 東京 |
| 時代背景 | 昭和初期 |
| 作者 | 高見順 |
-解説(考察)-
・『故旧忘れ得べき』のテーマ ~乖離した自我~
『故旧忘れ得べき』の物語のテーマは、
- 乖離した自我
です。広く知られているように、この物語はマルキシズムから転向した人々が描かれています。
マルキシズムとは?
マルキシズムとは、ロシア革命家のマルクスやレーニンなどが発展させた共産主義的な思想です。
資本家が労働者から搾取する経済システムを廃止し、共同で平等に運営する社会システムを唱えました。
日本でも大正~昭和初期にかけてマルキシズムが流行しましたが、日本帝国政府側の弾圧によって勢力は弱まります。
そうした弾圧で、共産・社会主義的な思想を捨てさせられたことを「転向」と言います。
高見順・中野重治などは転向をテーマにした作品を残しており、『故旧忘れ得べき』もその代表作です。
思想を強制的に捨てさせられるというのは、これまで生きてきて培ってきたアイデンティティを矯正されることと同じです。
主人公の小関や篠原は、マルキシズムに傾倒していた学生時代と、大人になり普通に働いている現在との乖離を感じながら生きています。
ほかの登場人物たちも、学生時代の自分と大人になった自分のかけ離れた姿に戸惑いを隠せません。
たとえば、柔道部で豪放だった松下長造は今では保険の外交員に。また当時は天才的な才覚を見せた友成達雄も、今では凡庸な新聞記者として描写されています。
このように、『故旧忘れ得べき』は学生時代とは違う、もっと言えば思想を持っていたときとは違う、彼らの乖離した自我がテーマになっている作品です。
ほかにも、転向に伴う主人公の心情を描いた村山知義の『白夜』。転向後にどう生きるかを描いた中野重治の『村の家』、島木健作の『再建』などは、「マルキシズムと転向」というテーマを掘り下げている作品です。
『故旧忘れ得べき』の「転向」というテーマが共通しているので、深く知りたい方はそれらもまとめて読むと理解しやすいと思います。
・『故旧忘れ得べき』のタイトル
この作品を面白くしているのが、『故旧忘れ得べき』という題名に関連する音楽です。
ある曲のタイトルである「Auld Lang Syne」の意訳が「故旧忘れ得べき」であり、日本では「蛍の光」という楽曲名で知られています。
閉店の音楽などで身近な「蛍の光」ですが、原曲はスコットランドの民謡で、実は世界中で親しまれている唱歌です。
ラストでは故人を偲んで男達が「蛍の光」をしめやかに合唱するのですが、メロディを知っているだけに切ない場面になっています。
冒頭でも以下の歌詞が引用されており、物語の中心になっていることが分かります。
Should auld acquaintance be forgot,
And never brought to min,?
Should auld acquaintance be forgot,
And auld lang syne?Robert Burns
高見順『昭和文学全集12』小学館,p531
旧い友達を忘れてしまってもいいのだろうか。
あの頃の日々は忘れ去られるものなのだろうか。
登場人物たちはこの「蛍の光」を大声で歌うのではなく、「胸の中のモダモダを吐き出すような侘しい」気持ちで歌います。
つまり、歌詞の内容に身を任せて感傷的になっているわけではなく、やりきれない侘しさとやるせなさで歌うのです。
こうした音楽の効果を用いて雰囲気を作りあげることで、作品に独特な哀愁が漂っていることが『故旧忘れ得べき』の特徴にもなっています。
-感想-
・顔を出す作者
『故旧忘れ得べき』では、物語の途中で度々「作者」が顔を出します。
読者よ!とこちらに向かって呼びかけたり、描写の至らなさを許して欲しいとお願いしたりしてくるのです。
こうした手法は饒舌体と呼ばれて高見順の特徴でもありますが、この作品ではそれがとくに顕著でした。
個人的な感想で正直に言うと、最初は少し顔を出しすぎるなあと思う気もします。
ですが、途中からはむしろ作者と一緒に読んでいる感じがしてきて、物語の端に常に作者の姿が見えるようになり、慣れてくるとあまり気にならなくなりました(太宰の作品でも作者がたまに顔を出してきますが、あれとは少し違った感じでもっとぐいぐい来ます)。
こうした「作者」の独特な介入も、『故旧忘れ得べき』の特徴だと思います。
解説では「転向文学」としてこの作品を読み解く形でしたが、もちろん「転向」を気にせず物語を楽しむことも出来る作品です。
実際、僕はこの小説や『村の家』などが転向文学だということを読んだ後で知りました。
それでも面白かった記憶があるので、まだ読んだことのない人はぜひ読んでみて下さい。
以上、『故旧忘れ得べき』のあらすじと考察と感想でした。
この記事で紹介した本