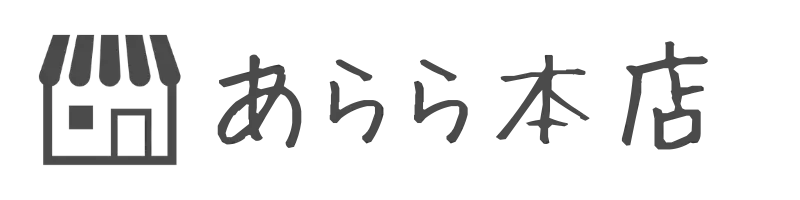『マダム・エドワルダ』とは?
『マダム・エドワルダ』という作品は、ジョルジュ・バタイユの代表作とされながらも、非常に読解しにくいことでも有名です。
マダム・エドワルダに出会った一夜を軸に、エロス(性)とタナトス(死)が混じり合った主人公の精神世界が描かれていきます。
ここではそんな『マダム・エドワルダ』のあらすじ・解説・感想をまとめました。
『マダム・エドワルダ』のあらすじ
主人公の男が、パリの夜を歩いている。
彼はなんともやるせない気持ちでいて、それから逃れるためには、裸にならなければならなかった。
彼は裸になり、夜の冷気を感じながら、果てのない自由に浸っていた。
物音がしたので彼はズボンをはき、娼婦のいる「鏡楼」に向かった。
そこで「私は神よ」という娼婦のマダム・エドワルダを見つけた。マダム・エドワルダは主人公の好みだった。
夢の時間が過ぎると、彼女は「出かけましょう」と言った。
マダム・エドワルダは、裸体に白いボレロと靴下を付けて、黒い外套をまとった。
主人公は裸では出られないので、服装を整えた。
外に出ると、マダム・エドワルダは一目散に駆けだした。
主人公が彼女を追うと、マダム・エドワルダはサン=ドニ門の下にいた。
そこで主人公は、マダム・エドワルダが神であることを理解した。彼女はもぬけのからだったのだ。
サン=ドニ門の下まで来ると、彼女はまた行方をくらました。と思ったら、近くのカフェ辺りにいた。
マダム・エドワルダは、主人公から一度離れ、すぐまた戻ってきて、主人公を殴りつけてこう言った、「お前なんかくそくらえ」。
そして彼女は地面に倒れ、苦悶でみみずのように痙攣した。
主人公は彼女を眺めながら、彼女の苦悩や自分の苦悩について、深く思考を巡らせた。
マダム・エドワルダが落ち着くと、主人公は彼女を抱きかかえ、彼女が一人で歩けるようになると、タクシーに乗った。
タクシーが動き出してしばらくすると、マダム・エドワルダは服を脱ぎ始めた。
目的の場所に着くと、マダム・エドワルダは運転手の前へ歩いていき、「私としましょ」と言った。
主人公のいる後部座席に、マダム・エドワルダと運転手が乗り込んできて、二人は快楽をむさぼった。
主人公はその様子を無気力に眺め、ときおり彼女の顔が見えやすいように電気を点けたり、のけぞる彼女の頸筋を支えたりした。
ことが終わると、タクシーの底には運転手が転がっていて、マダム・エドワルダもぐったりとしていた。
主人公は彼女の汗を拭い、車内の電気を消した。そして眠気が三人を襲った。
主人公がまず、不快な眠りから眼を覚ました。そして後には、待ち遠しい死への期待だけ。
・『マダム・エドワルダ』の概要
| 主人公 | 私 |
| 物語の 仕掛け人 |
マダム・エドワルダ |
| 主な舞台 | パリ |
| 時代背景 | 20世紀 |
| 作者 | ジョルジュ・バタイユ |
-解説(考察)-
・『マダム・エドワルダ』の分かりにくさ
『マダム・エドワルダ』は理解しにくい物語ですが、構造そのものは明瞭で、簡単に三つの場面から成り立っています。
- 主人公が娼館に行く場面
- サンドニ門の下でマダム・エドワルダを見つける場面
- タクシーの運転手とマダム・エドワルダが情事に及ぶ場面
このように、物語の構成は比較的分かりやすいです。
ですが、登場人物の行動の動機を語り手がきちんと説明していないため、場面どうしの関係が掴みにくくなっています。
たとえば、以下のようなところが、読者を迷わせる原因でしょう。
- マダム・エドワルダの変貌ぶり
- 主人公の複雑な内面
- マダム・エドワルダがタクシー運転手を選んだ理由
これらがきちんと説明されていないので、『マダム・エドワルダ』は分かりにくい物語になっています。
物語の分かりにくさが語り手によるものだとすれば、この「分かりにくさ」は意図的なものだといえるでしょう。
実際語り手は、「俺を分かってくれる人だけが理解してくれれば良い」というようなことを言っていて、読者を遠ざけようとする姿勢が見られます。
ほかにも様々に読者を寄せ付けまいとする表現は多く見られ、『マダム・エドワルダ』自体が読者を拒んでくるテキストになっています。
このように、『マダム・エドワルダ』はそもそも分かりにくい作品です。
逆説的ですが、そんな「分かりにくさ」を楽しむことが、本書の味わい方でもあります。
とはいえ、分かりにくいだけが本書の魅力ではありません。
ここでは、
- マダム・エドワルダの変貌ぶり
- 主人公の複雑な内面
- マダム・エドワルダがタクシー運転手を選んだ理由
など、先に挙げたような分かりにくいポイントを、個人的な視点から解説していきます。
・マダム・エドワルダの変貌
物語の序盤、マダム・エドワルダはただの娼婦として登場します。
主人公が娼館「鏡楼(レ・グラス)」で彼女を見つけ、大衆の面前でいかがわしい行為をして、その後ベッドにはいります。
きわどい描写ではあるものの、「私は神よ」という彼女の宣言を除けば、特に変わったことはありません。
ことが終わり、二人が娼館から町へ出かけるときから、物語は不可解な様相を帯びていきます。
マダム・エドワルダは外へ出ると、いきなり走り出すのです。
それから、サン=ドニ門の下に来ると、主人公に殴りかかったり罵ったり、苦悶のため地面にのたうち回ったりします。
こうしたマダム・エドワルダの豹変ぶり、また不可解な言動が、物語を分かりにくくしている原因の一つでしょう。
彼女が豹変した理由は、
- 服を着たから
- 外に出たから
の二つ、あるいは両方が考えられます。
まず、物語の初めには、彼女は裸で現れて「私は神よ」と言います。
しかし、服を着て外へ出ると、とたんに彼女は狂い始めるのです。
「服を着る・外へ出る」というきっかけが、彼女を狂わせていることが分かります。
そして物語の最後、タクシーの中でもう一度服を脱いで裸になった彼女は、登場時と同じように平静さを取り戻しています。
タクシーという閉鎖空間と、「裸」であるという状態が、彼女を落ち着かせているのでしょう。
こうしてみると、マダム・エドワルダは服を着ているか着ていないかで、精神的な安定が左右される人物として描かれていることが分かります。
物語の最初と最後のような「裸」の状態であれば、彼女の精神は安定し、物語の途中のような「着衣」の状態であれば、彼女の精神は不安定になるのです。
こうしたことから、マダム・エドワルダの変貌を通して、「裸=善いこと」であるという物語の設定が浮かび上がってくることが分かるでしょう。
さらにいえば、マダム・エドワルダは「神」だとされているので、彼女の「裸」は聖なるものとしても描かれています。
このように、ここではマダム・エドワルダと「裸」の関係を見てきました。
次は主人公に視点を移し、ラストシーンでなぜ彼が「死」を期待するのか、その点を見ていきます。
・主人公はなぜ「死」を期待するのか
主人公は物語の初めに、「夜のように裸になりたかった」ので、夜の街中で服を脱いで裸になります。
『マダム・エドワルダ』では「裸」が善いもの、聖なるものとして描かれていることは、先にも述べた通りです。
つまり、物語の冒頭では、主人公も聖なる時間を体験していることが分かります。
しかし、そんな主人公は「物音に不安をおぼえ」たので、ズボンを履きなおしてしまいます。
これは、主人公の聖的な体験が、他者によって妨げられていることを表します。
さらに物語を進めて、「鏡楼」での場面を見てみましょう。
主人公は、鏡張りの部屋でマダム・エドワルダと身体を重ねます。
彼はここで肉の快感に酔いしれているはずですが、鏡張りの部屋であるために、どうしても自分たちの交接を客観的に見てしまう瞬間があったはずです。
つまり、ここでも自分という他者(理性)が、主人公の「裸」を邪魔していることが考えられます。
それから、「鏡楼」でことが終わったあとの、マダム・エドワルダのセリフに続きます。
「早く、坊や」陽気に答える。「あんたは裸で出られないわ!」
ジョルジュ・バタイユ『マダム・エドワルダ』角川書店
普通ならマダム・エドワルダも裸では出られないので、このセリフは主人公が「裸」になれないことを表す象徴的な表現です。
実際の服装も、マダム・エドワルダは裸体の上から簡単な衣類に外套を重ねただけですが、主人公はきちんと身支度をして、夜の街に出て行きます。
この対照的な場面をきっかけとして、次第に主人公はマダム・エドワルダに突き放されていきます。
不意に狂ったように、駆けだした。突然はたと立ち止まると、外套の裾をひるがえし、腰をひねって、裸の尻を突き出した。それからこちらへ引っ返してきたかと思うと、おれに向かって襲いかかってきた。
ジョルジュ・バタイユ『マダム・エドワルダ』角川書店
ここは、マダム・エドワルダの不可解な行動が特徴的な場面です。
個人的には、彼女の誘いに乗らなかった主人公に対して、マダム・エドワルダが怒ったかたちだと思います。
「裸」になれない主人公が、彼女の誘いに乗らないのは当然でしょう。
この場面で主人公の「裸」は完全に閉ざされ、エロティシズムは失われていることが読み取れます。
そのため、物語の終盤でマダム・エドワルダはタクシーの運転手を求めますが、主人公はその横で、ただ二人を「無気力に」眺めているだけなのです。
そうして、物語はラストのセリフへと繋がります。
おれが最初に、不快な気分で眼をさました・・・あとには皮肉な、待ち遠しい死への期待・・・
ジョルジュ・バタイユ『マダム・エドワルダ』角川文庫
主人公は他者の眼のせいで、「裸」になることが出来ませんでした。
ただし、「裸」になれるもう一つの、そして唯一の方法があります。それは主人公の「死」です。
他人の視線によって自己を脱することができないのであれば、他人の視線が届かない死の世界に行くことで、「裸」になれる可能性があります。
このようにみてみると、エロティシズムによって「裸」になれなかった主人公は、死をもって「裸」になることを待ち望んだのだと考えられるのです。
・マダム・エドワルダとディオニュソス
ここでも見てきたように、性(エロティシズム)と死(タナトス)はジョルジュ・バタイユ作品を貫く主題です。
『マダム・エドワルダ』においては、娼館である「鏡楼」が性を、サン=ドニ門が死を象徴する場所として描かれています。
サン=ドニ門は、フランスのパリ郊外にある門で、サン=ドニ大聖堂に繋がることからその名が付けられました。
サン=ドニ大聖堂は、歴代フランス君主の埋葬地となっているので、そこに繋がるサン=ドニ門は、死を象徴すると考えられるのです。
ちなみにサン=ドニは「聖ドニ」という意味の言葉で、3世紀にいた殉教者ドニを指します。
ドニはパリのディオニュシウスと呼ばれ、異教の地で布教をしていたところ、剣で首を切られて殉教しました。
彼は首を斬り落とされた後、自分の首を拾い上げ、説教をしながら数キロメートルを歩いたと伝えられています。
そうして本当に死んだところに小さな礼拝堂がつくられ、そこがのちにサンドニ大聖堂になったそうです。。
聖ドニの呼び名である「デュオニシウス」は、ニーチェが「ディオニュソス的」と表したことでも有名で、その意味は「激情的」や「熱狂的」となります。
これは、マダム・エドワルダの卑猥な熱狂や激情の描写にも当てはまるところがあるでしょう。
つまり、サン=ドニ門は死の象徴であるだけでなく、マダム・エドワルダをディオニュソスと重ね合わせる仕掛けとしても機能しているのです。
こうした連想がはたらけば、マダム・エドワルダが感情的になったり暴れ出したりする描写も「狂っている」のではなく「激情的」だと捉えることが出来るので、物語をより捉えやすくなるかもしれません。
感想
・孤独で敗北者の主人公
『マダム・エドワルダ』を読んだとき、意味の分からないことは多かったのですが、ただ一つはっきりと感じていたことがあります。
それは、この主人公に漂う敗北感です。
彼はほとんどを苦悩のうちに生き、束の間の快楽にさえも没入できず、最後にはマダム・エドワルダをタクシーの運転手に取られてしまいます。
世の中も、人間との関係も、たったひとつの希望も、全て奪われてしまったような諦念が、主人公からはにじみ出ています。
また、フランス文学らしい乾いた感じもあって、サルトルやカミュをはじめとして、現代フランス作家ミシェル・ウエルベックなどにも繋がる源流を垣間見たような気もしました。
『マダム・エドワルダ』は難解な小説として有名ですが、難解であるからこそ、自分なりに読んでみてよい作品だと思います。
様々な解釈に耐えうる小説であり、そうした意味で、本作は紛れもなく名作だといえるでしょう。
物語を楽しみたいなら、バタイユの『眼球譚』もおすすめです。
以上、『マダム・エドワルダ』のあらすじと考察と感想でした。
この記事で紹介した本