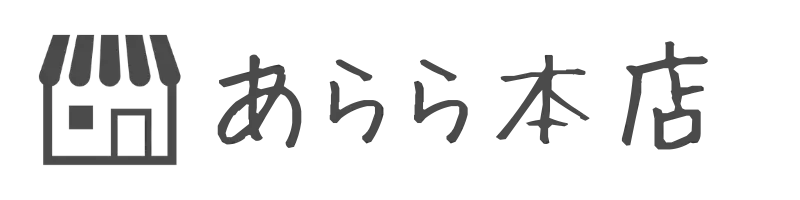『忘れえぬ人々』とは?
『忘れえぬ人々』は、無名の文筆家である主人公の大津が、旅で出会った忘れられない人々を描いていく物語です。
国木田独歩の初期代表作でもある本作は、「自然と人間生活」という彼の特徴的なテーマが強く出ている一篇にもなっています。
ここではそんな『忘れえぬ人々』のあらすじ・解説・感想をまとめました。
『忘れえぬ人々』のあらすじ
多摩川の溝口あたりの亀屋という旅人宿に、大津弁二郎という一人の若者が入っていった。
宿屋の主人は急に入ってきた男を不審そうに見たが、はなから興味はない様子で、少し話すと大津を七番の部屋へやった。
大津は無名の文筆家だったので、隣部屋にいた無名の画家である秋山松之助と打ち解け、一晩で友になった。
二人は文学論、美術論、宗教論まで勝手に話し、果ては昨今の作家や画家を手酷く批評するに至り、夜が更けるのにも気づかないほどだった。
大方悪口も言い尽くしたあと、話は大津の持っていた原稿に移った。
それは「忘れえぬ人々」と題された小説であり、大津はこの内容を秋山に分かりやすく話し始める。
「忘れえぬ人々とは、忘れてはならない人のことではない。
僕が旅先で出会った、どうしても忘れられない人々のことだ。
たとえば、船の上から見た島の浜辺で、何かを拾っていた人。
橋の上で俗謡を唄いながら、こちらも見ずに通っていった若者。
せわしそうな人々の中で、ひとり哀切な琵琶の音を鳴らしている琵琶僧。
このような人々が、すなわち僕の忘れえぬ人々である。
僕は生の孤独を感じて人懐かしくなると、決まってこの人々を思い出す。
そして、僕と彼らの間に何の違いがあるのかという思いが起こり、思わず涙が頬を伝う。
その時は実に、我もなければ他もない。僕はこのときほど心の平穏を感じることはないのだ。
僕はどうにかして、この題目で僕の思う存分に書いて見たいと思っている。」
それから二年が経った。
大津は東北の一地方に住み、かつて宿屋で出会った秋山との交際は全く途絶えた。
ある雨の降る晩、大津は独り瞑想にふけっていた。
机の上には秋山に見せたのと同じ「忘れえぬ人々」の原稿が置いてあって、その最後に書き加えてあったのは『亀屋の主人』であった。
『秋山』ではなかった。
・『忘れえぬ人々』の概要
| 主人公 | 大津弁二郎 |
| 物語の 仕掛け人 |
秋山松之助・亀屋の主人 |
| 主な舞台 | 多摩川溝口 |
| 時代背景 | 明治時代 |
| 作者 | 国木田独歩 |
-解説(考察)-
・「忘れえぬ人々」とは誰か
まず、「忘れえぬ人々」については、作中で次のように定義されています。
恩愛の契りもなければ義理もない、ほんの赤の他人であって、本来をいうと忘れてしまったところで人情をも義理をも欠かないで、しかもついに忘れてしまうことのできない人
国木田独歩『忘れえぬ人々』
つまり、自分とはほとんど人生上の接点を持たないけれど、どうしも忘れることのできない人々ということです。
『忘れえぬ人々』では、このような「忘れえぬ人々」が4人語られます。
すなわち、
- 瀬戸内通いの船の中から見た、さびしい島かげで小さな磯を漁っていた人
- 阿蘇山麓の村で、空車を押しながら馬子唄を歌って通り過ぎていった二十四、五の若者
- 四国の三津ヶ浜で、悲しげな琵琶の音を鳴らす四十歳半ばの琵琶僧
- 多摩川溝口で宿屋をしている、きわめて無愛嬌な六十歳ほどの主人
の4人です。
大津は、この他にも色々の「忘れえぬ人々」がいると言いますが、簡単に触れられるだけで、具体的に話されることはありません。
もうよそう、あまりふけるから。まだいくらもある。北海道歌志内の鉱夫、大連湾頭の青年漁夫、番匠川の瘤ある舟子など僕が一々この原稿にあるだけを詳しく話すなら夜が明けてしまうよ。
国木田独歩『忘れえぬ人々』
こうした人々が、本作で語られる「忘れえぬ人々」です。
・なぜ忘れられないのか
主人公の大津は、なぜ彼らのことを忘れられないのでしょうか。
それは、大津が生の孤立を感じて、堪たえ難いほどの哀情を催すようなときは、決まってこの「忘れえぬ人々」を思い出すからです。
ちなみにこの「忘れえぬ人々」は、人それ自身だけでなく、その人がいた景色も必ず一緒に思い出されています。
彼らを思い出した後、大津は次のようなことを感じます。
われと他と何の相違があるか、みなこれこの生を天の一方地の一角に享けて悠々たる行路をたどり、相携えて無窮の天に帰る者ではないか
国木田独歩『忘れえぬ人々』
自分と「忘れえぬ人々」との間に違いはない、みな生きている人間という点では全く同じなのだということを言っています。
そうした事を感じたとき、大津の頬には涙が伝い、自分も他人もなくなって、誰も彼も懐かしくなり忍ばれてくるのです。
このような心境に至るとき、大津はこのうえない心の平穏と自由を感じて、俗事を排して人間愛に溢れてきます。
つまり、
- 孤独→一体感→平穏と自由
という感情のプロセスを経て、人生の哀情の中に救いを見出しているのです。
大津はこのようなことを感じている人が他にもいることを信じて、「忘れえぬ人々」を主題に小説を書こうとしています。
・『忘れえぬ人々』の仕掛け
大津が人生の孤独を感じるのは、その多くが憂鬱な晩です。
僕は今夜のような晩に独り夜ふけて燈に向かっているとこの生の孤立を感じて堪え難いほどの哀情を催して来る。
国木田独歩『忘れえぬ人々』
引用部分の「今夜のような晩」というのは、うすら寒く雨がぱらぱらと降るような晩のことを指します。
ラストシーンでも、雨が降っているなかで瞑想をしている大津の姿が描かれます。
雨に催された大津がまた孤独を感じ、「忘れえぬ人々」を思い出していることが示されている場面です。
こうしたことから、彼は二年経っても「雨」によって哀情を催しており、「忘れえぬ人々」を思い出すことによって心の平穏を求めていることが分かります。
つまり、彼は二年前と比べて何にも進歩していません。
そのことは未だ原稿のままである『忘れえぬ人々』と、東北地方に住んでいる(=都市部で成功できなかった)という状況が何よりも表しているでしょう。
しかし、作中では地方と溶け合って生きている人間への肯定が読み取れることから、大津が何かを成し得ていない人物であったとしても問題はありません。
むしろ、大津自身が一地方に溶け込み、自ら「忘れえぬ人々」の一人となることは、大津自身の本望とも言えます。
作中で主体的な人物だった大津が、東北という地方に遠景化されることで客体的になり、そこで一人机の前に座して瞑想している大津の姿は、読み手である我々にとって「忘れえぬ人々」となる。
『忘れえぬ人々』は、こうした「主体=客体」の反転する構成を取っています。
そうすることで、読み手自身もまた「忘れえぬ人々」の一人なのだという「気づき」を迫る力が、本作にはあるのではないでしょうか。
-感想-
・阿蘇山の景色
『忘れえぬ人々』に出てくる阿蘇山へは行ったことがあります。
僕が人生で最も感銘を受けた景色です。
草千里ケ浜の雄大な草木地、厳しい阿蘇中岳火口、阿蘇の窪地を望む大観峰。
作中で大津は、自然の景観と人間の営為が重なっていた場面を想起することで、独自の心境に達しています。
その心持を、あの阿蘇の景色を見た僕は、どことなく分かるような気がするのです。
それは僕の感受性が豊かだとかそういった話ではありません。
多くの人があの場所に立つと感じるであろう自然の雄大さ、と同時に感じる人間の矮小さが関係しているように思います。
あの感覚は、宇宙に想いを馳せたときに感じる人間のちっぽけさとは違って、大きさと小ささが一つになったような、一体感といえば良いでしょうか。
そこに起こる微妙な切なさと、なんとも言えない幸福感のようなもの。
そうした心持ちが、『忘れえぬ人々』では描かれているように思うのです。
もちろんこの心持ちは、阿蘇に行かずとも起こり得ます。
先ほど「大きさと小ささが一つになった」と言いましたが、これは「自然と生活が一つになった」とも言い換えることができるでしょう。
「自然と生活の混ざり合い」というテーマは、国木田独歩の作品で繰り返し描かれています。
彼の小説世界に入ってゆくことで、そういった心持ちはおのずと体感していけるのかもしれません。
以上、『忘れえぬ人々』のあらすじと考察と感想でした。
この記事で紹介した作品(新潮文庫『武蔵野』に収録)