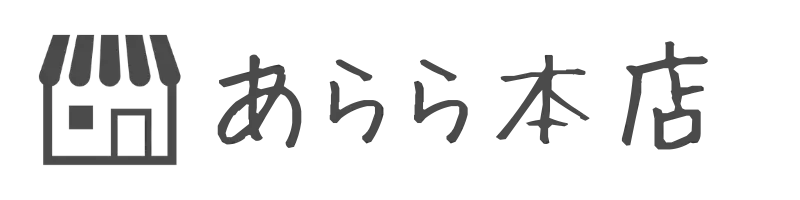隴西の李徴は博学才穎、天宝の末年、若くして名を虎榜に連ね、ついで江南尉に補せられたが、性、狷介、自ら恃むところ頗る厚く、賤吏に甘んずるを潔としなかった。
中島敦(1994)『山月記・李陵 他九篇』,p112,岩波書店.
『山月記』とは?


-あらすじ-
主人公は博学才穎の李徴。
彼は若くして官を辞して詩家を志します。しかし文名は容易に上がらずただ時だけが過ぎ、一年後遂に発狂し行方不明となります。
翌年、袁傪が陽の昇らないうちに商於の路を通ろうとしたとき、1匹の虎が彼を襲おうと躍り出ました。
しかし、どうしたことか虎は元の叢に隠れ、「危ないところだった」と繰り返しています。
その声に聞き覚えのあった袁傪は、「その声は、我が友、李徴子ではないか?」と尋ねました。
声は「いかにも」と答えます。なんと李徴は虎になっていたのです。
袁傪と虎の李徴は思わぬ再会を果たし、話は李徴が虎になった経緯へと移ります。
それから李徴は自分の詩のこと、今の気持ち、妻子のことなどを袁傪に全て話し、それを彼に託します。
夜が明けて、二人の友は別れの時を迎えます。李徴は言います。「前方百歩の所にある、あの丘に上ったら、此方を振りかえって見て貰いたい」。
袁傪一行が丘に上って振り返ると、虎が路に躍り出ます。そして三度月に咆哮したかと思うと、また元の草むらへと消えていったのです。
『山月記』-概要
| 主人公 | 李徴 |
| 物語の仕掛け人 | 袁傪 |
| 主な舞台 | 商於近辺の林中 |
| 時代背景 | 中国・唐代 |
| 作者 | 中島敦 |

商洛市は赤く囲ってあるところだ。

『山月記』-解説(考察)
袁傪というキーパーソン


そのため、物語の進行には聞き手、つまり袁傪という人物が必要不可欠となりますね。








再会した李徴と袁傪の会話。(袁傪は要点のみ抜粋)
※袁傪の部分は原文です。











(夜明けを告げる角笛がどこからか響いてくる。)




それから、丘の上まで登ったらこちらを向いてくれ。二度と私に会おうという気持ちを起こさせないためにこの姿を見せよう。

(袁傪が丘に上り振り返ると叢から虎が躍り出た。そして三度咆哮し、また叢の中へと消えていった。おわり。)





李徴と袁傪 ~『山月記』における対比構造~
















『山月記』に出てくる漢詩はどういう意味?

偶因狂疾成殊類 災患相仍不可逃
今日爪牙誰敢敵 当時声跡共相高
我為異物蓬茅下 君已乗軺気勢豪
此夕渓山対明月 不成長嘯但成嘷


『山月記』 漢詩~書き下し文~
偶(たまたま)狂疾に因って殊類と成り
災患相仍(さいかんあいかか)りて逃るべからず
今日の爪牙(そうが)誰か敢(あえ)て敵せん
当時の声跡共に相高し
我は異物と為り蓬茅(ほうぼう)の下にあり
君は已に軺(よう※馬車)に乗りて気勢豪なり
此の夕べ渓山(けいざん) 明月に対して
長嘯(ちょうしょう)を成さず但(た)だ嘷(こう)を成す
『山月記』漢詩~口語訳~
たまたま狂気のために異類となり、
さまざまの災難も重なり逃れることができない。
今や私の爪や牙に歯向かうものはいないが、
あのころの私は君とともに名声に包まれていた。
だが私はいま虎となって雑草の中にひそみ、
君は馬車に乗ってますます勢いがある。
今宵この山あいで明月を仰ぐも、
私は吟ずることができずただ吠えることしかできない。



『山月記』-感想
虫にならなかった李徴
『山月記』は人間が虎になってしまう、いわゆる変身譚です。
変身譚は昔からあるジャンルで、世界中に色んなお話があります。近代で有名なのはカフカの『変身』ですね。
『変身』は、主人公がある日突然虫になっていた物語です。作者はフランツ・カフカという人ですが、生きているうちは作品が世に認められませんでした。
しかし、中島敦はカフカがまだ世に知られていないころから彼の作品を英訳で読んでいたことが分かっています。
それだけでなく、カフカの作品に感銘を受けた中島敦は日本でも最初期にカフカの作品を翻訳しています※1。それほどまでに何か通ずるものがあったのでしょう。
さて、カフカは主人公を虫に変身させましたが、中島敦は主人公を虎に変身させました。
僕はここに彼らの精神の片鱗をみてとることができるような気がします。
カフカは実際にサラリーマン生活をしていましたが、文学に割く時間がもっと欲しいと常に嘆いていました。会社に行かずずっと家に居たい。そういう思いが主人公を家から出ない虫にしたのかもしれません。
中島敦はエリートの道を進みつつ芸術も志しながら青年時代を送りました。
そうした中で、李徴と同じような複雑な内面性が育まれたとしても想像することは難しくないでしょう。ただ、それを「虎」という猛獣にしたところに中島敦の自尊心がにじみ出ているような気はします。
主人公を通して作者へと思いを馳せることも文学の楽しみ方の一つであることを改めて実感させてくれる作品です。
以上、『山月記』のあらすじと考察と感想でした。
この記事で紹介した本