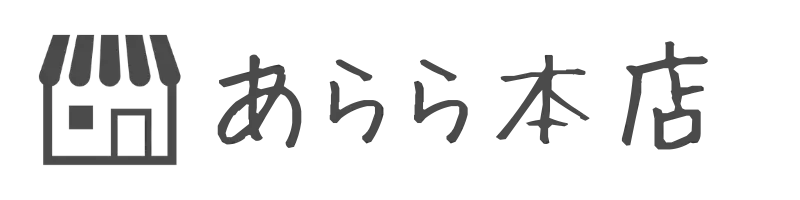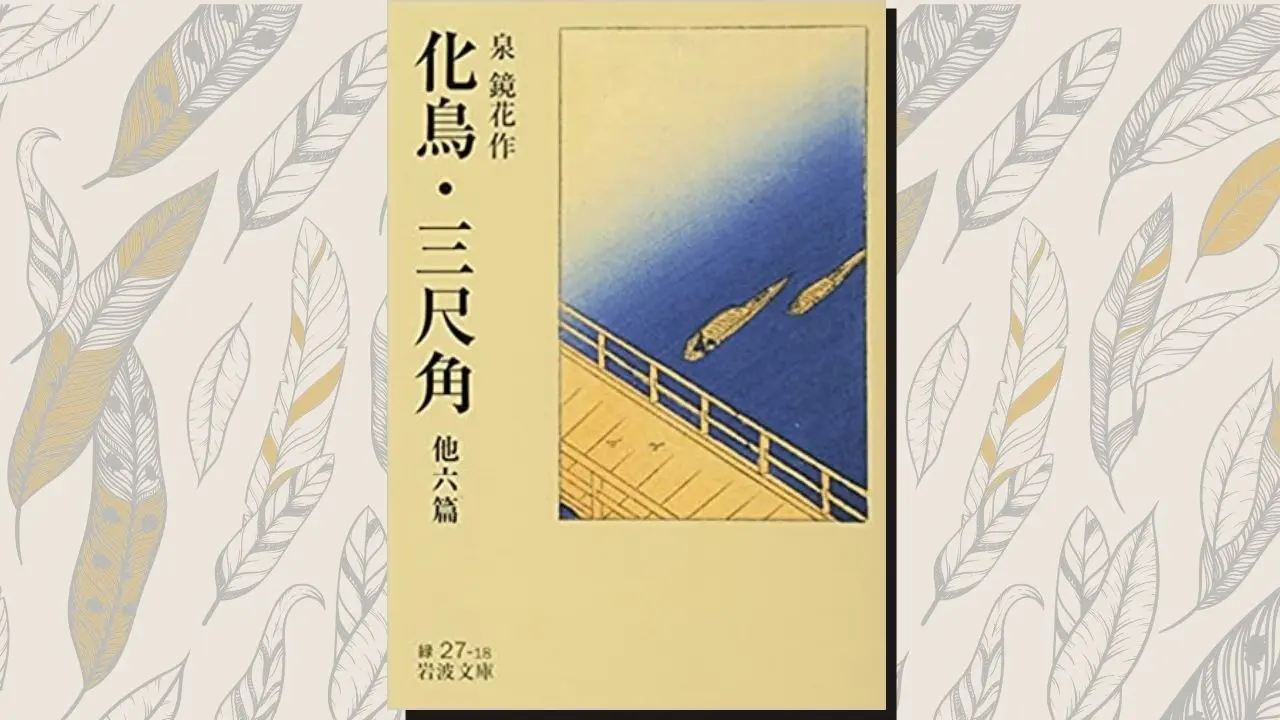『化鳥』とは?
『化鳥』は、主人公の廉を通して、神秘的な母親の神話が描かれる物語です。
零落した母親の独特な人生哲学や考え方を軸に物語が進んでいくため、一風変わった幻想&奇怪的な作品になっています。
ここではそんな『化鳥』のあらすじ・解説・感想をまとめました。
『化鳥』のあらすじ
主人公の廉は、橋の脇へ建てた小屋に、母親と二人で住んでいる。
橋は母親のもので、橋を渡る人々から通行料をもらって糊口を凌いでいる。父親はない。
廉は小屋についた窓から、橋を通る人々を眺めては、あれは猪だ、あれはアンコウだと言って面白がっている。
これは母親から教えられた考えで、「人間は獣と同じだ」という彼女の人生哲学によるものだ。
そんなだから廉は、学校でも少し変わった子どもとして先生に目を付けられている。
だけど廉にはそんなこと関係なく、「みんな今に分かる」と心の中で思い続けている。
そんな彼は半年ほど前に、石で足を滑らせて、川へ落ちたことがあった。
溺れかけて死にそうになったが、「羽の生えたうつくしい姉さん」が助けてくれた。
廉はその姉さんを探しに鳥屋へ行ったり、かつて母の御殿があった梅林へと出かけたりしたが、見つけることは出来なかった。
その代わり、梅林で奇妙な体験をした。
それは、日も暮れて辺りが暗くなった頃、フクロウや蛙がたくさん鳴いていて、廉はその声に怯えていた。
自分の身体を見ようと袖を開くと、その影が鳥のように見えたので、怖ろしくて思わずぎゃっと叫んだ。
そのとき母様が後ろから抱きしめてくれなかったら、どうなっていたかしれない。
母様の顔をそっと見上げると、このとき、「羽の生えたうつくしい姉さま」は母様だと分かった。
しかし、よく見ると背中に羽は生えていないので、やっぱりはっきりしない。
だけれども、まあいい。母様がいらっしゃるから、母様がいらっしゃったから。
・『化鳥』の概要
| 主人公 | 廉 |
| 物語の 仕掛け人 |
母様 |
| 主な舞台 | 橋小屋付近 |
| 時代背景 | 明治時代 |
| 作者 | 泉鏡花 |
-解説(考察)-
・主人公のキャラクター
『化鳥』の主人公・廉は、不思議な母親のもとで育ったがゆえに、変わった少年として幼少期を過ごします。
彼の様子からは、母親を絶対的に信奉し、彼女の言うことなら問答無用で受け入れようとする姿勢が見られます。
橋を通る人を見ては、猪だと言ったり、アンコウだと言ったりして楽しんでいますが、これは「人間=けだもの」という母親の考えから来るものです。
犬も猫も人間もおんなじだって。ねえ、母様、だねえ母様、いまに皆分るんだね。
泉鏡花『化鳥』
廉はこうした母親の考え・価値観をそのまま受け継いでいるので、学校で先生が言う「一般的」なことも間違っていると感じています。
この先生とのやり取りは、『化鳥』の物語を支える「人間=けだもの」という論理が分かりやすく書かれている場面で、物語の中でも特徴的な描写です。
ほかにも、廉が川に溺れる場面や、廉が鳥に変貌してしまいそうになる梅林での場面も、『化鳥』の特徴的な場面です。
そうした場面については、後ほど母親の考察と絡めながら見ていきます。
・母親のキャラクター
廉の母親のキャラクター像も『化鳥』の面白さを引き立たせている一員です。。
廉の母親はかつて裕福な夫人でしたが、夫が死ぬと零落し、橋の通行料で糊口を凌ぐまでになってしまいます。
彼女は没落していき、惨めな目に遭わされる中で、「人間=獣」であるという人生哲学を悟ります。
人に踏まれたり、蹴られたり、後足で砂をかけられたり、苛められて責まれて、煮湯を飲ませられて、砂を浴せられて、鞭うたれて、朝から晩まで泣通しで、咽喉がかれて、血を吐いて、消えてしまいそうになってる処を、人に高見で見物されて、おもしろがられて、笑われて、慰にされて、嬉しがられて、眼が血走って、髪が動いて、唇が破れた(中略)そういう酷いめに、苦しい、痛い、苦しい、辛い、惨酷なめに逢って、そうしてようようお分りになった
泉鏡花『化鳥』
これほどに辛いような経験をしているので、彼女は世間との関わりをほとんど持たずに生きています。
それゆえ、世間の人々は彼女を「番小屋のどうかしてるやつ」と思っています。
「どうかしてる」かはさておき、実際、彼女にはどこか魔術的な雰囲気があります。
たとえばアンコウ先生の蝙蝠傘が川へ流れる場面では、そのことがよく分かります。
ここに、その場面を会話文だけ抜き出してみましょう。
「母様、母様、母様。」
「あい。」
「あらあら流れるよ。」
「鳥かい、獣かい。」
「蝙蝠なの、傘なの、あら、もう見えなくなったい、ほら、ね、流れッちまいました。」
「蝙蝠ですと。」
「ああ、落ッことしたの、可哀相に。」
「廉や、それはね、雨が晴れるしらせなんだよ。」泉鏡花『化鳥』
『化鳥』では、人間が隠喩的な表現で獣と重ねて描かれます。
しかし、この場面で廉が言っている「蝙蝠(こうもり)」とは「こうもり傘」のことであり、実際の動物ではありません。
にも関わらず、母親は「蝙蝠ですと」と受けています。
廉がコウモリ傘であることを強調して「落っことした」と言いますが、彼女はこう続けます。
- 「廉や、それはね、雨が晴れるしらせなんだよ。」
「こうもり傘が流れる」=「雨が晴れるしらせ」になるというのは奇妙な関係性です。
一方で、「ツバメが低く飛ぶ」=「雨が降る」のように、動物と雨の関係性は簡単に連想できます。
なので読者は、動物の「蝙蝠」が川へ流れると、「雨が晴れるしらせ」なのかなと考えます。
ですが、実際に流れているのは「コウモリ傘」なので、会話のねじれを感じてしまいます。
こうした「違和感」を抱えたまま読者が遭遇するのは、
- このあと本当に雨が晴れてしまう
という奇妙な事態です。
「コウモリが流れる」=「雨が晴れるしらせ」という奇妙な関係性が、雨が晴れることによって実際に成立してしまうのです。
そうして廉は、「母様はうそをおっしゃらない」と呪文のように繰り返します。
『化鳥』のなかでも奇怪さが際だった場面だと言えるでしょう。
このような母親の魔術的・神秘的な雰囲気は、作品を通して漂っています。
次の感想では、そのような母親の深層心理について考察していきます。
-感想-
・母親の意識の告白
物語の中盤、半年前の回想という形で、主人公の廉が川に溺れる場面があります。
そのとき廉は「もう駄目だ」と思いますが、「大きなうつくしい目」を持つ人が助けてくれて、九死に一生を得ます。
その晩、廉が「助けてくれた人は誰か」と母様に問うと、いつもなら気軽に動物などに例えて返事をする母親が、この時ばかりは顔色を変えて、返答を躊躇します。
そして小さな声で、「廉や、それはね、大きな五色の翼があって天上に遊んでいるうつくしい姉さんだよ」と言うのです。
私がものを聞いて、返事に躊躇をなすったのはこの時ばかりで、また、それは猪だとか、狼だとか、狐だとか、頬白だとか、山雀だとか、鮟鱇だとか、鯖だとか、蛆だとか、毛虫だとか、草だとか、竹だとか、松蕈だとか、湿地茸だとかおいいでなかったのもこの時ばかりで、そして顔の色をおかえなすったのもこの時ばかりで、それに小さな声でおっしゃったのもこの時ばかりだ
泉鏡花『化鳥』
この場面で母親が返事に躊躇した理由は、世間の人間を「けだもの」と言っている彼女が、「そういう自分は何なのか?」ということを考えたからでしょう。
「人間=けだもの」ということであれば、人間である彼女もまた「けだもの」にほかなりません。
しかし、そのような人間たちと私は一線を画している、そんな心持ちが彼女にはあったと考えられます。
そして彼女が出した答えは、「大きな五色の翼があって天上に遊んでいるうつくしい姉さん」というものです。
自分はほかの人間とは違う、もちろんけだものとも違う、天上にいる人外の者なのだという意識の告白が、ここでは行われていると考えられます。
・「人間=けだもの」より上位の存在
物語の終盤では、主人公の廉が鳥に変貌してしまいそうになる場面があります。
自分の身体を見ようと思って、左右へ袖をひらいた時、もう、思わずキャッと叫んだ。だって私が鳥のように見えたんですもの。どんなに恐かったろう。この時、背後から母様がしっかり抱いて下さらなかったら、私どうしたんだか知れません
泉鏡花『化鳥』
廉が「ほんとうにその晩ほど恐かったことはない」というほどの場面で、『化鳥』のクライマックスシーンです。
彼は暗い梅林に一人でいて、フクロウや蛙の鳴き声がひっきりなしに聞こえ、さらには自分の影が鳥のように見え、心底怖くなってきます。
廉が「背後から母様がしっかり抱いて下さらなかったら、私どうしたんだか知れません」と言っているように、この場面は彼が鳥になってしまいそうだったことを表しています。
そのことは、タイトルが『化鳥(鳥に化ける)』となっていることからも明らかです。
ですが、結果的に彼は鳥になることなく、彼のままを保ちました。
ここで注目したいのが、彼の変貌を止めたのは、ほかでもないあの「母様」の抱擁だということ。
つまり、鳥というけだものに変貌してしまいそうになった廉を、人外の者である母親が引き留めたということになります。
「人間=けだもの」なのであれば、鳥になることをあまり嫌がらなくともよさそうなものです。
にも関わらず、母親は廉の「鳥化」を引き留め、廉自身もまた「自分が鳥に見えて怖ろしかった」と感じています。
いつもは人間を見て「猪だ」「アンコウだ」と言っている二人ですが、いざ自分が「けだもの」になるのは嫌だと見えます。
ここで分かるのは、母親だけでなく主人公の廉も、「人間=けだもの」と自分は違う存在だと思っていたということです。
つまり、彼らは「人間とけだものは同じだ」という思想を持ちつつも、自分たちはそこに属さない上位の存在だと思っていたことが読み取れます。
まとめると、『化鳥』は「人間=けだもの」から一線を画した存在である母子が、最後までけだものに墜ちることなく、自らの存在を保った物語だといえるでしょう。
こうした物語が廉の視点を借りて語られているという構図になっているので、『化鳥』は「母様」を神聖化したある種の神話のような趣きさえ感じます。
以上、『化鳥』のあらすじと考察と感想でした。
この記事で紹介した本