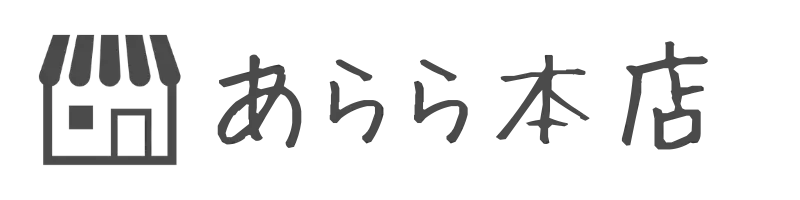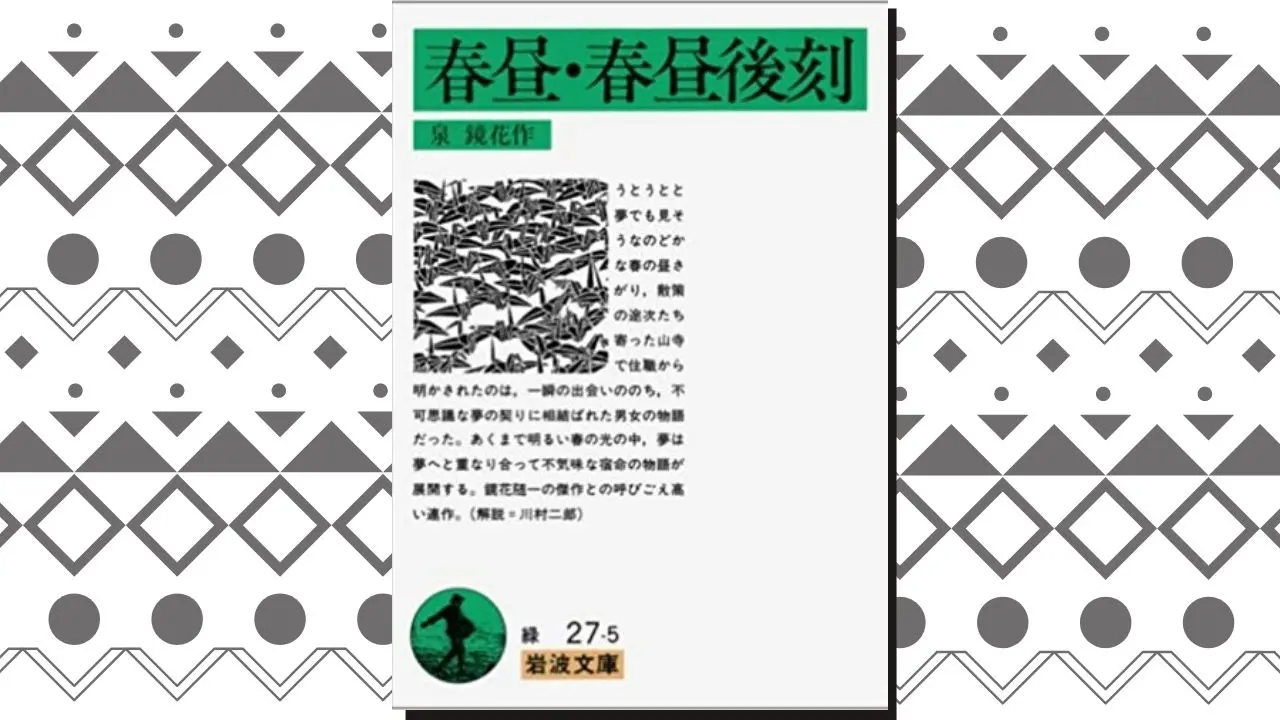『春昼』とは?
泉鏡花の『春昼』は、ある春の日に観音堂へ散策をしに行った主人公の物語。
泉鏡花の傑作としてよく挙げられる作品で、『春昼後刻』とつづき物になっています。
ここではそんな『春昼』と『春昼後刻』をまとめて、あらすじ・解説・感想までをみていきます。
『春昼』のあらすじ
主人公は逗子の町を散策しており、その日は久能谷の観音堂へ参った。
道の途中である家にヘビが入るのを見たが、自分では怖ろしいので、近くで畑仕事をしていた親仁によろしく頼んでおいた。
お堂へ着くと、壁や柱に様々な巡礼札が張られている中に、ひとつ恋の和歌が書かれているのがある。
主人公がそれを眺めていると、お堂の出家が彼に声をかけた。
去年の夏にそのお堂で寝泊まりしていた客が、主人公に似ているという。
その客は恋煩いの末に海へ入って死んだそうで、出家はその顛末を話してくれた。
客の男はこの近くに住む美しい「玉浦みを」という夫人に恋をした。
主人公がここへ来る途中、ヘビの入った家が玉浦家だという。
彼女には金持ちの夫がいるが、あまり良い扱いは受けていないように見える。
思い煩う日々を過ごす客の男だったが、ある日の晩、山の方から祭りのお囃子が聞こえると言って、お堂の裏手にある山を登っていった。
行き着いた先で男が見たのは、奇妙な舞台にいる寝衣姿の玉浦みをとその男自身だった。
驚いた男が二人を見つめていると、舞台にいるもう一人の自分が女の寝衣に「△□○」と書きはじめた。
その「○」の最後の一筆がつながったかと思うと、風がさっと吹いて、怖ろしくなった男はお堂まで走って逃げた。
その三日後に、男は死骸となって海に打ち上げられていた。
『春昼後刻』のあらすじ
主人公は出家の話を聞き終わると庵を辞した。
そして元の道を帰っていると、行きに出会った畑の親仁と出くわした。
親仁は「ヘビのことを教えてくれたお前さんに、玉浦さんがお礼がしたいそうじゃ」と言う。
気が進まなかった主人公だが、帰り道に彼女がいたので挨拶をすることに。
美しい彼女は一通りお礼を述べると、話し相手が欲しかったらしく、よもやまのことを話した。
主人公は彼女の話を聞きながら、何気なく彼女が書いたという手帳をめくっていると、蒼白くなってぞっとした。
そこにはさまざまな「○△□」がびっしりと、ページ一面に書き込まれていたからだ。
ちょうどその時、山の方から太鼓の音が聞こえてきた。子どもの旅芸人である。
夫人は子どもを呼び止めて、これを持って行って欲しいと、和歌を手帳へさらさらと書いて子どもに渡した。
主人公はそこで夫人と別れて、一度宿に戻り、それから海へ出た。
海辺には先ほどの子どもがいて、二人で遊んでいる。
と思ったら、和歌を手渡された方の子どもが、波に足を取られてざぶんと倒れ、それから浮かんでこなくなった。
もう一方の子どもが大人を呼びに行ったが、彼が助かることはなかった。
次の日、去年お堂の客が打ち上げられたのと同じ岬に、子どもは玉浦みをと一緒になって打ち上げられていた。
・『春昼』の概要
| 主人公 | 私(散策士) |
| 物語の 仕掛け人 |
玉脇みを |
| 主な舞台 | 逗子 |
| 時代背景 | 明治時代 |
| 作者 | 泉鏡花 |
-解説(考察)-
・登場人物の整理
物語を見通すために、まずは登場人物の整理をしていきます。
・散策士
散策士はこの物語の主人公で、ヘビの嫌いな若い男性です。
彼の動きに沿って、物語は進んでいきます。
前編の『春昼』ではお堂のご出家から話を聞き、後編の『春昼後刻』では玉脇みをと話をする役目です。
・畑の親仁
畑の親仁は、人の良さそうなおっとりとした人物です。
主人公の話を聞いて、玉脇家へ蛇退治に行きます。
主人公と「玉脇みを」を繋ぐ役割を担います。
・出家
「出家」は久能谷観音堂にいる僧侶です。
「出家した僧侶」を省略して「出家」と表現することで、僧侶そのものを指しています。
恋に死んだ客の話を、身振り手振りで主人公に聞かせます。
・庵室の客
庵室の客は、物語の一年前に観音堂で寝泊まりし、近くに住む玉脇みをに恋をした若い男です。
恋煩いの末、山奥で奇妙な体験をした後、鳴海岬につながる蛇の矢倉で死にます。
容貌や雰囲気が主人公と似ています。
・玉脇みを
玉脇みをは、村に住む金持ちの妻で、出自は不明ですが美しい女性です。
後編の『春昼後刻』でメインの登場人物となります。
主人公と話した翌日、角兵衛と一緒に鳴海岬へ打ち上げられます。
・玉脇斉之助
玉脇斉之助は、村の金持ちで玉脇みをの夫です。
普段は東京にいて、逗子にはあまり帰りません。
・角兵衛
角兵衛は、『春昼後刻』で玉脇みをが短歌を預けた二人の子どもです。
名前ではなく、「角兵衛獅子」という旅芸人で、獅子舞の頭部を被って踊る見世物をします。
物語のラストでは、短歌を受け取った方が海に溺れ、翌日玉脇みをと一緒に打ち上げられます。
以上が『春昼』『春昼後刻』の主な登場人物です。
登場人物を整理できたところで、次は物語に挿入される和歌の意味や「○△□」の意味などをみていきます。
・和歌や漢詩
『春昼』『春昼後刻』では、作中に和歌や漢詩がよく挿入されており、物語の特徴といえます。
特に和歌は、作品を読む上での重要なポイントにもなってきます。
作中で取り上げられている和歌・漢詩は以下の通りです。
・うたた寐に恋しき人を見てしより夢てふものは頼みそめてき/小野小町
歌意:「夢で恋しい人を見てしまってから、あてにならない夢というものを頼りにするようになってしまいました」
玉脇みをが久能谷観音堂の柱に貼り付けた歌です。
絶世の美女として有名な小野小町の和歌で、玉脇みをの容姿が美しいことにも重ねられています。
ご出家によれば、玉脇みをがこの歌を書きつけた理由は、以下の二つだと考えられています。
- 純粋に相手を想う恋の歌
- 「恋しい人」を観世音になぞらえて、観音様を一目みたいという気持ちの歌
どちらかというよりは、どちらの意味も含まれていると考えるのが、和歌らしい捉え方でしょう。
・暗きより暗き道にぞ入りぬべき遥に照せ山の端の月/和泉式部
歌意:「暗い道をより暗い道へと歩いていく。山の端へ月が出て明るく照らして欲しいものだ。」
玉脇みをが歌を書きつけた「理由」を出家が考えついたとき、彼女の心境をなぞらえるために引用した歌です。
「かすかに照らせ山の端の月、と申したように、観世音にあこがるる心を、古歌に擬らえたものであったかも分りませぬ。」
泉鏡花『春昼』
- 「暗き道」=煩悩や心の闇
- 「山の端の月」=観音による救いの光
と解釈すると、この歌は悩める人が観音に救いを求める歌だと読むことができます。
これを出家は、「うたた寐に恋しき人を見てしより夢てふものは頼みそめてき」も同じような事かもしれない、と連想したのです。
本文が「かすかに照らせ」となっているのは、鏡花の引用ミスである可能性が高いかもしれません。
・君とまたみるめおひせば四方の海の水の底をもかつき見てまし/和泉式部
歌意:「あなたにもう一度お会いできるなら どこの海の底でも潜って探そう」
玉脇みをが、角兵衛に預けた紙に書いた恋の歌です。
その後、彼女はこの歌と同じように、海に入って死んでしまいます。
一年前には「庵室の客」が海に入って死んだので、この歌意と合わせて考えると、彼を探しに行ったのだろうか?と思わせる一連の出来事になっています。
玉脇みをと「庵室の客」が、なんらかの関係性によって繋がっていたことを強調している和歌です。
・蝋光高懸照紗空~/李賀
詩の大意:「もしあなたが優しい方なら、私を解き放ってください。もし今すぐ自由になれるなら、故郷へと帰りたいのに。」
庵室の客が、懐から出した本に書かれてある詩がこの『宮娃歌』です。
原文は長いですが、一応引用しておきます。
蠟光高懸照紗空
花房夜擣紅守宮
象口吹香毾㲪暖
七星挂城聞漏板
寒入罘罳殿影昏
彩鸞簾額著霜痕
啼蛄弔月鉤欄下
屈膝銅鋪鎖阿甄
夢入家門上沙渚
天河落處長洲路
願君光明如太陽
放妾騎魚撇波去李賀『宮娃歌』
ひとり里に放っておかれている「玉脇みを」と、詩の中で幽閉されている「妾」が重ね合わせられています。
また、「放妾騎魚撇波去(私を放ち、魚に乗って去らせてください)」とあるように、海へ入っていく二人の末路とも重なります。
以上の和歌や漢詩が作中に出てくることで、物語はより重層化し、奥行きが作り出されています。
ほかにも、「ぶんぶく茶釜」や「観音経」なども、同じような効果を生むため間接的に挿入されています。
・「○△□」という記号
『春昼』『春昼後刻』で特に奇妙なのが、「○△□」の記号です。
庵室の客が山へ行くと、そこで玉脇みをと自分のドッペルゲンガーを見ます。
そしてドッペルゲンガーは、玉脇みをの寝衣に「○△□」の記号を書くのです。
それだけでも奇妙ですが、『春昼後刻』では「玉脇みを」も手帳にびっしりと「○△□」を書いていることが分かります。
この「○△□」とは一体何を表しているのでしょうか?
その答えは『春昼後刻』で玉脇みをが言うセリフから読み取ることができます。
この円いのが海、この三角が山、この四角いのが田圃だと思えばそれでもようござんす。それから○顔にして、□い胴にして△さに坐っている、今戸焼の姉様だと思えばそれでも可うございます、袴を穿いた殿様だと思えばそれでも可いでしょう。
泉鏡花『春昼』
つまり、「○△□」は何に見立ててもよく、何と思ってもよいということです。
ただし、これは読み手が「○△□」をどう解釈しても良いというわけではありません。
庵室の客と玉脇みをが「○△□」を何に見立てていたか、なんと思っていたかを考えなければならないからです。
ちなみに「○△□」は研究者の間でもよく議論されており、明確な答えは出ていません。
なので、以下は個人的な解釈となります。
この「○△□」は、
- 庵室の客が玉脇みをの寝衣に書いた「○△□」
- 玉脇みをが手帳に書いた「○△□」
の二つがあります。
なので、それぞれの立場から同じ意味の「○△□」が書かれているのか、それとも違う「○△□」が書かれているのか、という点がまず分岐します。
それぞれ違う「○△□」が書かれているという視点では、
- 庵室の客の「○△□」=玉脇みを
- 玉脇みをの「○△□」=庵室の客
だと考えます。
これは、お互いを「○△□」という記号に落とし込むことで、「○△□」という偶像を作り出しているという考え方です。
つまり、「○△□」と書くだけで相手のことを想うことができる、ということになります。
唱えれば極楽へ行けるお経などと似ていますね。
「○△□」と書くことで、相手の霊魂を通わせる取っ掛かりにしているのではないでしょうか。
一方で、同じ「○△□」が書かれているという視点では、
- 「○△□」=愛しています
というロマンチックな言葉が入るかもしれません。
ただし、そうなれば玉脇みをが手帳に「愛しています」とびっしり書いていることになるので、それはそれでなかなか狂気的ではあります。
(いずれにせよあの場面は「狂気的な怖さ」がある場面なので問題はありませんが。)
・記号からの脱却
こうした『春昼』の記号に関しては、主人公が冒頭でも似たようなことを言っています。
温和そうな主人公が「偶像」について語り、珍しく熱くなる場面です。
唯、人と言えば、他人です、何でもない。これに名がつきましょう。名がつきますと、父となります、母となり、兄となり、姉となります。そこで、その人たちを、唯、人にして扱いますか。偶像も同一です。唯偶像なら何でもない、この御堂のは観世音かんぜおんです、信仰をするんでしょう
泉鏡花『春昼』
ただ記号だったものに名前がつく。そうして名がついて浮かび上がってきた実体を想うことが大事なのだ、という論旨です。
このような、
- 記号と実体
を象徴的に表している場面があります。
それは、出家の話す「女人の名前が彫られた石地蔵」の場面です。
この坂の両方に、五百体千体と申す数ではない。それはそれは数え切れぬくらい、いずれも一尺、一尺五寸、御丈三尺というのはない、小さな石仏がすくすく並んで、(中略)一々女の名と、亥年、午年、幾歳、幾歳、年齢とが彫りつけてございましてな、何時の世にか、諸国の婦人たちが、挙って、心願を籠めたものでございましょう。
泉鏡花『春昼』
この石地蔵は、ただの石を切り出したものに、女の名前を彫りつけることで、石を「偶像化」しています。
しかし、地蔵はかなり前に作られたものであり、今ではこの石地蔵を思う人などいません。
なので、石地蔵から実体が浮かび上がることはなく、記号としてのとしての石地蔵にとどまっていることになります。
この場面はのちに、庵室の客が「山の壁際に女がずらりと並ぶ光景」を見る場面と繋がります。
不細工ながら、窓のように、箱のように、黒い横穴が小さく一ツずつ三十五十と一側並に仕切ってあって、その中に、ずらりと婦人が並んでいました。
泉鏡花『春昼』
壁際の穴の中にずらりと並ぶ女が、先ほどのずらりと並ぶ石地蔵と重ねられていることが分かります。
女たちは誰からも想われることがなければ、石地蔵と同じように、ただの記号としての「女」です。
しかし、誰か想ってくれる人がいれば、「女という記号」から抜け出し、名を持った個人として実体を持ちます。
すなわち、玉脇みをがこのとき舞台へと上がってきたのも、庵室の客という彼女を想う人があったからだと考えられるでしょう。
ここで庵室の客のドッペルゲンガーは、彼女の寝衣に「○△□」を書くのです。
これは相手を「○△□」という偶像にすることで霊魂を通わせようとしているのか、はたまた「愛しています」などの意味なのか、それとも全く別の何かか。
あなたなりの「○△□」を考えてみると、『春昼・春昼後刻』はより楽しめる作品になります。
ー感想ー
・『春昼』の醍醐味
ここまで、「○△□」の意味や、庵室の客・玉脇みをの悲恋などを中心にみてきました。
しかし『春昼』の醍醐味は、むせ返るほど濃い草の香りが漂う「春の昼」が描かれている点にあると思います。
みなさんは、春の昼と聞くとどんなイメージが思い浮かぶでしょうか。
「のどか」だとか、「のんびり」だとか、ほのぼのとした風景だという人が多いかもしれません。
しかし、泉鏡花の描く春の昼は少し違います。
ずたずたに切られるようで、胸を掻きむしられるようで、そしてそれが痛くも痒くもなく、日当りへ桃の花が、はらはらとこぼれるようで、長閑で、麗で、美しくって、それでいて寂しくって、雲のない空が頼りのないようで、緑の野が砂原のようで、前生の事のようで、目の前の事のようで、心の内が言いたくッて、言われなくッて、焦ッたくって、口惜くッて、いらいらして、じりじりして、そのくせぼッとして、うっとり地の底へ引込まれると申しますより、空へ抱き上げられる塩梅の、何んとも言えない心持
泉鏡花『春昼』
がする春の日の昼なのです。
これを主人公と玉脇みをの二人は、「厭な心持」のする気候だと述べています。
春独特の寂しさ。「鼓草(たんぽぽ)の花が、ふっと、綿になって消えるように魂がなりそう」な柔らかい午後の日差し。
そんな春の昼に、主人公はご出家から奇妙な物語を聞きます。
その後、翌日には自殺してしまう玉脇みをとも話をします。
そんな出来事があった「春昼」を、主人公は生涯忘れることがないでしょう。
のどかで麗らかな春の日が訪れるたび、彼は何度でもこの日を思い出すのです。
穏やかで優しく柔らかな風が吹くたび、「厭な心持」だと言っていた女性がいたことを思い出すのです。
そうしてそれを思い出すのは、僕たち読者もまた同じなのかもしれません。
以上、『春昼』のあらすじと考察と感想でした。
この記事で紹介した本