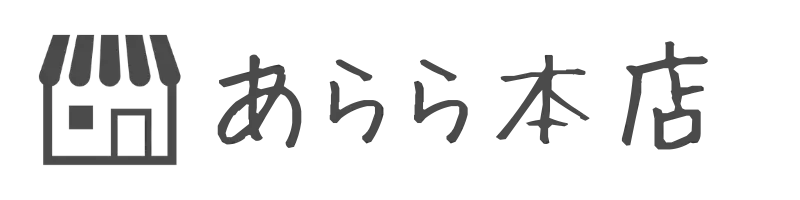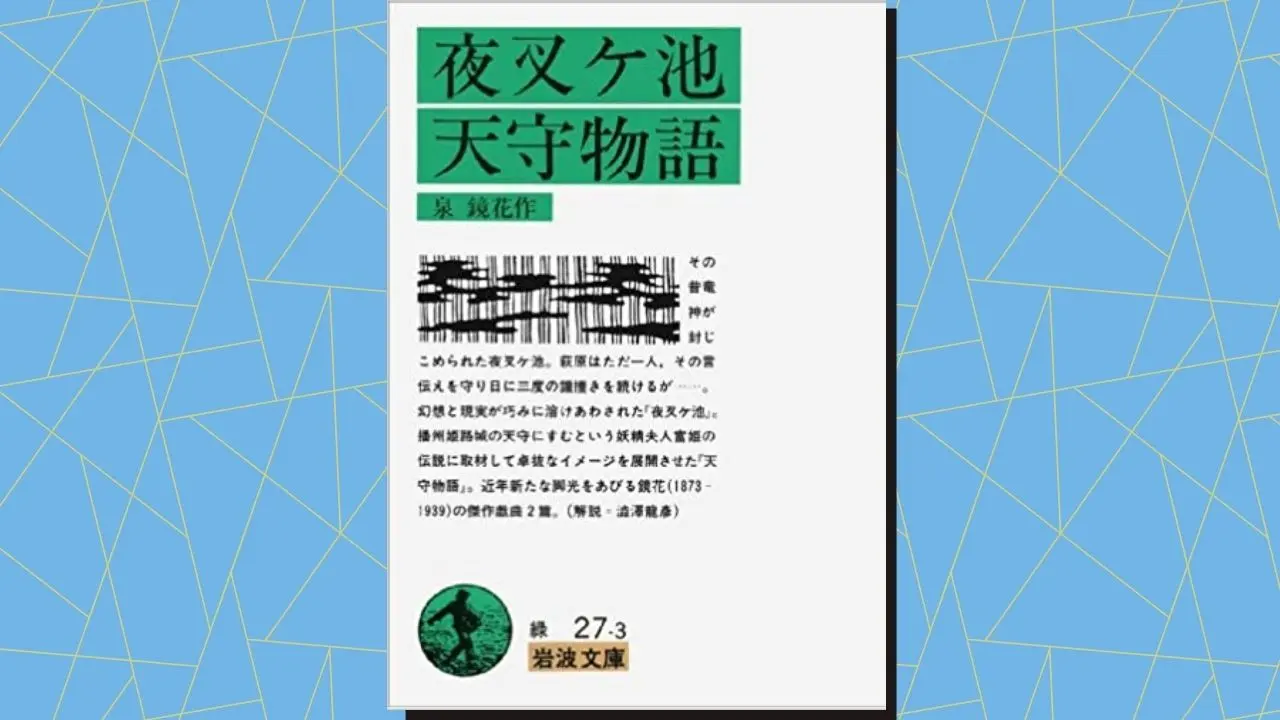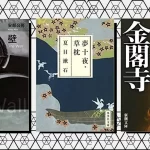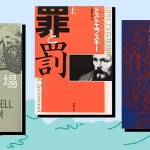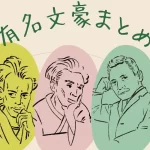『夜叉ヶ池』とは?
『夜叉ヶ池』は、日に三度鐘を撞くことで、池の竜神から村を守っている男の物語です。
魑魅魍魎、水、美しい女性など、鏡花らしいモチーフが「物語」となって描かれます。
ここではそんな『夜叉ヶ池』のあらすじ・解説・感想をまとめました。
『夜叉ヶ池』のあらすじ
時は明治後期、鹿見村というところに、萩原晃という男と、お百合という女が住んでいた。
萩原は各地に伝わる物語を探し求めていたところ、鹿見村琴弾谷にある夜叉ヶ池の竜神伝説を聞いて、この土地にやってきた。
そこには、毎日三度の鐘を鳴らすことが、古くに竜神と人間の結んだ契りだと言って、鐘の音を絶やさない翁がいたが、萩原の前で突然死してしまう。
翁は萩原に役目を継いで欲しいと願い、萩原はそれを引き受ける。
その鐘を鳴らすことをやめてしまうと、たちまち竜神が洪水を起こし、八千人の命が流れてしまうのだという。
しかし、村人たちの中で竜神伝説を信じていたのは翁一人で、それを引き継いだ萩原は村人たちに馬鹿にされる。
ただ、お百合という女性だけは萩原を慕い、二人は生活を共にして、気づけば二年が経っていた。
そこへ学円という男が、竜神伝説で名高い夜叉ヶ池を見に、この鹿見村へやって来た。
彼は京都大学の教授で、萩原とは友人だった。
出会った二人はこれまでの経緯を話し、学円は萩原がここを離れられない理由を知る。
一方、夜叉ヶ池では白雪という竜神が、剣ヶ峰の千蛇ヶ池にいる若旦那に恋い焦がれている。
しかし、剣ヶ峯に行くには、この辺りの山一帯を川に変える必要がある。
白雪は恋心を抑えきれず、人間との誓いを破って洪水を起こそうとするが、大姥や蟹、鯉などの眷属に押しとどめられる。
その日の夜、萩原と学円は夜叉ヶ池に向かい、家にはお百合が一人、鐘を鳴らすために残っていた。
それを好機と、村長や村の役員などが、お百合を攫いに来る。
今年のひでりが酷いので、村一番の美女であるお百合を生贄に捧げようというのだ。
嫌な予感がした萩原は夜叉ヶ池から引き返し、間一髪お百合が攫われるのを引き留める。
しかし村の人間たちは、殺してでも連れて行くという。
押し問答の末に、お百合は自分で胸を裂き、萩原も後を追った。
鐘を撞く者はいなくなったので、村は洪水に襲われて、村人は全て魚に変わった。
学円だけは高く一人鐘楼に佇み、川となった村を見て合掌した。
・『夜叉ヶ池』の概要
| 主人公 | 萩原晃 |
| 物語の 仕掛け人 |
百合 |
| 主な舞台 | 越前国大野郡鹿見村琴弾谷 |
| 時代背景 | 明治後期~大正初期 |
| 作者 | 泉鏡花 |
-解説(考察)-
・主要な登場人物
・萩原晃
萩原晃は『夜叉ヶ池』の主人公で、百合の夫です。
先代の鐘撞き弥太兵衛のあとを継いで、毎日三度の鐘を撞いています。
物語を集めるために東京から鹿見村に来て、それから二年も滞在しています。
・百合
百合は村一番の美人です。
親兄弟はなく、叔父だけが親類として生きています。
萩原晃のために、旅人から物語を聞いています。
・山沢学円
学円は萩原の友人で、京都大学の教授(文学士)です。
浄土真宗本願寺派の坊主でもあります。
夜叉ヶ池を見に鹿見村へ訪れて、思いがけなく萩原と再会します。
・白雪姫
白雪姫は、夜叉ヶ池の竜神です。
千蛇ヶ池にいる若旦那に恋をしています。
かつて鹿見村で生贄にされた少女も、同じく白雪という名前でした。
・万年姥
万年姥は、白雪姫に仕える眷属の中でも、側近的な立場の魔物です。
針のような白髪で、見た目はお婆さんですが、人間離れした力をもっています。
だだをこねる白雪に対して、長者らしく落ち着いて振る舞います。
・弥太兵衛
弥太兵衛は、鹿見村で唯一、鐘撞きの伝承を守っていた翁です。
萩原と出会ったときに突然死してしまい、鐘撞きの伝統を萩原に託します。
以上の6人に加えて、ラストシーンでは村人たちがまとめて登場します。
次には『夜叉ヶ池』で描かれているテーマを見ていきます。
・「恋」というテーマ
『夜叉ヶ池』は「恋」がテーマの作品です。
作中では二つの恋が描かれます。
- 萩原晃とお百合の恋
- 白雪姫と千蛇ヶ池の若旦那
の二つです。
ただこの二つの恋は、二人の仲を引き裂く原因が違います。
たとえば萩原とお百合の恋は、「村の伝統」によって引き裂かれています。
お百合は村一番の美女なので、雨ごいのために生贄に捧げられなければなりません。
生贄という村人たちの伝統に阻まれて、萩原とお百合は村を出て行くことが出来ないのです。
一方で、白雪と若旦那の恋は「人間との約束」によって引き裂かれています。
竜神である彼女が池を離れると洪水が起き、そうなると昔に人間とした約束を破ってしまうことになるからです。
約束を破ってでも剣ヶ峰へ行きたい白雪ですが、「義理や仁義」を重んじている眷属たちに阻まれて行くことが出来ません。
最終的には、お百合の美しい歌声を聞いて、その感情も落ち着きます。
白雪「恋しい人と分れている時は、うたを唄えば紛れるものかえ。」
泉鏡花『夜叉ヶ池』
明治という時代は、西洋からきた文明開化とともに、自由恋愛が芽吹きかけていました。
しかし、根強く残っている「伝統」や「義理」に阻まれて、現代ほど自由な恋愛ではありません。
こうした恋の障害が、『夜叉ヶ池』では描かれています。
ちなみに泉鏡花の『婦系図』という小説でも、同じようなテーマが扱われています。気になった方はぜひ読んでみて下さい。
『婦系図』のあらすじ・解説はこちら▽
-
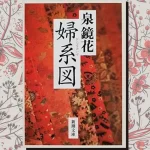
-
小説『婦系図』あらすじ&解説&感想!登場人物から早瀬主税の心理考察まで!
続きを見る
・「物語」という構成
『夜叉ヶ池』で面白いのは、「物語」になってしまったという主人公の感覚です。
僕は、それ諸国の物語を聞こうと思って、北国筋を歩行いたんだ。ところが、自身……僕、そのものが一条の物語になった訳だ。
泉鏡花『夜叉ヶ池』
物語とは、不思議な出来事や、現実的でないこと、興味深いことが語られます。
萩原は『夜叉ヶ池』という作品の中で現実の人間ですが、「古い言い伝えを守ってずっと鐘を撞く男になった」という現象を、「自分が物語になった」と言い表しているのです。
このような萩原の物語を、読者である我々は『夜叉ヶ池』という作品を通して見ることになります。
つまり、物語が物語に包まれるという構成になっているのです。
こうした構成に創りあげることで、物語は現実から遠ざかり、魑魅魍魎や竜神といった人ならざる者の存在が描きやすくなります。
また物語の構造上、この「物語」を広め伝えたのは、洪水の唯一の生き残りである学円しかあり得ません。
学円、高く一人鐘楼に佇み、水に臨んで、一揖し、合掌す。
月いよいよ明なり。泉鏡花『夜叉ヶ池』
だとすれば、『夜叉ヶ池』は本当に起こった出来事ではなく、行方不明の友人を思って描かれた学円の「物語」である可能性も出てきます。
こうして物語は二重、三重と虚構性に包まれていき、描かれる幻想性が受容可能なものとなるのです。
このような構成が、『夜叉ヶ池』という作品を支えている物語上の仕掛けだといえるでしょう。
-感想-
・「水」と白雪の人間味
幻想性・怪奇性が泉鏡花の特徴だとするならば、『夜叉ヶ池』はその特徴が存分に発揮されている作品です。
鏡花の幻想的な作品で、かつ代表的なものには、『化鳥』『高野聖』『草迷宮』などがあります。
そのいずれにも水流が出てくるため、「水」は鏡花作品に見られる特徴的なモチーフといえるでしょう。
その中でも、洪水が関わっている作品は、『高野聖』『照葉狂言』『龍潭譚』などが挙げられます。
言うまでもありませんが、『夜叉ヶ池』も水が深く関わる作品で、洪水が直接描かれる物語です。
水の源流は夜叉ヶ池という竜神の住む池で、人々が「義理」を裏切ったために氾濫します。
自然の化身である白雪は、人々が義理を守らなければ滅びが待っているということを体現している存在です。
しかし、彼女自身も「恋」のために約束を違えようとしてしまう人間味があります。
このような「人間味が許された自然」という描写によって、物語が教訓的になってしまうのを防いでいます。
こうした繊細なバランスの取られ方が、『夜叉ヶ池』の魅力的なポイントでもあります。
・百合の自決と『外科室』
終盤で、逃げ切れなかった萩原と百合が自決する場面があります。
先ほども書いたように、彼らは「伝統」に阻まれて恋が叶いませんでした。
これは、「身分違いという伝統」に阻まれて恋が叶わなかった、『外科室』の高峰と貴船夫人の二人を想起させます。
また、伝統に阻まれるという図式だけでなく、百合と貴船夫人の両女性が、胸を掻き切って自決するという行動も全く同じです。
ただし、『外科室』では死後の様子が直接描かれることはありませんでしたが、『夜叉ヶ池』では二人の死後の様子が描かれています。
この『夜叉ヶ池』の様子から推測すると、『外科室』の二人も死後に一緒になったと考えることができます。
『外科室』の独特な幻想性は、それは鏡花の中にある創作の光が「お化け」を書かずして生まれたものだからかもしれません。
ちなみに、個人的には『外科室』が泉鏡花の作品の中で最も幻想的な小説だと思っています。
『外科室』のあらすじ・解説も書いているので、良ければ見てみて下さい。
-
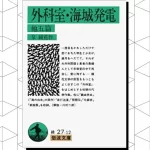
-
小説『外科室』あらすじから結末まで解説!「忘れません」の意味と手術台の象徴とは?
続きを見る
以上、『夜叉ヶ池』のあらすじと考察と感想でした。
この記事で紹介した本