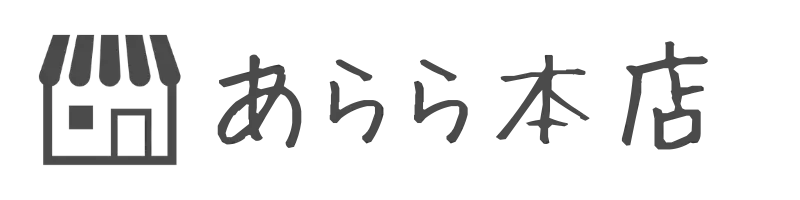『高野聖』とは?
『高野聖』は、ある旅僧が飛騨の山越えをしたとき、怖ろしく奇妙な体験をしたことを、主人公に話して聞かせる物語です。
泉鏡花の代表作として有名で、日本においても幻想・怪奇小説の金字塔といえるでしょう。
ここではそんな『高野聖』のあらすじ・解説・感想をまとめました。
『高野聖』のあらすじ
主人公の「私」が汽車で名古屋から敦賀に向かう途中、ある旅僧と一緒になった。
その旅僧は、高野山の宋朝(そうちょう)という大和尚であるらしい。
主人公は旅の一人なのを心細く思っていたので、泊まりをご一緒してくれないかと持ちかけた。
その晩、宿の布団のなかで、僧がこんな話をした。
「わしがまだ若い時分、飛騨の山越えをしようと思ったときの話だ。
山の麓の茶屋で、性格の悪い薬売りと出会った。
わしは良い気分に思わなかったから先に行くと、薬売りは追いついてきて、そうして追い越していった。
そらからしばらく進むと分かれ道があって、そこで薬売りが立ち止まっていた。
悩んだあげく、薬売りは険しい道を先に行ったが、わしには歩けそうにもない。
そこで出くわした百姓に聞くと、片方は本道、片方は旧道らしい。
旧道は人の通れた道ではなく、迷い人が出るほどで、命が欲しければ本道にしておけという。
しかし、薬売りが行ったのはその旧道だから、これでは見殺しにしたも同然だ。
わしも僧侶の端くれであるから、薬売りを助けるために、同じく旧道を歩いて行った。
山を進むと、蛇やら蛭(ひる)やらがいて、ことに蛭などは夥しく、木にびっしりと付いていて、わしの身体へくっついては血を吸った。
必死の思いで山を越えると、どこからか馬の鳴き声が聞こえた。
これはと思い、少し行くと独家があって、そこにはきれいな女と白痴の青年が住んでいた。
もう歩を進めることができないわしは、彼女に一宿を頼むことにした。
蛭に身体中を吸われているので、痛くて痒くてたまらない、女の薦めもあって川に水浴びをしに行った。
途中、女が「おじさま」と呼ぶおやじに出会うが、どうやら血縁関係ではなさそうだ。
川へ入ると心地良いことこの上なく、僧の身ながら裸になって、女に背中を洗ってもらった。
女も汗をかいたからと、白く美しい肌を露わにして身体を清めはじめたから、わしは驚いたが平静を保った。
その日の晩、おやじは馬を町に売りに行くと言って出かけ、わしは一人女の厄介になった。
晩飯の席で、わしが「薬売りがここを通らなかったか」と聞くと、女はどこか訳ありげな笑いを漏らしたが、「知らない」と答えた。
夜も更けて床につくと、表では動物たちがこの独家を囲んで走り回っている様子なので、わしは怖じ気づいて念仏を唱えたほどだ。
あくる日、独家を出て里へ下りたときに、馬を売った帰りのおやじに出くわした。
滝を見ながら、あの女と一生をともに過ごそうかと考えていた折だったので、声をかけられたわしは驚いた。
その様子を見抜いたおやじは、こんなことを言って聞かした。
「お前さんもお嬢に取り憑かれたのだね。
しかしお嬢はやめておいた方が良い。
彼女は男を惑わして、獣に変える力を持っているんだ。
現にあの馬を見ただろう。あれは昨日お嬢に助平心を起こした薬売りさ。
だから余計な心は起こさずに、早くここをお発ちなされ。」
それを聞いたわしは魂が身に戻ってきて、一散に里を駆け下りたのだ。」
話を聞いた翌朝、主人公は雪中山越えを行く聖と名残惜しく別れた。
次第に高く坂道を上る聖の姿は、まるで雲に乗っていくかのように見えた。
・『高野聖』の概要
| 主人公 | 私(聞き手) |
| 物語の 仕掛け人 |
旅僧(宋朝) |
| 主な舞台 | 飛騨山脈 |
| 時代背景 | 明治時代 |
| 作者 | 泉鏡花 |
-解説(考察)-
・主な登場人物
私
「私」は一人旅をしている若者です。
一人なのを淋しく思い、宋朝に泊まりの同行を頼みます。
物語内では「聞き手」の役割をこなすと同時に、『高野聖』という物語の語り手でもあります。
宋朝(高野聖)
宋朝(そうちょう)は、物語の主軸となる「飛騨山越での不可思議な出来事」を語る高野山の大和尚です。
年は45.6歳で、「宗門名誉の説教師」とあるように、民衆へ向けたお話しが上手な語りのプロだといえます。
薬売り
薬売りは、宋朝が飛騨の山越えをするときに、麓の茶屋で出会った人物です。
俗人的な性格で、「けたいの悪い、ねじねじした厭な壮佼(わかもの)」として描かれます。
彼は後に「嬢様」によって馬に変えられてしまいます。
嬢様
嬢様は、山を越えたところにある「独家」に住む女で、物語の最も重要な登場人物です。
宋朝は彼女に泊めてもらいますが、後に「男を虜にして動物に変える鬼女」だったことが明かされます。
十三年前に起きた洪水の生き残りで、玉のように美しく、幼い頃から不思議な力を持つとされていました。
聖性と魔性の両方を持つ女性として描かれています。
親仁
「親仁」も十三年前の洪水の生き残りで、嬢様の世話をしている人物です。
動物に変えられた人間を町へ売りに行っては、生活の足しにしています。
宋朝に女の正体を明かし、もう近づかないようにと警告し、よく修行しろと励まします。
次郎
独家の女と一緒に住む白痴の青年です。
その見た目とは裏腹に、とてもきれいな歌声をもっています。
足の腫れ物を女の父親に診てもらっていたが治らず、手術にも失敗したので不具のまま生きています。
彼の身体描写には動物的な比喩が多用されているので、あえてグロテスクに描かれていることが分かります。
以上が『高野聖』の主な登場人物です。
登場人物を押さえたところで、次は『高野聖』の特徴でもある「幾層にも重なる語りの構造」をみていきます。
・『高野聖』の構造
『高野聖』は語りを重層化させることで、物語の幻想性を増す手法が採られています。
『高野聖』の語りは以下のような形です。
- 『高野聖』という物語
- 『高野聖』という物語の中で語られる「宋朝の物語」
- 『高野聖』という物語の中で語られる「宋朝の物語」の中で語られる「親仁の物語」
まず、「私」と宋朝が出会う『高野聖』としての物語が、一番外側にある枠になります。
汽車に居合わせた二人は、成り行きで同じ宿の泊まることになり、そこで宋朝の不思議な体験談が始まるのです。
次がその「宋朝の物語」で、美しい女の住む独家で起きた奇妙な出来事がメインです。
そして最後には、「宋朝の体験談」の中で出てくる「親仁の話」が語られます。
この親仁の話で、実は独家の女が通りかかった男を虜にする魔性の女であることが明かされるのです。
このように『高野聖』の語りは重層化していき、手前の語りほど現実的で、奥に行くほど非現実的な出来事が語られます。
言い方を変えれば、語りが重層化するにつれて、物語は幻想的なベールをまとっていくともいえるでしょう。
こうした手法によって、『高野聖』の幻想性は作られています。
次にはそんな『高野聖』の幻想的な名場面を三つみていきます。
・『高野聖』の怪奇・幻想的な名場面
1.蛭の森
何にしても恐しい今の枝には蛭が生っているのであろうとあまりの事に思って振返ると、見返った樹の何の枝か知らずやっぱり幾ツということもない蛭の皮じゃ。
泉鏡花『高野聖』
山を越える道の途中で、宋朝は大森林に入ります。
そこは「蛭(ひる)」がおびただしく住まう森で、宋朝が通ると血を求めて身体にぼたり、ぼたり、と落ちてくるのです。
血を吸ってぶくぶくと太った蛭の描写はグロテスクで、目を細めたくなるようなおぞましさがあります。
ここで注目したいのは、宋朝が思わず想像した不気味な世界観です。
およそ人間が滅びるのは、地球の薄皮が破れて空から火が降るのでもなければ、大海が押被さるのでもない、飛騨国の樹林が蛭になるのが最初で、しまいには皆血と泥の中に筋の黒い虫が泳ぐ、それが代がわりの世界であろう
泉鏡花『高野聖』
これは、蛭が人間の血を大量吸って、その血を山に吐き出すことで、山の土は血の泥と化すだろうという想像をもとに、宋朝が考えたことです。
ここにきて視点は、
- 蛭→木→山
と拡大していき、現実的なグロテスクさは抽象的な畏怖と混ざり合っていきます。
まさに血と土が混ざり合って血の泥が出来るように、なんとも言えない不気味さが形成されていくのです。
そのため「蛭の森」はグロテスクなだけではない、幻想的ともいえる場面になっていきます。
2.女との水浴び
『高野聖』を代表する名場面といっても過言ではないのが、宋朝と独家の女が川で水浴びをする場面です。
水を浴びる女の妖艶な美しさと、宋朝の性的な欲望の揺らぎが描かれています。
泉鏡花の作品では「水」が登場人物の転換点になることが多く、『高野聖』でもその傾向は見られます。
若い修行僧である宋朝は、蛭に吸われた身体を清めるために「川」へ入り、女に背中を流してもらうことで「得も言われぬ心地の良さ」を感じます。
その心地の得もいわれなさで、眠気がさしたでもあるまいが、うとうとする様子で、疵の痛みがなくなって気が遠くなって、ひたと附ついている婦人の身体で、私は花びらの中へ包まれたような工合。
泉鏡花『高野聖』
しかし、危ういところで蝙蝠や猿が現れて、女は怒って場の空気は一転。
後になって分かることですが、この動物たちは川で女に魅了され動物になった男たちです。
つまり、宋朝にとってこの「川」こそが運命の分かれ道であり、もしかすると動物になっていたかもしれないという場面です。
それを乗り切った彼は、僧侶として一回り大きくなったことを表します。
このように、「川」での場面は女の艶やかさに加えて、実は宋朝にとって運命の分かれ道だったという危うさもあり、ことさら幻想性を帯びている場面となっています。
3.「独家の夜」と「雲に駕す宋朝」
川での女の誘惑を断ち切った宋朝ですが、その日の晩、家の外で不気味な気配を感じます。
二十三十のものの鼻息、羽音、中には囁いているのがある。あたかも何よ、それ畜生道の地獄の絵を、月夜に映したような怪しの姿が板戸一枚、魑魅魍魎というのであろうか、ざわざわと木の葉が戦そよぐ気色けしきだった。
泉鏡花『高野聖』
羊・牛・むささみなど、あらゆる獣の足音、気配がするのです。
それに加えて、納戸にいる女の「今夜はお客様があるよ」という叫び声が聞こえ、外のものが盛んに動くために家が揺れます。
このような様子が、「魑魅魍魎」や「畜生道の地獄の絵」といった言葉で描かれているので、仏画を連想させるような仕掛けになっています。
ちなみに、芸術的・幻想的だと言われる近代日本の小説には、どこか「仏教絵画」的な趣があることが多いです。たとえば芥川の『地獄変』なんかもそうですね。
『高野聖』ではラストシーンも仏画的な描写だといえます。
ちらちらと雪の降るなかを次第に高く坂道を上る聖の姿、あたかも雲に駕して行くように見えた
泉鏡花『高野聖』
雲に駕していく、つまり「雲に乗っていく」ように見えたというのは、あきらかに仏画が念頭に置かれた表現です。
「雲に乗っている仏」は仏画でよく使われるモチーフです。
仏のイメージと宋朝が重ねられているのですから、「私」はラストシーンで宋朝の姿に仏性を見い出したということが分かります。
こうした「独家の夜」と「雲に駕す宋朝」の仏画的なシーンも、怪奇・幻想的な場面です。
・念仏の意味
宋朝は先ほど述べた「独家の夜」の場面で、怖じ気づいて念仏を唱えます。
「陀羅尼品」という念仏で、作中には以下の文言が記されます。
若不順我呪 悩乱説法者
頭破作七分 如阿梨樹枝
如殺父母罪 亦如厭油殃
斗秤欺誑人 調達破僧罪
犯此法師者 当獲如是殃泉鏡花『高野聖』
この陀羅尼品を簡単に解せば、「法華経は大変尊いお経であるから、布教を妨害する人は痛い目見るよ」という意味です。
ですが、『高野聖』においてこのお経自体の意味はあまり重要ではありません。
なぜなら陀羅尼品は、お経を読むことによって無心になるために唱えられるものだからです。
また、陀羅尼品には、「これを唱えるものを守る」という効果があるとされるお経です。
そのため、恐怖に包まれた宋朝は自己を守るために無心でこのお経を唱えたということになります。
とはいえ、泉鏡花があえて陀羅尼品全文を載せた理由は見過ごせません。
『高野聖』は「語り」という性質が強い作品です。
なので、作品を声に出して読んだときに、「夜の独家」で唱えられるお経は臨場感を一層強めます。
このような音読による効果を泉鏡花は狙っていたと考えられます。
また、仏画というモチーフとの調和を図るためにも、お経が効果的に作用していると考えられます。
-感想-
・「水」でつながる二つの場面
宋朝は女に惑わされて動物になることなく、元の姿を保つことができました。
しかし、彼が魔性の手を逃れられたのは偶然なのでしょうか?
実は、宋朝が女を回避できるであろうことは、物語の序盤から伏線が張られています。
宋朝と茶屋の女との間に、このようなやりとりが交わされます。
「もし、姉さん。この水はこりゃ井戸のでござりますか」
「いんね、川のでございます。」
「山したの方には大分流行病がございますが、この水は何から、辻の方から流れて来るのではありませんか。」泉鏡花『高野聖』
宋朝は病にかかることを気にして、新鮮な水かどうかを確かめています。
ちなみにこの「流行病」とは、明治時代に幾度か流行した「コレラウイルス」のことです。
からからに乾いていた彼の喉ですが、そうした用心深さが原因となって、結局水を飲むことはありませんでした。
なぜなら、そこに居合わせた薬売りが、「坊主なのに命が欲しくて水が飲めないのか。もし腹を壊したら俺の薬を売ってやろう」と笑いながら茶化したからです。
真っ赤になった宋朝は、そのまま何も言わずすたすたと先を歩いて行きます。
つまりここでは、「水を飲む」という欲望が他者の妨害によって遮られ、結果的に欲望を達せない宋朝が描かれているのです。
こうした図式は、後の「女との水浴びの場面」でも同じ構成でみられます。
女と水浴びをしているとき、二人は少し良い雰囲気になりますが、蝙蝠と猿が現れることで、女が怒って雰囲気は流れます。
これは、宋朝の性的な欲望が、蝙蝠と猿という他者の妨害によって満たされなかったという図式です。
つまり、「水」というものを共通項に、二つの場面はつながっていることが分かります。
・物語の奥にある「大滝」
『高野聖』の背景にはいつも「滝」があります。
この水は源が滝でございます。(中略)あの森から三里ばかり傍道へ入りました処に大滝があるのでございます、それはそれは日本一だそうですが、路が嶮しゅうござんすので、十人に一人参ったものはございません。その滝が荒れましたと申しまして、ちょうど今から十三年前、恐しい洪水がございました
泉鏡花『高野聖』
この大滝は、ときに洪水を起こして村を流す凶暴性をもちながら、宋朝が女と浴びた川の水でも分かるように、旅人の傷を癒やすせせらぎにもなります。
また女が言うには、主人公が物語の中盤で聞いた山の中の「大風のような音」は、この大滝が落ちる音のようです。
それから、物語のラストで宋朝が眺める夫婦滝も、大滝からの流れでできた滝です。
もっと言えば、序盤に出てくる茶屋の「水」も、この大滝を源流とした川の水である可能性が十分にあるでしょう。
このように「大滝」は物語の背景に常に存在していますが、「十人に一人参ったものはございません」とあるように、その姿を確認することはできません。
つまり、「大滝」は確かに存在しながらも、誰も到達することがない異境の地にあり、物語の中でぼんやりと浮かんでいます。
こうした「大滝」の描き方も、『高野聖』の幻想性を高めている一因ではないかと思います。
・ラストシーンをどう読むか?
宋朝は、「女の独家」という魔境へ行って帰ってきた、「成長する」人物として描かれます。
このような物語の構成は「行きて帰りし物語り」と呼ばれ、多くの話がこの構成によって作られています。
たとえば、鬼ヶ島に行って帰ってくる『桃太郞』、竜宮城へ行って帰ってくる『浦島太郎』など、挙げていけばキリがありません。
もちろん現代の作品でもこの構成は使われています。ジブリアニメ『千と千尋の物語』などもそうですね。千尋の家族が神々のいる異境へ行き、千尋は成長し、最後は無事に帰ってきます。
話を『高野聖』にもどすと、宋朝は旅僧として魔境へ行き、生還することで、僧侶としてひとつ上の次元へと辿り着いたはずです。
しかし『高野聖』が面白いのは、そのような宋朝の成長譚がメインなのではなく、その話を「私」が聞いているという構成にあります。
「私」はラストシーンで、別れ行く宋朝の背中を見て次のように思います。
ちらちらと雪の降るなかを次第に高く坂道を上る聖の姿、あたかも雲に駕して行くように見えたのである。
泉鏡花『高野聖』
話を聞き終えた「私」は宋朝の背中に仏性を見出していますが、それは「飛騨山脈」での出来事を超えて、その後絶え間なく修行を重ねている宋朝に対する畏敬の念からです。
とはいえ、「私」が心の底から敬服しているとは思いません。
宋朝が聖人としての人生を選択しながらも、どこかで「独家の女」を忘れられずにいて、その煩悩とずっと向き合い続ける姿を、「私」は尊敬しながらも憐れんでいるように感じます。
以上、『高野聖』のあらすじと考察と感想でした。
この記事で紹介した本