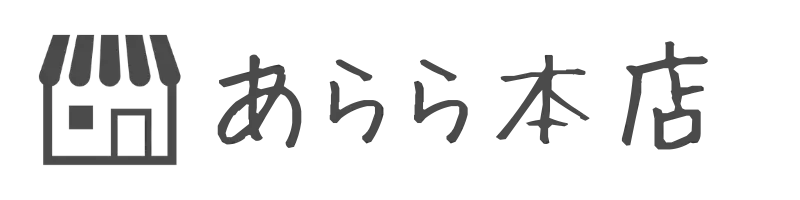『アラーの神にもいわれはない』のあらすじ・内容
主人公は、コートジボワールの西部地域に生まれた、10歳~12歳(確かな年齢は不詳)の少年ビライマ。幼くして両親を亡くした彼は、リベリアにいるらしい叔母のマーサを探す旅へ出ます。
旅のおともはヤクバという呪術師の男。2人は内戦の銃声が鳴り止まない1994年の西アフリカを渡り歩き、ビライマは少年兵として、ヤクバは呪術師としてその場その場を生き抜きながら、叔母のマーサを探すのです。
コートジボワール、リベリア、シエラレオネと西への旅を続けるなか、2人はさまざまな武力勢力(NPFL、ULIMO、INPEL、RUF)に入り、そこでの血なまぐさい経験が描かれることで、リベリア・シエラレオネの内戦の様子が浮かび上がる物語になっています。
主人公のビライマや、行く先々で出会う少年少女兵たちの人生を通して、西アフリカ諸国の内戦の実情や政権問題が描かれる小説です。
・『アラーの神にもいわれはない』の概要
| 物語の中心人物 | ビライマ(10~12歳の少年) |
| 物語の 仕掛け人 |
ヤクバ |
| 主な舞台 | コートジボワール→リベリア→シエラレオネ |
| 時代背景 | 1993年~1996年(リベリア第一次内戦) |
| 作者 | アマドゥ・クルマ |
『アラーの神にもいわれはない』を読んで分かること
- 1990年代リベリア・シエラレオネの内戦
- 少年兵の実情
・物語のキーワード
少年兵・親無し・内戦・政変・武力勢力・ハシシュ・カラシニコフ・キリスト教・イスラム教・略奪・コートジボワール・リベリア・シエラレオネ
『アラーの神にもいわれはない』の登場人物
○ビライマ
10歳~12歳の少年主人公。コートジボワール生まれ。マリンケ族。叔母を探しながら少年兵として生きる。
○ヤクバ
ビライマと同郷の呪術師。ビライマとともに旅をする。
○マ
ビライマの母親。両足が不自由。ビライマが子どもの頃に亡くなる。
○マーサ
ビライマの叔母。彼女を探すためにビライマは旅に出る。
○セクー
ヤクバの友人。マーサの行方を知っている。
○善人パパ
ビライマが最初に与するゲリラ軍「NPFL(リベリア国民愛国戦線)」の指揮官。
○オニカ
ビライマが二番目に与する組織「ULIMO(リベリア民主統一解放戦線)」の指揮官。
○プリンス・ジョンソン
ビライマが三番目に与する組織「INPFL( リベリア独立国民愛国戦線)」の指導者。
○チエフィ将軍
ビライマが4番目に与する組織「RUF(革命統一戦線)」の将軍。
『アラーの神にもいわれはない』の武力組織
○NPFL(リベリア国民愛国戦線)
チャールズ・テイラー(1948 - 。リベリア共和国第22代大統領)が結成した武力組織。
○ULIMO(リベリア民主統一解放戦線)
サミュエル・ドウ(1951年 - 1990年。リベリア共和国第21代大統領)の派閥が、ドウ亡き後に結成した武力組織。NPFLと対立関係。
○INPFL( リベリア独立国民愛国戦線)
NPFLから離脱したプリンス・ジョンソン(1952年- )が結成した武力組織。サミュエル・ドウを殺害する。
○RUF(革命統一戦線)
フォディ・サンコー(1937年 - 2003年)が結成したシエラレオネの武力組織。NPFLのチャールズ・テイラーと結託。
○ECOMOG(西アフリカ諸国経済共同体監視団)
ナイジェリア軍を軸とした戦争調停団体。主人公のビライマからは「戦争の調停をしない調停団体」と揶揄されている。
『アラーの神にもいわれはない』の感想
・アフリカ内戦の実情が分かる
アフリカの内戦って、「○○族と○○族の確執が~」とか「○○派のクーデターが~」というふうに報道されることが多くて、アフリカ諸国の内部で対立構造があるように思われがちだけど、実はそうじゃないんだということが書かれてありました。
1990年代に起こったリベリアの第一次内戦は、たしかに表面上は「クラン族(政権側)VSギオ族・マノ族(クーデター側)」と見ることもできるのですが、実際に彼らが兵士として集めたのは民族も多様な人たちで、なかには主人公のような少年もいるんですね。
集められた人たちは「生きるため」に兵士をやっている人が多くて、要するに武装集団に属していたら、ご飯が食べられるから銃を手にしているわけです。僕らがバイトをしたり、仕事に就いたりしてお金を稼ぐのと、なんら変わりはないんですね。それくらい「子ども兵」や「武装集団」が常識化していた現状が、手に取るように分かりやすく、リアルに描かれていました。
・「凄惨さ」はあまりない
『アラーの神にいわれはない』は、「子ども兵の人生が描かれる凄惨な小説」という説明がされていますが、実際に読んでみると、凄惨さを煽るような本ではないと感じました。語り手のくだけた口語調で、事実が淡々と述べられていく形です(もちろんその事実自体が悲惨なものではあるのですが)。
「死」が当たり前の世界になっているから、当たり前のこととして書かれる、ただそれだけ。という感じのある小説でした。
・イスラムの影は薄い
タイトルが『アラーの神にいわれはない』だったので、内容にイスラムが深く関係しているのかな?と思っていましたが、そんなことはありませんでした。
主人公がなにかにつけて、「アラーの神にもいわれはないんだもんね」といったことを言うので、物語に効果的なリフレインを生んでいて、それがそのままタイトルになっています。
この「アラーの神にもいわれはないんだもんね」というのは非難を含む言い方で、「アラーの神さまだって全員を平等にする義務なんてないんだもんね。だから女の子が暴行されて殺されたり、男の子が爆弾で吹っ飛んだりしても、別にアラーの神さまのせいじゃないんだもんね。」という主旨になっています。
物語の中で悲しいことが起こるたびに、この一文が繰り返されることで、次第に神に対する非難の色が強くなっていき、冒涜的な様相を帯びていく仕掛けになっています。このリフレインは本作でも面白いポイントのひとつでした。
・戦争と向き合いたくない子どもたち
少年兵たちが戦場で怖じ気づかないよう、大麻を吸ってから出陣したり、呪術師が「敵の弾が水に変わるまじないをかけた」と言って、子どもたちの恐怖を和らげたりしていたところも印象的でした。
この「敵の弾が水に変わる」というのは、かつてローデシア(現ジンバブエ)が19世紀末に植民地化されかけたとき、土地の伝統的予言者である「スビキロ」と呼ばれるひとたちが、「神(ムワリ:ショナ人の信じていた最高神)が白人の銃弾を無害な水に変えてくれる。死を恐れず戦え。」と呼びかけているものと同じです。このことから、アフリカの信仰では伝統的な考え方なのかもしれません。
いずれにせよ子どもたちは、大麻で頭をおかしくしたり、まじないを信じたりすることで、戦場の恐怖を直視しないようにしていることが分かります。主人公の語り口調もふざけた感じなのですが、そこには、紛争とは真正面から向き合いたくない、どうにかして目を逸らしたいという思いが反映されているのかもしれません。しかし、紛争は彼らの生活の一部になっていることから、100%目をそむけることはできないんですね。そうした状況が、紛争を斜めから見る、ふざけた口調の主人公を生んだように思います。はじめは違和感のあった口語調の文章でしたが、読んでいくうちに、そうせざるを得なかった主人公の人生を考えさせられた、そんな一冊でした。
この記事で紹介した本