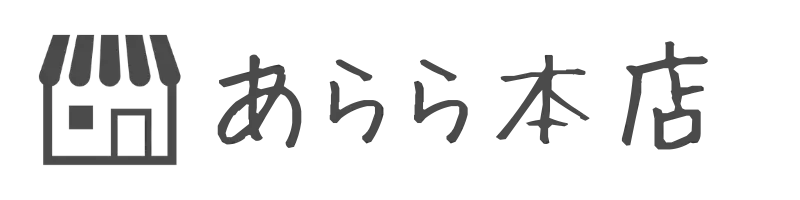『文字禍』とは?
『文字禍』は中島敦が初期に書いた作品です。
有名な『山月記』を含む、中島敦の「古潭四篇」のうちの一つとして数えられます。
○中島敦の古潭四篇○
- 『狐憑』
- 『木乃伊』
- 『山月記』
- 『文字禍』
『文字禍』は、アッシリア帝国時代を背景に、老博士と文字の精霊の物語が描かれています。
ここではそんな『文字禍』のあらすじ・考察・感想までをまとめました。
-あらすじ-
アッシュールバニパル大王がアッシリア王国を統治していた時代の話。
ナブ・アヘ・エリバという老博士は、文字の精霊についての研究を命じられた。
研究が進むと、文字の精霊は人を操り、禍(わざわい)をもたらしていることが分かった。
「武の国アッシリヤは、今や、見えざる文字の精霊のために、全く蝕まれてしまった。」
老博士がこのことを報告すると、知恵の神を崇拝していた王は怒り、老博士に謹慎処分を下した。
老博士は、この結果は文字の霊の復讐であると考え、その恐ろしさを痛感した。
けれども、文字の精霊の復讐はこれだけでは終わらなかった。
数日後、博士が書庫にいるときに大地震が起き、彼は無残にも書物に埋もれて圧死したのである。
・『文字禍』の概要
| 主人公 | ナブ・アヘ・エリバ |
| 物語の 仕掛け人 |
文字の精霊 |
| 主な舞台 | 新アッシリア帝国 |
| 時代背景 | 紀元前6世紀 |
| 作者 | 中島敦 |
-解説(考察)-
・文字の精霊とはなにか
『文字禍』にでてくるキーワードは、
- 文字の精霊
という言葉です。
これは、文字に宿る魂のことを言い、すなわち、
を表します。
単なるバラバラの線に、一定の音と一定の意味とを有たせるものは、何か? ここまで思い到った時、老博士は躊躇なく、文字の霊の存在を認めた。
ナブ・アヘ・エリバ博士は、この「文字に意味を持たせるもの」について研究しています。
そして博士が研究を進めるうちに出てきた疑問はこのようなものです。
これはつまり、物事の本質ではなく、文字を通した概念に支配されてしまうのではないかという危惧を表しています。
たとえば、芸人の松本人志が生み出した
- 空気を読む
という言葉があります。
この言葉が生まれる以前は、人々はコミュニケーション上の雰囲気を敏感に察知し、いわば本能で「空気を読んで」いました。
しかし、この言葉が生まれたことで、人々は「空気を読む」という概念で空気を読むようにりました。
文字の無かった昔、ピル・ナピシュチムの洪水以前には、歓びも智慧もみんな直接に人間の中にはいって来た。今は、文字の薄被をかぶった歓びの影と智慧の影としか、我々は知らない。
人間は文字を操る側であるはずなのに、逆に文字の概念を追いかけ、むしろ支配されてしまう。
そうした「言葉・文字」の持つ怖さが、文字の精霊を通して『文字禍』では描かれています。
・アッシリアって何?『文字禍』の時代背景
『文字禍』の物語は、
を背景にして進んでいきます。
アッシリアは現在のイラクあたりで興った古代王国です。
作中に出てくる、
- アシュル・バニ・アパル(アッシュールバニパル)大王
は実在していた人物で、彼が在位の頃にアッシリア王国は最盛期を迎えます。
アシュル・バニ・アパル大王は書物の収集癖があり、現在でも有名な「アッシュールバニパルの図書館」を建設した人物でもあります。
しかし、そんなアシュル・バニ・アパル大王が死ぬと、その次の代でアッシリアは滅亡します。
つまり、『文字禍』は滅亡に向かうアッシリア王国時代を背景に描いている作品なのです。
そうしてみると、主人公であるナブ・アヘ・エリバ博士が報告した王への進言は的確だったことが分かります。
武の国アッシリヤは、今や、見えざる文字の精霊のために、全く蝕まれてしまった。しかも、これに気付いている者はほとんど無い。今にして文字への盲目的崇拝を改めずんば、後に臍を噛むとも及ばぬであろう云々。
このように『文字禍』では、武の国アッシリアが「文字の禍い」によって滅びるという構図を取っています。
そうした時代背景が分かると、『文字禍』は主人公である博士の個人的な不幸の話ではなくなり、より大きな枠組みの話へと拡大されます。
アッシリアについて詳しく知る必要はないですが、こうした予備知識があれば作品理解の助けになるかもしれません。
-感想-
リル、リリツ、ナムタル、エティンム、ラバス、アッシリヤ、アシュル・バニ・アパル、ニネヴェ、シャマシュ・シュム・ウキン、バビロン。
『文字禍』を読むと、まずはじめに見慣れないカタカナの羅列に面食らいます。
ああ、これはアッシリア王国時代の話かと理解するまでに、僕なんかは少しの時間を要しました。
それから少しずつ、『文字禍』の世界に入っていきます。
当時の書物が粘土板だったせいで、物語には砂っぽいイメージがつきまとっています。
ゲシュタルト崩壊を起こすまで研究に没頭するナブ・アヘ・エリバ博士は巨眼で縮髪。
ほかの登場人物は、せむしで書物狂の老人に、面倒な若い歴史家、ご立腹の王様。
この物語には「イケてる」奴も出てこないし、豪華絢爛な都の様子も描かれません。
要するにみんな滅びを待っている、乾いた存在です。
古代スメリヤ人が馬という獣を知らなんだのも、彼等の間に馬という字が無かったからじゃ。
ナブ・アヘ・エリバ博士は一時、文字の精霊を賛美します。
夏目漱石が「肩が凝る」という言葉を生み出した瞬間から、日本人は肩こりという症状に悩まされることになり、
伊集院光が「中二病」という言葉を生み出した瞬間から、中二病になる人が生まれるようになります。
文字ってすごいよね。文字最高。それで終わっていればよかったのです。
けれども博士はもう一歩踏み込みます。
彼の大きな眼を通して、文字と人間の関係が描かれる物語です。
以上、『文字禍』のあらすじと考察と感想でした。
この記事で紹介した本