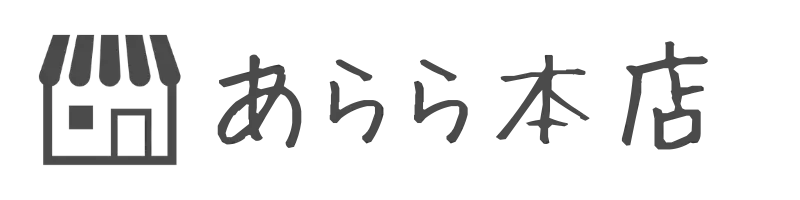『照葉狂言』とは?
『照葉狂言』は、母を亡くした主人公・貢が、一人の男として生きていくまでを描いた泉鏡花の作品です。
清楚で不幸な姉、姉にきつく当たる継母、流れ者の小親(こちか)など、様々な女性を通して、主人公の内面が浮かび上げられます。
ここではそんな『照葉狂言』のあらすじ・解説・感想をまとめました。
『照葉狂言』のあらすじ
主人公の貢(みつぎ)は、まだ幼い美少年。
優しい姉が一人いるが、母は亡くなっている。
だから、貢は伯母さんに育てられ、姉は父の再婚相手である継母に育てられていた。
どこの継母も大半がそうであるように、姉もまた継母につらく当たられており、貢はそのことを日夜悲しんでいる。
そんな彼は、人から聞くお話や能などの見世物が好きで、町に来ていた見世物屋には毎日通うほどだった。
見世物屋の人たちは、誰よりも熱心に舞台を見てくれる貢を得意客だと言ってもてなし、その中の小親(こちか)という娘は特に貢を可愛がった。
ある日、いつものように見世物屋へ行ったが、その帰りに国麿というガキ大将と一悶着があったので、家に着くのが遅くなった。
貢が家に着くと、伯母さんが賭けカルタをして、警察に捕まっていた。
その日から貢は小親に引き取られ、見世物役者の芸人として地方を転々として生きていくことになる。
それから8年後、貢は見世物役者として、再び故郷に帰ってきた。
彼は慕っていた姉のお雪が気になりつつも、すぐに会いに行くことも出来ない。
偶然継母に出会ったのは、貢と一行がこの地に着いて20日が経った後だった。
継母は、町に起きた洪水のことや、夫を貰ったお雪のことなどを貢に話した。
お雪の夫は気性が荒く、妻のお雪に対する仕打ちは、あの継母でさえも心が痛くなるほどだという。
そんなお雪の夫は小親のことを綺麗だと言っているようで、貢や継母は色仕掛けでお雪を救えるかもしれないと考える。
ただし、お雪は助かるかもしれないが、小親を犠牲にしなければならない。
一方で、小親とこのまま生きていけば、姉のお雪を見捨てることになる。
どちらを取ることもできない貢は、小親のもとをそっと抜けだし、夜の道を山へ向かって歩き出した。
山に着くと、謡を唄う4,5人の人がいた。
その妙なる歌声を聞いた貢は、自分一人で生きていこうと決心し、山を越えていこうと道を定めた。
・『照葉狂言』の概要
| 主人公 | 貢(みつぎ) |
| 物語の 仕掛け人 |
お雪、小親(こちか) |
| 主な舞台 | 金沢 |
| 時代背景 | 明治時代 |
| 作者 | 泉鏡花 |
-解説(考察)-
・『照葉狂言』の構成
『照葉狂言』は、
- 鞠唄
- 仙冠者
- 野衾
- 狂言
- 夜の辻
- 仮小屋
- 井筒
- 重井筒
- 峰の堂
という9つの章から構成されており、1~5章までが少年時代、6章~9章までが青年時代の話になっています。
それぞれの章は、付けられたタイトルを象徴する出来事が描かれ、映像的に分かりやすい舞台設定になっています。
ちなみに、7章の「井筒」は世阿弥の能、8章の「重井筒」は近松の浄瑠璃が踏まえられているのではないかと考えられます。
「少年→青年」と進む作品の構成からも分かる通り、『照葉狂言』は主人公・貢の成長を描いた物語です。
そして、この主人公の成長をあらゆる表現手段で描いているところが、『照葉狂言』の素晴らしい点だといえます。
たとえば、
- お雪と小親の二人の女性
- 能の演目『松風』の内容
- 楓と松の木
- 月と一番星
などの描写によって、主人公の成長が描かれています。
次からは、そういった主人公・貢の成長が具体的にどのように描かれているのかを見ていきます。
・二人の女性と貢の成長
『照葉狂言』では、二人の女性が重要な役割を担っています。
主人公の貢はお母さんを亡くしているため、優しい姉に母性を見出し、幼心にある淋しさを埋め合わせています。
また、見世物屋の小親は、貢を可愛がってくれる頼れるお姉さんです。
物語の前半では、貢はお雪と小親の二人に可愛がられながら生き、守られる立場にあります。
そんな貢に変化が訪れるのは物語の後半、彼が青年になってからです。
6章の「仮小屋」で、貢は姉が夫に苛められていることを知ります。
彼は一度、小親に頼るのですが、そうすれば小親を売ってしまうことになります。
とはいえ、姉を見捨てて自分だけ小親と生きていくことなどできません。
ここで貢は、自分の非力さを痛感します。
無意識に姉の優しさに甘え、小親を頼りにしていたことに気が付くのです。
悩んだ末に彼が出した答えは、自分一人で生きていくという選択でした。
今の自分に姉を助けることはできないし、いつまでも小親を頼ることもできない。
そう考えた彼は山を越えていこうと思い、一人で峰を上っていきます。
このように、二人の女性から守られる立場を抜け出し、一人の男として生きていこうとする貢の姿を描くことで、『照葉狂言』は少年の成長譚となっているのです。
ただ、貢が一人で生きていく決断をした理由はそれだけではありません。
次には、終章の「峰の堂」で語られる、彼の決断のもう一つの理由を見ていきます。
・『松風』と貢の成長
『照葉狂言』の終章「峰の堂」で描かれるのが、『松風』を唄う4,5人の人々です。
やや落着く時、耳のなかにものの聞ゆるが、しばし止みたるに、頭上なる峰の方にて清き謡の声聞えたり。
松風なりき。
あまり妙なるに、いぶかしさは忘れたるが、また思い惑いぬ。ひそかに見ばや、小親を置きて世に誰かまたこの音の調をなし得るものぞ。泉鏡花『照葉狂言』
『松風』とは、世阿弥の能の作品のひとつです。
貢はこの『松風』を唄う彼らのきれいな声を聞いて、小親以外にこんなにも上手に唄える人がいるのかと思います。
小親の唄いを最上だと思っていた貢が、小親と同じくらい上手な唄いを聞くことで、世界は広いということを知る場面です。
この歌声を聞いて、彼は「山を越えていこう」と決心します。
そして大きくなってから、姉や小親の元へ帰ってこようという心づもりなのです。
そう考えられる根拠は、『松風』という作品の内容にあります。
『松風』は在原業平という一人の男に、松風と村雨という二人の姉妹が恋をする話です。
この構成が、貢を慕うお雪と小親の三人を表しているのは言うまでもありません。
『松風』では二人の恋は叶わず、彼女たちの霊は在原業平との思い出を語って狂おしく舞います。
この舞台中に、在原業平が詠むこんな歌があります。
立ち別れ いなばの山の 峰に生ふる 待つとし聞かば いま帰り来ん
(お別れして、因幡の国へ行く私ですが、因幡山の峰に生えている松の木のように、私の帰りを待つと聞いたなら、今すぐにでも戻ってきましょう。)在原業平
百人一首にもなっている有名な歌ですが、この「峰の松」という描写は、『照葉狂言』のラスト「峰の堂」で描かれる松の場面とも重なります。
そして、松の下で唄われていたのが、一人の男を慕う姉妹の話である『松風』です。
つまり、『松風』と『照葉狂言』の「峰の堂」の場面は完全にリンクしていることが分かります。
だとすれば、貢の心境が在原業平の心境と重ねられていたとしても不思議ではありません。
このようなことから、貢はラストのシーンで一人旅立つことを決意しながらも、いつかまた帰ってこようと思っているのではないかと考えられます。
見てきたように、小親以外に存在した歌の上手な人や、世阿弥の『松風』という作品も、主人公の成長を描いている仕掛けになっているといえるでしょう。
・物語の楓と松
『照葉狂言』では、楓と松が対照的に、そして象徴的に配置されています。
楓は主人公の家の横に植わっている木で、姉と主人公との思い出の木でもあり、また後には姉の住む広岡の家を洪水で流してしまう原因にもなる木です。
一方で、峰の松は物語の最初と最後に出てくる木で、主人公の芸事への関心を象徴しており、ひいては小親を表しています。
物語の前半は楓の描写が多く、後半は松の描写が多くなります。
以下は2章の楓と松の描写です。
山は近く、二階なる東の窓に、かの木戸の際なる青楓の繁りたるに蔽われて、峰の松のみ見えたり。
泉鏡花『照葉狂言』
少年時代の貢にとって、姉は世界のほとんどを占める存在です。
そのため、ここでは楓(姉)の陰に松(芸事)が隠れているという表現になっています。
しかし、物語の後半になると、楓は流されしまい、貢は松にどんどん引き寄せられていきます。
楓が流されたのは、姉が嫁に貰われてしまったことを、貢が松に引き寄せられるのは、彼が芸事に関心が強まっていることを表していると考えられます。
ただし物語の終章では、貢は楓を見過ごして、松を通り過ぎ、山を越えていこうとしています。
つまり、姉を見過ごして、小親の元から抜け出し、新たな道を歩む貢の姿が描かれるのです。
こうした楓と松の描写からも、彼が二人の女性から決別し、成長していくが物語の構成が読み取れるでしょう。
・月と一番星
見てきたように、楓と松は対照的に描かれている木です。
しかし、これらの木の描写には共通点があります。
それは、木の後ろに「月」がかかっているということです。
月は『照葉狂言』のなかで19回も描かれており、中編小説としてはかなり多いといえます。
そのなかで、楓の木に月がかかっているのは6章の場面です。
手を放すより、二三間駈出して、われはまず青楓の扇の地紙開きたるよう、月を蔽いて広がりたる枝の下に彳みつ。
泉鏡花『照葉狂言』
一方、松の木には9章の場面で月がかかっています。
月は峰の松の後になりぬ。
泉鏡花『照葉狂言』
また、この後にも松の背景に月があることが重ねて書かれています。
月は古くから「母性」を表す象徴として描かれてきました。
そのため、楓と松にかかる月は、主人公がお雪と小親という二人の女性の中に、母性を見出しているということを表していると考えられます。
とはいえ、月は小親の顔を照らしたり、木の後ろに隠れているばかりで、前面に出てくる様子はありません。
あくまでもぼんやりとした存在として、背景にいるばかりです。
そんな月とは対照的なのが、物語のラストに出てくる一番星です。
と見れば明星、松の枝長くさす、北の天にきらめきて、またたき、またたき、またたきたる後
泉鏡花『照葉狂言』
明星とは一般的に金星のことを指しますが、金星は北の空には見えないので、ここでは一番星だと考えられます。
一人で山を越えていこうと決意した主人公の頭上にあるのは、月ではなく一番星です。
こうした描写からは、彼は姉や小親だけでなく、亡き母への思慕からも自立したことが読み取れます。
彼の頭上にきらめく星は、彼自身の新たな決意の炎なのかもしれません。
・タイトルの『照葉狂言』とは何か?
最後の解説では、本作のタイトルについてお話しします。
タイトルの照葉狂言とは、江戸末期から明治中期にかけて流行した寄席演芸のことです。
能や狂言といった伝統芸能に、歌舞伎・寸劇・俗謡などを取り入れた見世物で、演者が女性であることが特徴になっています。
同じように、泉鏡花の『照葉狂言』でも、女性が登場人物のほとんどを占めています。
具体的には、見世物屋の「小親」や主人公の姉である「お雪」、亡くなった「母親」に、育ての親である「伯母」や「継母」といった女性たちが中心となって物語を進めていきます。
また、
- 鞠歌(下谷一番)
- 俗謡(源がばばさん焼き餅好きで)
- 民話(お銀小金)
- 能(松風)
など、照葉狂言と同じように色々な大衆文化が作中に取り入れられています。
このようなことから、『照葉狂言』自体が照葉狂言的な約束事に沿って書かれた作品だといえるでしょう。
ちなみにお銀小銀は石川県の民話です。面白いので、気になった人はぜひ調べてみて下さい。
-感想-
・お雪の死亡説
『照葉狂言』で気になったのが、7章で聞こえた「あれっ」という姉の声です。
貢と小親はその声をたしかに聞きましたが、なぜか確認しようとはしませんでした。
ただ、小親は「貢とお雪が獣に追いかけられて井戸に落ちた夢を見た」と怖ろしいことを言うばかりです。
また、7章の副題になっている「井筒」は井戸のへりという意味ですが、実は世阿弥の能に『井筒』という作品があります。
『井筒』は帰らぬ夫を待ち続ける妻の話で、その姿は弟の帰りを待つお雪とも重なります。
『井筒』が世阿弥の作品と重ねられているのであれば、8章の『重井筒』というタイトルも、近松門左衛門の浄瑠璃『心中重井筒』が踏まえられているかもしれません。
『心中重井筒』は、浮気相手と心中しようとする男が、最後には井戸にはまって命尽きる話です。
どちらも悲しい話であり、姉の状況が良くなりそうなものとは思えません。
それに加えて、「あれっ」と聞こえたときには、猫が鳩をくわえて通っていきました。
猫は物語の前半、主人公の伯母が警察に捕まる場面でも登場しており、悪いことが起きる予兆としての役目でした。
だとすると、仮小屋の横を猫が通ったことも、何か悪いことが起こる前触れと考えてよさそうです。
さらに、猫は血まみれの鳩を咥えています。
このようなことをまとめると、お雪が死んだという直接的な表現はありませんが、ともかく死を連想させる雰囲気がこの場面では強く漂っていることが分かります。
個人的には、お雪は井戸に落ちて死んでしまったのではないかと考えていますが、皆さんはどう思うでしょうか。
以上、『照葉狂言』のあらすじと考察と感想でした。
この記事で紹介した本