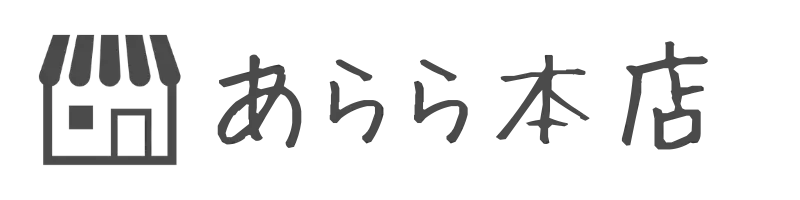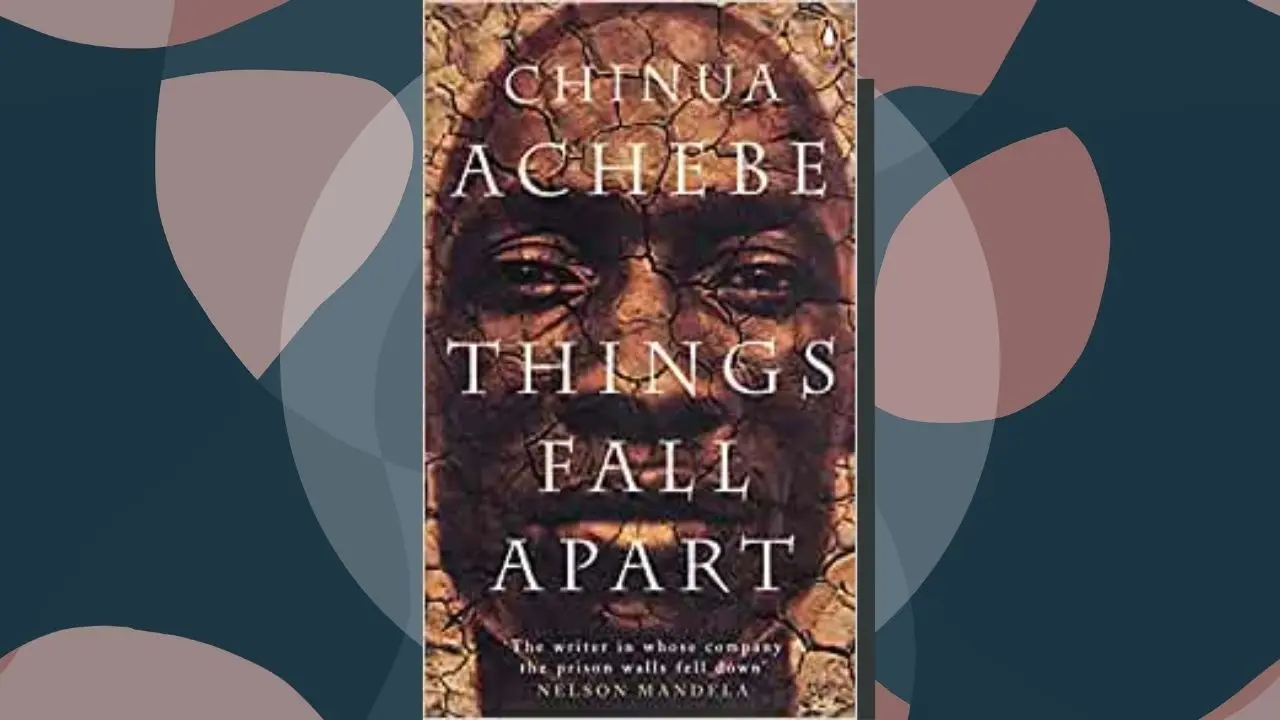『崩れゆく絆』のあらすじ・内容
舞台は19世紀後半のナイジェリア東部地域。作中では「ウムオフィア」という架空の地名が付けられています。
ウムオフィアは9つの集落からなる共同体で、そこでは古くから伝わる儀礼や、宗教、文化があり、長老から長老へと引き継がれてきた掟を守りながら民族が暮らしていました。
主人公のオコンクウォは、その集落の一つで生まれます。父親が怠け者だったため一家は貧しく、オコンクウォはそんな父親を恥ずかしく思っていました。というのも、村では立派な人物に称号を与える制度があり、称号が多ければ多いほど人から尊敬を集められるのですが、オコンクウォの父は、ひとつの称号も持っていなかったのです。そして、借金だけを残して彼は死にました。
オコンクウォは必ず尊敬を集める人物になると決意し、大人になるころには、その通り立派な人物となりました。彼は9つの集落で一番のレスラーという名声を得て、広い畑を持った裕福な農民となり、三人の妻を持ち、まだ若いというのに、すでにふたつの称号を手にしていました。村同士の戦争では誰よりも武勇を上げ、勇敢な戦士としてその名を轟かせました。
順調に進んでいた彼の人生ですが、あるとき長老の孫を誤殺してしまい、村の掟により7年の追放を言い渡されます。ここから彼の人生が転落していくのですが、それとほぼ同じころ、ウムオフィアには白人の影が忍び寄っていました。9つのうち1つの集落を、やって来た白人が滅ぼしたのです。
白人たちは残る集落にキリスト教を持ち込み、「お前たちが崇めているのはただの木切れや石ころだ」と言い、村人たちに改宗を迫りました。また拠点として、村に教会を建てたいと申し出ました。
白人を初めて見る村の人々は、気の狂った人間が来たと思い相手にしていませんでしたが、村からは出ていってほしいので、白人に「悪霊の森」であれば教会を建てても良いと言いました。悪霊の森とは、強い呪いの力があると信じられている場所で、そこに教会などを建てると、白人たちは間違いなく呪われて勝手に死ぬだろうと考えたのです。しかし、教会が建って何日、何週間が経っても、白人たちは死にませんでした。そのころから、ちらほらと、キリスト教に入信する者が出始め、一族は徐々に分裂していきます。
古くからの価値観を守りながら生きてきた民族が、西洋の文化や価値観に侵略されていく様子が描かれる、現代アフリカ文学の原点といわれる小説です。
・『崩れゆく絆』の概要
| 物語の中心人物 | オコンクォ |
| 物語の 仕掛け人 |
白人宣教師 |
| 主な舞台 | ウムオフィア(ナイジェリア東部のイボ族の集落) |
| 時代背景 | 1900年前後 |
| 作者 | チヌア・アチェベ |
『崩れゆく絆』を読んで分かること
- イボ族の信仰や文化と民族受難
・物語のキーワード
イボ族・宗教・精霊思想・呪術・偉人・集落・白人・侵略・改宗・キリスト教・チ(守り神)
『崩れゆく絆』の感想
「アフリカ文学の父」に納得
『崩れゆく絆』を手に取ったのは、アフリカ文学を読み始めた最初のころ。にも関わらず、それまでに読んだ数冊の物語のなかにはすでに『崩れゆく絆』への言及があって(『アメリカーナ』『ぼくらが漁師だったころ』など)、それだけ後世に大きな影響を与えているんだなという印象を持って、大きな期待とともに読みました。
読んでみると、アチェベが「アフリカ文学の父」と言われる理由が分かります。なぜなら『崩れゆく絆』で書かれてあることを、手を変え品を変えて、ほかの作家が再編成していると言ってもよいくらい、根本的な要素が詰まった作品だったから。
民族の文化、伝統、呪術、口承文学、それらが西洋文化に破壊される過程。揺らぐ信仰やアイデンティティ、共同体の崩壊。ゼロからの再スタート。こうしたことが、イボ族の戦士オコンクォの生涯を通して語られるのが本作で、ここに現代の問題を織り込むと現代アフリカ文学に。というのはさすがに大げさすぎるけど、それくらい近代アフリカの歴史を象徴した作品になっていると感じました。
覆された世界とオコンクォ
イボの集落では、力こそが至高であり、もっとも強い者がコミュニティのトップになれる仕組みでした。主人公のオコンクォは集落の長になるという目標を生きがいにしており、そのために何をおいても民族的な「男らしさ(必要とあらば子どもも殺す)」を優先し、金もため、集落の中では最も強いレスラーとなり、長への道を着々と歩んでいました。
しかし、白人が集落へやってきて侵略が始まると、これまで民族にあったシステムも崩壊していきます。男らしさは「野蛮」に変わり、呪術は「思い込み」に変わり、神さまは「木切れや石ころ」に変わるのです。こうした世界では、オコンクォの夢だった長という立場も、もはやかつての尊敬を集めるものではありません。民族の世界が覆されたのと同時に、オコンクォという個人もまた、土台から覆されるのです。
もう少し柔軟性があれば、新しい世界に順応していくことも出来たはずですが、なにせオコンクォは真面目なので(「男らしさ」のために感情を表に出さない。「男らしさ」のために人も殺す)、彼の最後の選択は必然的で、物語的には当然の結末です。そこを曲げられるのであれば、彼はイケメフナを殺さなかっただろうし、家族にもっと優しくしていたでしょう。だからこそ、民族の滅び(=オコンクォの滅び)が運命だったという構成の点において、この小説の物語の悲劇性が高まっているところに巧さを感じました。
妥協点を模索する人々――関連する小説について
現代ナイジェリア人口の17%はイボ人
こうした民族受難のもとでは、多くのイボ人がオコンクォと同じメンタリティだったと思いますが、それでも生きていかなければならないですよね。
いまのナイジェリア人口のうち約17%はイボ人で、『崩れゆく絆』で描かれた白人支配が起こったとき、「生きる」という選択をした人々の子孫です。このイボ族はいまでもイボ語(と場合に応じて英語)を話しており、イボの文化や信仰も受け継いでいます。
後世に引き継がれる「イボ」のテーマ
チママンダ・ンゴズィ・アディーチェは、現代のナイジェリアを代表するイボ人の作家です。彼女の短編『がんこな歴史家』や『ママ・ンクウの神様』では、イボ信仰の世界とキリスト教世界の妥協点を模索しながら生きる人々が描かれていて、『崩れゆく絆』の別視点といえる小説になっています。イボ人の文化や信仰を多角的に見ることができるので、『崩れゆく絆』が面白かったという人は、彼女の短編を読むと得るものが多いと思います。
また、イボ族は1967年に独立国家「ビアフラ共和国」を建国しますが、ナイジェリア連邦側に戦争で敗北して解体しています。このビアフラ戦争をテーマにした小説『半分のぼった黄色い太陽』も、イボの民族性や近代史を知るのにおすすめです。こちらはアディーチェの長編小説ですが、アチェベはこの本を読んで、彼女を次のように評しています。
古くから伝わるストーリーテラーとしての天賦の資質をそなえた新しい作家
チヌア・アチェベ
この記事で紹介した本