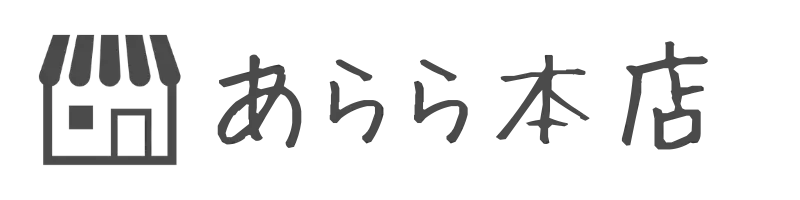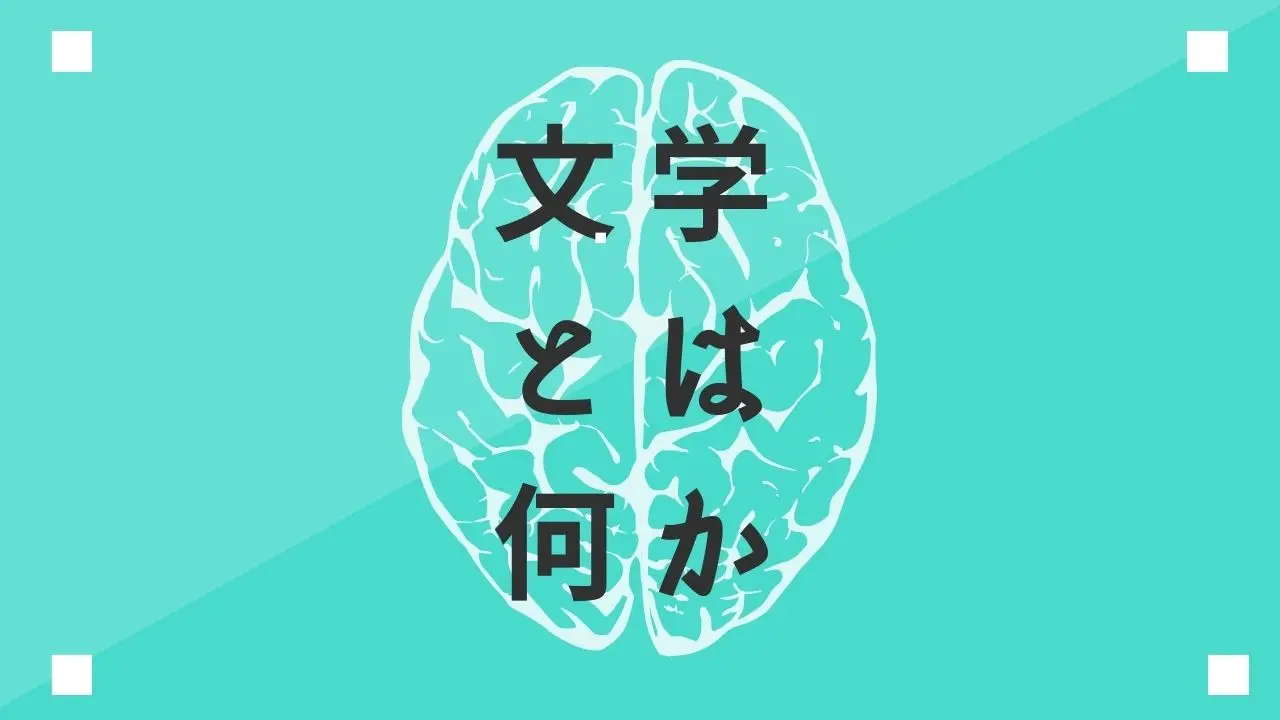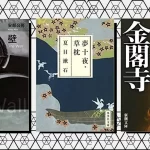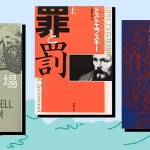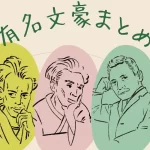「文学」って何?
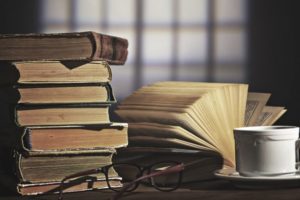
文学ってなんなんだろう、そう思ったことはありませんか?
僕はあります。
きっかけは、「純文学」と「大衆文学」の違いって何だろう?と思ったことです。
それから疑問は「そもそも文学ってなんなんだ?」という方向に向かいました。
ここではそんな僕が、
- 文学とは何か?
という大それた問いに一応の答えを出したので、ここに記しておきます。
まずは「文学とは何か」を調べた
僕がまず最初に目を通した資料はT.イーグルトンの『文学とは何か』でした。
この本に絶対答えが載ってある!
そう確信した僕は、すぐさまこの本を読みました。
彼は序論で以下のように語ります。
絶対不変の価値を保証された作品の集合体という意味の文学、ある内在的特性によって認知される文学というのは、存在しないのだ。本書の中で、「文学的」とか「文学」という言葉を私が用いるときには、その言葉の上に目に見えない×印を書きつけていることになる。その言葉がとりあえずのものでしかないこと、さしあたってこれにかわるよい言葉がみつからないことを示すために。
T.イーグルトン『文学とは何か ――現代批評理論への招待』,p17,岩波書店,1997
なんだか小難しいですが、要するに「文学」や「文学的」という言葉を定義することはできないということを言っています。
まだ序論なのに、いきなりのカウンターフックです。
イーグルトンの『文学とは何か』という本は、文学理論入門の良書としてよく知られています。
なので、ここに答えがあると期待していた僕は落ち込みました。
けれども僕はめげずに、参考文献として挙げられていたほかの文学理論書も読んでいきました。
しかし、「文学とはこういうものである」と定義したものを見つけることはついに叶いませんでした。(一方で「文学というのはこれこれの理由で定義できない」という定義できない理由は数多く目にしました。)
つまり、長い時間と膨大な書物の中で僕が知ったのは、
- 「文学とは何か」は定義することができない
ということでした。
僕の考える「文学」とは

結局、「文学」とはなんなのでしょう。
僕が読んだ書物の中に「文学とは何か」という定義はありませんでした。
しかしそれらの書物は、
- 「文学」をどう読むか、「文学」はどう書かれているか
ということを考える指針を僕に与えてくれました。
僕はその指針を拠り所に、「文学とは何か」を僕なりに考えることができたのです。
・僕なりの「文学」定義
「僕なりの」とは便利な言葉です。
この言葉を使えば、たとえどんな突拍子のない意見でも主張することができます。
そうした責任逃れの前置きをしつつ、誤解を恐れずに結論をまず言います。
僕は文学とは「体験」であると思います。
かっこよくするならこんな感じ。
文学とは体験である。
小助「あらら本店」,2019
これをより正確に言うなら、
- 文学という言葉の意味を支える一つの側面には、作者が紡ぐ言葉の連なりを認識する過程で起こる強烈な体験がある
となるかもしれません。
でもこういうと少しくどいから、僕は思い切って「文学とは体験だ」と言いたい(「芸術は爆発だ」みたいでかっこいいから)。
定義、それから。
ここまではもとより答えのないものに無理矢理答えを出す形で話を進めてきました。
ですが正直に言うと、僕は「文学とは何か」について調べているうちに、だんだんと「文学とは何か」なんてどうでもいいのではないかと思うようになりました。
文学とは体験だ。それも一つの見方ではあるでしょう。
しかし最も大事なのは、文学による体験がなぜ起こるのかを考えることだと思います。
もっといえば、言語にどのような形式が用いられ、どんな仕掛けがはたらいて、どのような効果によって読者に体験という影響を及ぼすのか。
それを考えなければいけません。
「文学」それ自体を暴くのではなく、文学作品をどう読むかを考えることによって、さまざまな方向から「文学」に光を差し、その照らし出されたものに目を向けることが大事なのかもしれません。
「文学とは何か」を考える上でおすすめの文学理論書3選!
「文学とは何か」という問いを考えるために、僕は文学理論書を20冊ほど読みました。
ここでは、その中でも特に、
- 面白く
- 分かりやすく
- 簡単に入手できる
文学理論書ベスト3を紹介しておきます。
「文学」について考えを深めたい人には本当におすすめです。
1.『文学とは何か』テリー・イーグルトン
イーグルトンの『文学とは何か』は、文学理論の代表的な本だと言えるでしょう。
ボリュームがあるので、文学理論をがっつり勉強していきたいという人におすすめです。
2.『文学理論』ジョナサン・カラー
「がっつりはちょっと・・・」という人には『文学理論』がおすすめです。
文学の読み方にはあらゆる方法があるのですが、それらを分かりやすく体系的にまとめてくれています。
文学理論全般について気軽にざっと知りたいという人は、この本を読むと良いでしょう。
3.『批評理論入門―「フランケンシュタイン」解剖講義』廣野由美子
「そもそも文学理論って何?」という人にはこの本がおすすめです。
小説『フランケンシュタイン』を、実際に様々な文学理論を用いて読んでみるとどうなるか?ということを教えてくれます。
それぞれの理論の特徴が分かりやすく示されているので、理論ごとの特徴を理解するのに役立ちます。
ジョナサン・カラーの『文学理論』と合わせて読むことで、入門編はバッチリでしょう。
文学理論から文学へ
文学を読む上で、「文学理論」を知ることは必須ではありません。
しかし、これらを読む前と読んだ後では、確実に僕の「文学」への接し方は変化しました。
ジョナサン・カラーはこう言います。
勉強したからと言って、理論のマスターにはなれないが、逆に前と同じ位置にとどまっていることもできなくなる。ただ、読みについて新しい角度から考えられるようになるだけである。少なくとも、以前とは違った問いを立てることができるようにはなるだろうし、読む本にぶつける問いの含蓄がずっと分かるようにもなるだろう。
ジョナサン・カラー『文学理論』p24
読んだ本について考えることは、ひいては文学について考えることにつながります。
文学とは何か?の答えを探る1つの指針として、ぜひ文学理論に触れてみてください。