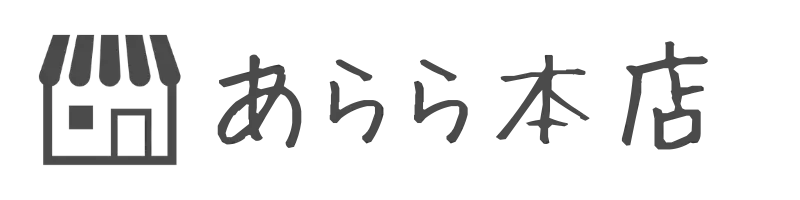『斜陽』とは?
太宰治の『斜陽』は、
- 主人公のかず子
- 弟の直治
- 母
という三人の元貴族の一家が没落する、美しくも儚い最期の様子を描いています。
しかし、この物語は「没落」していくだけの話ではありません。
彼女たちの没落を描く一方で、同時に恋という革命が「勃興」する様子も描かれています。
ここでは、そうした『斜陽』のあらすじ・考察・感想までをまとめました。
-あらすじ-
主人公のかず子は元貴族の生まれですが、戦後の影響で一家は次第に没落していきます。
そんななか、主人公は家族のある男性に恋をします。
その恋は男性の子を身ごもるという形で成就しますが、男性には捨てられます。
母は死に、弟も自殺して、残された彼女はおなかの子と二人で生きてゆく決心をします。
・-概要-
| 主人公 | かず子 |
| 物語の 仕掛け人 |
直治 |
| 主な舞台 | 伊豆の山荘 |
| 時代背景 | 戦後直後 |
| 作者 | 太宰治 |
-解説(考察)-
・姉の革命と弟の敗北
この物語のテーマの一つは、「恋と革命」です。
『斜陽』で恋をする登場人物はふたり出てきます。
ひとりは主人公のかず子です。
そしてもうひとりは弟の直治です。
彼女たちはくしくも、同じ夫婦を好きになります。
かず子は夫の上原を、直治は上原の妻に恋をするのです。
そして、主人公であるかず子の恋は、「上原の赤ちゃんを身ごもる」という点で成就します。
私のひとすじの恋の冒険の成就だけが問題でした。そうして、私のその思いが完成せられて、もういまでは私の胸のうちは、森の中の沼のように静かでございます。
太宰治『斜陽』
一方、弟の直治の恋は果たされません。それどころか、彼はそのまま自殺してしまいます。
ただ、僕は姉さんに、僕がそのひとの奥さんにこがれて、うろうろして、つらかったという事だけを知っていただいたらいいのです。
太宰治『斜陽』
このふたりの恋の命運は、
- 「恋の革命」を起こしたか起こしていないか
に左右されています。
つまり、姉であるかず子は革命を起こしたから恋が成就し、弟の直治は革命をしなかったから敗北したのです。
こうした二人の恋の勝利と敗北は、『斜陽』という物語の光と影の関係になっています。
しかし、なぜ弟の直治は「革命」をしなかったのでしょうか?
その答えは、この物語のもう一つのテーマでもある
- 「貴族の精神」
にあります。
次には、そんな「貴族の精神」について解説していきます。
・貴族の精神
『斜陽』のもう一つのテーマは「貴族の精神」です。
戦後、新たな日本国憲法によって、貴族制度は廃止されていく流れになります。
そうした時代背景をふまえて、『斜陽』では貴族である主人公一家の没落が描かれます。
ただし注意しなければならないのは、作中では「母親」だけがほんとうの貴族であると強調されていることです。
少し長いですが、分かりやすい説明の文章なので引用します。
爵位があるから、貴族だというわけにはいかないんだぜ。爵位が無くても、天爵というものを持っている立派な貴族のひともあるし、おれたちのように爵位だけは持っていても、貴族どころか、賤民にちかいのもいる。(中略)おれたちの一族でも、ほんものの貴族は、まあ、ママくらいのものだろう。あれは、ほんものだよ。かなわねえところがある。
太宰治『斜陽』
彼らの母親は作中で、「日本で最後の貴婦人」として描かれます。
これは、主人公のかず子や弟の直治は、しんからの貴族ではないということを表しています。
とはいえ、主人公のかず子はその「貴族」であることを誇りに思っていたかといえば、決してそうではありません。
むしろ、古い道徳を破る「恋の革命」をすることによって、積極的にその地位を投げ捨ててゆきます。
生まれもって与えられた自分の立場にこだわらずに生きてゆこうとする姿勢が、かず子からはうかがえます。
しかし、一方で弟の直治は、「貴族」という自らのアイデンティティに最後まで悩まされ続けます。
僕は下品になりたかった。強く、いや強暴になりたかった。そうして、それが、所謂いわゆる民衆の友になり得る唯一の道だと思ったのです。(中略)
僕は下品になりました。下品な言葉づかいをするようになりました。けれども、それは半分は、いや、六十パーセントは、哀れな附け焼刃でした。へたな小細工でした。民衆にとって、僕はやはり、キザったらしく乙にすました気づまりの男でした。彼等は僕と、しんから打ち解けて遊んでくれはしないのです。しかし、また、いまさら捨てたサロンに帰ることも出来ません。いまでは僕の下品は、たとい六十パーセントは人工の附け焼刃でも、しかし、あとの四十パーセントは、ほんものの下品になっているのです。太宰治『斜陽』
彼は、姉のように強くはなれませんでした。庶民になろうとしたのですが、彼の中にある「貴族」が抜けきらなかったのです。
つまりこれは、姉と同じように古い道徳を破れず、人の妻を手にするという恋の革命を起こせなかったことに繋がります。
ですが、それは彼にとって本望でもありました。
直治の遺書の最後は、このような言葉で締めくくられています。
もういちど、さようなら。
姉さん。
僕は、貴族です。太宰治『斜陽』
このことから、彼は革命を起こす庶民の側にはつかず、あくまでも貴族として死ぬことを選んだということが分かります。
直治は自らの「貴族」というアイデンティティを重んじたために、「革命」という手段を選ばなかったのでしょう。
貴族の精神を破って生きる姉と、貴族の精神とともに死ぬ弟。
そうした二人を照らす太陽であった「ほんものの貴族」だった母。
『斜陽』は、この三人の「貴族の精神」の違いが、作品のコントラストを生み出すよう巧みに構成されている作品です。
-感想-
・スープと構成とヘビと
僕は冒頭のスープの場面がとても好きで、ひらりひらりとスープを飲む女性がいたら、やはりそれは一種の美しさを感じるのだろうなと思います。
また、それに続く骨付きチキンの話も好きです。
形式を重んじすぎて身が入っていないと、人間はどうしても滑稽になってしまうというのは共感できるところがあります。
ところで、タイトルの『斜陽』は、陽の落ちる頃に射す夕日という意味です。
これはもちろん「没落する貴族」を喩えているのですが、冒頭が「朝」で始まっていて、終盤の夕方(没落)に向けてグラデーションのように移り変わっていく描写が見事だと思います。
母親が死んだときの描写が、「秋のしずかな黄昏」だったので、それ以降は夜に向かうということでしょうか。
だとすれば、六章の終わりか、七章の「直治の遺書」で夜を迎えているのかもしれません。
なんにせよ、「母の死」が貴族の没落のクライマックスで、それをきっかけにこの物語は大きく動いていきます。
また、この母の死は、一章にでてくる「萩の白い花」や、医者が三度も履いてくる「白足袋」などから、物語序盤から周到に用意されていることが分かります。
そういえば、この物語ではヘビが象徴的に使われています。
- 父が亡くなったとき
- 主人公がヘビの卵を燃やしたとき
- 母の死の間際
ヘビの卵を燃やしてその十日後に自分の家が火事になるのですから、その恐ろしさったらありません。
ヘビで連想するのは、やはり聖書の「創世記」でしょう。
エデンの園には食べてはいけない善悪の実があり、ヘビはその実をイヴに食べさせようとそそのかす、悪い生き物として描かれます。
『斜陽』では、母がヘビを怖がっていて、主人公はそのヘビを怖がっていません。
つまり、母が「悪いこと」を怖がっているのに対し、かず子は「悪いこと」を怖がっていないと考えることができます。
これは、かず子が「古い道徳を破る」ことを革命としている点からも読み取れますね。
しかし正直に言うと、太宰の聖書解釈についてはまだあまり深く考えていないので、もっと違う読みがあるかもしれません。
以上、『斜陽』のあらすじと考察と感想でした。
この記事で紹介した本