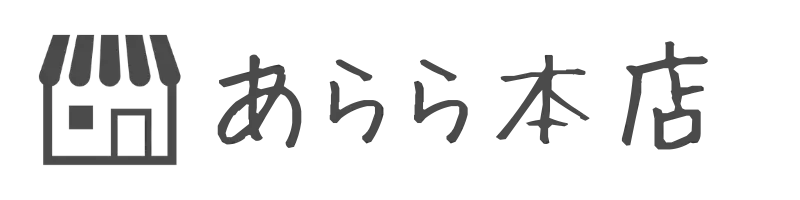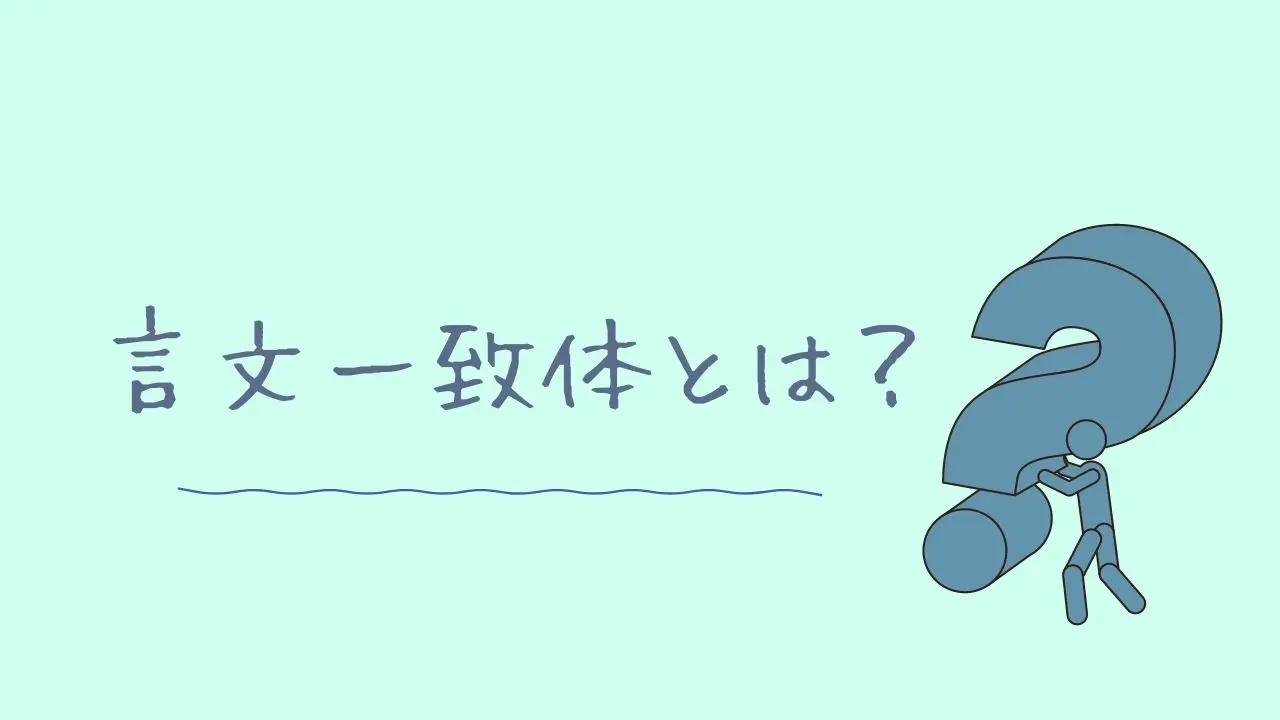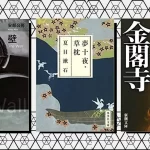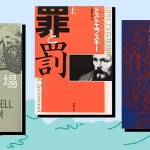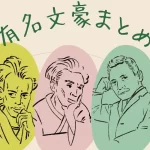言文一致運動の代表的な小説
・二葉亭四迷『浮雲』
日本近代小説の開祖とも言われる二葉亭四迷。
『浮雲』は、そんな彼が初めて言文一致を試みた代表的な作品です。
-
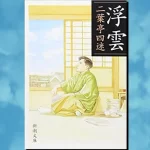
-
『浮雲』のあらすじ・解説&感想!言文一致を推し進めた二葉亭四迷の代表作!
続きを見る
また二葉亭四迷は翻訳家としても有名であり、ロシア文学を言文一致体で翻訳しています。
なかでも彼が訳したツルゲーネフの『あいびき』は、初めて言文一致体の随筆を著した国木田独歩をはじめとして、多くの作家に影響を与えました。
・山田美妙『武蔵野』
山田美妙も言文一致を推し進めた作家です。
初期の頃は二葉亭四迷と同じダ調(~だ)を用い、その後はデス調(~です、~ます)を用いて言文一致を試みました。
『武蔵野』ではダ調が、『胡蝶』ではデス調が見られます。
-
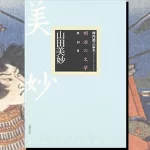
-
山田美妙『武蔵野』のあらすじ・解説・感想!言文一致を推し進めた小説!
続きを見る
もっと詳しく!そもそも言文一致とは?
言文一致とは、文章を話し言葉に近い「口語」で書こうという運動です。
明治の初期頃から、二葉亭四迷や山田美妙らによって試みられてきました。
それまでの文章は多くが文語でしたが、普段人々が使う口語とはかけ離れていたので、新しい文章表現のあり方としてこのような運動が起こりました。
- 文語例:我家に宿りたる画工は、廓外に出づるをり、我を伴ひゆくことありき。(森鴎外『即興詩人』)
- 口語例:古い話である。僕は偶然それが明治十三年の出来事だと云うことを記憶している。(森鴎外『雁』)
文語例と口語例を見比べると、語尾が変化していることが分かります。
文語体「〜なり(断定)」→言文一致体&現代「〜だ。〜である(断定)」「〜です。〜ます(断定)」
文語体「〜けり。〜き。〜つ(過去)」→言文一致体&現代「〜た(過去)」
「です・ます」などの断定や、「〜た」という過去形は、現在の私たちもよく使っていますよね。
しかし、当時はこの変化が画期的であり、当時の作家にとって言文一致運動の衝撃は非常に大きいものでした。
言文一致体がすぐに広まったわけではなかった
とはいえ、全ての作家がすぐに口語体に移行したわけではありません。
例えば、森鴎外は言文一致運動があった時代の作家ですが、彼はあくまでも文語体にこだわる姿勢を見せました。
有名な『舞姫』などは文語体で書かれた作品で、皆さんも教科書などで記憶があるかもしれません。
先の例にあるように、文語体では過去形が「〜けり。〜き。〜つ」など複数あり、それぞれ微妙なニュアンスの違いがあります。
一方、言文一致体では、過去形が「〜た」しかありません。
こうした表現の違いにより、「そういう表現はちょっと違うんだよな〜」「昔の方が使いやすいよね〜」という作家もいたわけです。
スマートフォンが出たからといって、ガラケーの人々がすぐに移行しなかったように、新しい言文一致体もすぐに広まることはなく、多くの作家は既存の使いやすい文語体を使っていました。
実際、二葉亭四迷の『浮雲』から約10年が経った頃に、ようやく言文一致運動が再燃したのでした。
言文一致体をスタンダードにさせた「語り」の変化
しかし言文一致体には、語尾がシンプルだからこそ、誰が誰に対して話しているのか分かりにくいという問題がありました。
そこで新しく出てきた言葉が、「彼」「彼女」「私」という人称です。
このような人称は、現代では一人称や三人称と呼ばれ、語り手≒主人公を通した、より深い内面の表現が可能になるというメリットがあります。
言文一致体は、これまでの文語よりも、主人公の内面を前面に押し出した文章表現が得意だったわけです。
こうした流れで出てきたのが、田山花袋の『蒲団』や島崎藤村の『破戒』といった、いわゆる「私小説」と呼ばれるジャンルの走りとなる作品でした。
言文一致運動→語りの変化による内面の深化→私小説の誕生
このようにして、私小説は近代文学の主流となり、その流れは現在にも続いています。
逆に言うと、私小説の形式を可能にしたのが、言文一致運動による口語体の出現と言い換えることもできるでしょう。
私小説は、言文一致体だからこそ書くことができた。
これが、言文一致体をスタンダードな文章表現にさせた大きな理由の一つです。
こうして時代や文壇の潮流にもまれながら、口語体は徐々に一般的なものになっていき、現在の形へと辿り着きます。
つまり、今ここで書かれている僕の文章も、言文一致運動が起こったために、口語に近いくだけた表現が可能になっているのです。
そうした意味では、言文一致運動は、日本語の世界を変えた革命だと言ってもよいでしょう。
日本の文学史をもっと知ろう!
以上、言文一致体について、代表作から概要までを見てきました。
ここで見てきた『浮雲』を出発点として、日本文学史がどのような変遷を経てきたか、一目で分かる年表をまとめたので、知りたい方はぜひ読んでみて下さい。
-

-
近代文学作品の年表一覧!明治~平成までの主要作品まとめ!
続きを見る
この記事で紹介した本